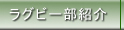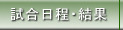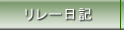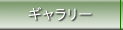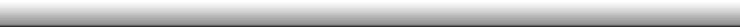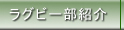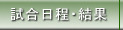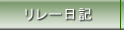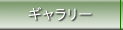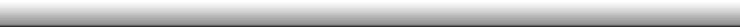|
昨年の慶應戦の直後、選手の何人かが私の顔を見るなり、沈痛な面もちで詫びてきた。正直、驚きばかりが大きくて、どんな言葉をかけられたのか明確には覚えていないが、選手たちの辛そうな気持ちだけが伝わってきて、そんな彼らに対して何も言ってあげられない自分が歯痒かった。
昨年は、女子マネージャーが急激に減った年だった。にもかかわらず、マネージメントシステムをそれに見合った形で変革していけるようなそんな時間もなく、慢性的な人手不足のまま、来るべき対抗戦・ジュニア選手権の対応におわれているというような状態にあった。マネージャー1人1人の負担が増大したことで、しんどいにはしんどかったが、それでも自分にできる限りのことはやっていきたいと思っていた。 ところで私は、基本的に、選手というものは、女子マネージャーの存在など眼中にないものだと思っていた(プレイングマネージャーの立場にあるマネージメント部員は例外として)。だから、慶應戦後のことは、大げさに言えば衝撃だった。
私は、毎日の練習でも試合の時でも、そのやっている仕事が、東大ラグビー部にとって役立つかどうかということを考えてやってきた。選手が私たちの行為に対して、どう思っていても(無関心でも)、東大ラグビー部にとってよいことであれば、それで一応はいいのだと思っていた。しかし、選手の中には、どんなに厳しい状況にあっても、私たちのことまで思ってくれている人がいるのだということを改めて感じた。
それからの私は、選手の1人1人に対して、私にできること、やってあげられることというのをそれまで以上に考えるようになったし、東大ラグビー部のことを考える時間がそれまで以上に増えていった。文字通り没頭していった。ラグビー部以外のものはなかったし、生活のすべてがラグビー部の為にあったような気がする。そして、以前よりも、東大ラグビー部のことが大事になったし、選手の1人1人が大切な存在になった。
そういう気持ちでやっていけたから、どんな無茶でもできたし、自分自身納得のいくところまで仕事ができたのだと思う。以前のように、責任感に突き動かされるのではなくて、私が心の底から望んでやっていくことができた。
青学戦後、「女マネのためにも勝ちたい」と戦前に主将が言っていたとコーチから聞かされた。対抗戦の主将の中で、こんなことを言ってくれる主将は他にいないと思う。そして、主将をはじめ、私たちをこれほどまでにがんばらせてくれた同期には、言葉ではいいつくせないほど感謝している。(彼らの私たちに対する信頼なくして、昨年の私はなかったと思っている。) 昨年の一年間は、これまでに経験したことがないほどしんどい思いもしたが、これから先10年たっても20年たっても忘れられないものになるだろうと思う。
後輩のみんなも(特にマネージャーの人たちも)、そんな、密度の高い時間を過ごして欲しいと思う。
|