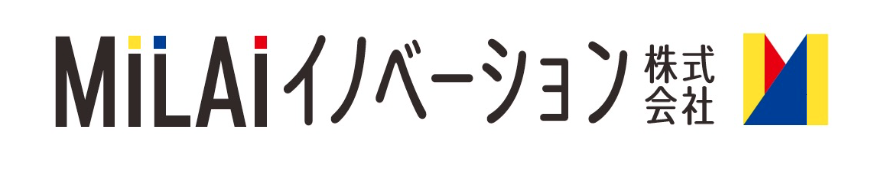- トップ
- 全体トップ
- 東京大学ラグビー部リレー日記
- ラグビー部リレー日記
ラグビー部リレー日記
| <<前へ | 次へ>> |
受け継ぐ
投稿日時:2022/07/07(木) 15:30
個性の結晶体とも言える猿渡からバトンを受け取りました、3年の西久保です。開成出身の僕は、地方公立高校の人は真面目な人が多いと思っていたのですが、どうやら宮城出身の人はその真面目のベクトルが90度くらいズレているようです。(サンプル数2)
3ヶ月も経たないうちにまたリレー日記が回ってきてしまいました、そんな短期間で書くネタができるようなおめでたい人間ではないので勘弁してほしいです笑。僕のようにネタがない、ネタがないなどと言っている上級生が5人揃った僕のスモブラはもう何ヶ月間開催されていないでしょうか、新加入の片桐と翼には申し訳ないなと若干思いつつも、相変わらずネタのない生活を送っています。
まだ今シーズンは地獄の夏、勝負の秋とまだまだ続いていきますが、自分が次のリレー日記を書くのは来シーズンになるでしょう。その頃には今の4年生がいなくなってしまうと考えると、早くも寂しくなってしまいます。
コロナ禍で友達を1人も作れない中(コロナのせいにしておきます)、東大ラグビー部に飛び込みましたが、当時の先輩方は寛大に、優しく僕たち3年のことを受け入れて下さいました。
藤井さんの代は、ラグビー的にも人間的にも、とにかく1人1人のレベルが高かったと思います。もちろん皆さん優しくて面白い方々であるのですが、その動作や言動、笑い1つとっても、経験の深さからくる大人の余裕みたいなものが感じられ、僕はその威厳というかオーラというか、何かそういうものにいつも圧倒されていました。(あくまでも自分のイメージです)
杉浦さんの代は、女子スタッフが1人もいないという、僕らと似たような境遇だったので少し親近感はありました。ただ本当にラグビーが上手い方々で、Aチームの中で練習しててもプレッシャー感じまくって、正直生きた心地してませんでした。(当時1年ながらスタメン張ってた昴は本当にすごいなと思ってました)おちゃらけた感じの人もいましたけど、決して自分の弱みは見せないというか、そういう部分は強かさを感じていました。(イメージですが)
そして今の4年生は、三方さんの言葉を借りれば、本当に多種多様な方々だと感じます。人間関係も複雑なところで絶妙なバランスを保っていて、そういう意味では、単一分子内でただわいわいやっている今の3年とは真逆の存在であるような気がします。でもそんな僕らのことをいつも気にかけてくれる温かい先輩方です。お互いに弱みを見せ合えるという点では、先輩というより仲間という意識の方が強い気がします。(失礼かもしれないですが、イメージです)
簡潔に言えば、上の代から順に、尊敬・敬愛・親愛みたいな感じですかね。どの代も頼りになる偉大な先輩方なのですが、やっぱり國枝さんの代は長く接していることもあって、1番思い入れが深いです。先輩達の涙は嫌というほど見てきたので、今年こそは対抗戦で良い結果出して、4年には笑顔で卒業してもらいたいと思います。まだまだ一緒に頑張りましょう。
そして次は僕らの代が最上級生としてチームを牽引しなければならないと考えるとどうしても不安になってしまいます。今の後輩たちには僕らはどのように見えるのでしょうか。自分は別に後輩にナメられるのは構わないんですが、たまにしか挨拶を交わさない近所のおっちゃんみたいな感じで思われていたらショックなので、その場合は、まずはお友達としてからでいいので、仲良くなりたいなと思います。
次は粋とプロテインでメキメキと体をデカくし、フランカーへの道を順調に辿ってきている?、2年の平川にバトンを回します。最近の彼には、本厄並みの不幸が立て続けに起こっていると感じるので、何か良い話を提供してもらいたいです。
駅事務所にて
投稿日時:2022/07/05(火) 17:06
私は直近の3週間で2回、スマホを駅で落としました。1回目は聖蹟桜ヶ丘駅、2回目は千駄ヶ谷駅です。2回とも駅事務所に届いており、無事に回収することができました。拾って届けてくださった方、手続きをしてくださった駅員の方、一緒に探したり心配したりしてくださった部の皆様に心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
ところで、スマホの端末を持ち逃げして転売したり、中のデータを抜き取ったりすれば、やりようによっては相当の利益が上がるはずです。なぜ私のスマホはそうした被害に遭わなかったのでしょうか。
私は、自分のスマホの見た目が役に立ったと考えています。このスマホには、高校入学と同時に買った手帳型のケースが付いています。当然ながら傷みがひどく、ケース表面の皮が半分以上はがれて内部のプラスチックの板が露出しています。また、ケースの縁はプラスチック板が割れてギザギザしており、不用意に触ると危険です。
この、明らかに金銭的価値の低いケースに包まれていたことによって、私のスマホは盗難を免れたのだと思います。「明らかにぼろいスマホだ」「どうせ持ち主もロクな人じゃないし、大したデータは入ってないだろう」等と悪い人たちに考えさせることができれば、私の勝利です。
私の祖母はスマホを持っていますが、「落としたら大変だから」と言い、スマホを金庫にしまって出かけていきます。私は近いうちに、ダメージ加工のスマホケースを買って贈ろうと思います。きっと安心してスマホを携帯できるようになるでしょう。
次は、開成出身の西久保さんです。地方の公立高校出身の私が「開成の人」に対して勝手に抱いていたイメージとはまるで違う、身体能力の非常に高い先輩です。羨ましいかぎりです。
テキーラ!テキーラ!
投稿日時:2022/07/03(日) 18:45
昨日は学習院大学との試合がありました。まだまだ課題は沢山あり、秋までに改善し、成長しなければならない点も山ほどありますが、やはり勝てたというのはとても嬉しいことです。勝って反省出来ることに感謝しながら、秋シーズンに向けて一日一日を大切に過ごしていきます。どうか応援よろしくお願いいたします。
私事で恐縮ですが、最近髭を伸ばし始めました。伸ばし始めた理由は単純で、就活が終わり自由な時間が増えたため、何か見た目に変化を起こしたいなあと思ったからです。(いつも一緒にアップをしている本多の髭に憧れたからというのもほんの少しあります。)他にも髪を染めるなど、自分の中で色々候補はあったのですが、髪を派手に染めていると相手から舐められそうなのでやめました。「あの金髪デブ見た!」みたいな感じで相手にノミネートされても嫌ですし、髭に目を付けて正解だったと思います。
髭を伸ばし始めたのは6月の始めくらいでしたが、6月の半ばにはいい感じに口髭が生えてきました。自分で楽しむために始めた髭でしたが、やはり周りからの反応も気になるところです。一体どう思われているのでしょうか。
結果としては、意外と好評だったと言って良いと思います。「結構似合うね」とか「迫力あるね」とか、好意的な言葉を頂けることが多く、内心非常に嬉しいです。一方でラグビー部の同期など、近しい人間にはそこまで好評ではなさそうです。好意的な言葉が社交辞令でないことを祈るばかりです。
次は期待の新人、猿渡にバトンを回します。彼は規格外の体格を誇り、ラグビーのプレー中は非常に迫力があります。またプライベートの私服は、半袖短パンに使い古したリュックサックというポケモンマスター的スタイルのため、グラウンド外でも異彩を放っています。
花火の思い出
投稿日時:2022/07/01(金) 23:00
新歓といえば、その時期にはどうしてもラグビー部はWARRIORS(東大アメフト部)とはライバル関係になってしまいますが、僕はWARRIORSにとてもお世話になった関係で今でも勝手に仲間意識をもっています。特に今年の春シーズン、僕の同期の代が二年生にしてすでに何人もスタメンに入っているのをSNSで知って、「さすがだな」と思うと同時に、僕も負けじと活躍しなければと良い刺激を一方的に受けまくっていました。
逆に僕も彼らに少しでも影響できるよう、ラグビー部で頑張っています。お互い頑張ろう。
さて、アニメについて話します。
僕は中高の男子校時代、正直アニメを見ている周りの友達を小馬鹿にしていました。現実を見ないオタクだと思っていじっていました。当時バカにした人、ごめんなさい。今僕はそのアニメにはまっています。
結論からいえば、現実を見ていなかったのは当時の僕かもしれません。中高は男子校という閉ざされた同質社会で死ぬほど楽しかったですが、それと同時進行で失われていた共学の青春に僕は気付いていませんでした。
僕は今、失った青春をアニメを見て取り返しています。転校、キュン、文化祭、意識、席替え、恋愛、花火大会、告白、デート、すれ違い、仲直りといった様々な種類の青春を、擬似的に経験しています。ここ2ヶ月くらいで色々なアニメを見て、青春をだいぶ取り返してこれたので良かったです。これからもたくさんのことを経験して成長していきたいと思います。
次は四年生の三方さんに回します。声がかっこよく喋っていると面白いし優しいし、そのうえギターを弾ける、男として憧れの先輩です。
新歓の総括
投稿日時:2022/06/28(火) 20:17
2年のフィクサーこと一木からバトンをもらいました、杉井です。
今年度、新歓を担当しました。結果としてプレイヤー15人、マネージャー2人が入部を決めてくれました。大変嬉しく、ありがたく思います。せっかくの機会ですので、今年度の新歓を振り返りたいと思います。
今年度の新歓は昨年に比べて大変苦労した年でした。例年新歓が落ち着いている5月1日の時点で入部確定者が8人しかおらず、日々不安で胃が痛む思いでした。最後には多くの新入生が入部を決めてくれ、本当に良かったと思っています。
後輩の役に立つ可能性を考え、ここまで苦労した原因を分析したいと思います。
・イベントに来てくれた新入生の囲い込みが甘かった
今年は、4月2週目の末にタグラグビー大会、3週目の末に新歓セブンスという2つの大きなイベントを実施しました。このイベント自体への集客は大成功で、例年を大きく上回る50人以上の新入生が参加してくれました。
ただ、イベント後奢り飯に連れて行けない・部員への新歓への意識づけが足りていなかった・新入生の数が部のキャパを超えていた、などが原因で、せっかくイベントに来てくれた新入生へのその後のアプローチが甘くなってしまいました。ここで逃した潜在的な入部者はたくさんいたのではないかと思います。
・アメフト部と例年以上に競合した
これが今年大きく苦労した一番大きな理由です。
今年は特に、ラグビー経験者がアメフト部と迷うケースが多く、経験者の早期確保に失敗しました。経験者を早期に確保することは新歓において非常に重要な戦略で、経験者が勧誘を手伝ってくれる、「ラグビー部人気そう」な空気を醸し出すことができるといったメリットがあります。これに失敗したため、「同期が少なそうだから入部をためらっている」という子が続出しました。
経験者の早期確保には、早めの経験者会実施と叙々苑奢り、テント列等での早期接触がとても大事です。(どちらもコロナで実施できませんでしたが、、)
以上のように沢山の苦労はありましたが、なんやかんや無事終えられて一安心です。
最後になりましたが、新歓でお世話になった全ての方々にこの場を借りてお礼申し上げます。
特に、江上様はじめOBの皆様にはお忙しい中ツテを使って経験者の連絡先確保に尽力していただきました。大変ありがとうございました。
また、新歓委員のみんなもそれぞれ忙しい中協力してくれてありがとう。とても助けられました。素晴らしいメンバーでした。
次は、怪我から復帰早々、鮮やかなトライを決めた寿太郎に回します
| «前へ | 次へ» |
2025年11月
| <<前月 | 翌月>> |
| |
アーカイブ
- 2025年11月(1)
- 2025年10月(13)
- 2025年9月(11)
- 2025年8月(11)
- 2025年7月(11)
- 2025年6月(10)
- 2025年5月(8)
- 2025年4月(9)
- 2025年3月(9)
- 2025年2月(7)
- 2024年12月(18)
- 2024年11月(12)
- 2024年10月(12)
- 2024年9月(13)
- 2024年8月(11)
- 2024年7月(12)
- 2024年6月(8)
- 2024年5月(9)
- 2024年4月(8)
- 2024年3月(8)
- 2024年2月(11)
- 2024年1月(5)
- 2023年12月(9)
- 2023年11月(12)
- 2023年10月(11)
- 2023年9月(12)
- 2023年8月(11)
- 2023年7月(11)
- 2023年6月(8)
- 2023年5月(7)
- 2023年4月(8)
- 2023年3月(7)
- 2023年2月(9)
- 2023年1月(3)
- 2022年12月(23)
- 2022年11月(14)
- 2022年10月(13)
- 2022年9月(14)
- 2022年8月(14)
- 2022年7月(16)
- 2022年6月(10)
- 2022年5月(11)
- 2022年4月(12)
- 2022年3月(10)
- 2022年2月(9)
- 2021年12月(12)
- 2021年11月(12)
- 2021年10月(14)
- 2021年9月(12)
- 2021年8月(12)
- 2021年7月(12)
- 2021年6月(11)
- 2021年5月(12)
- 2021年4月(11)
- 2021年3月(13)
- 2021年2月(4)
- 2021年1月(14)
- 2020年12月(11)
- 2020年11月(12)
- 2020年10月(13)
- 2020年9月(12)
- 2020年8月(14)
- 2020年7月(12)
- 2020年6月(12)
- 2020年5月(13)
- 2020年4月(12)
- 2020年3月(13)
- 2020年2月(5)
- 2019年12月(10)
- 2019年11月(15)
- 2019年10月(11)
- 2019年9月(13)
- 2019年8月(13)
- 2019年7月(10)
- 2019年6月(8)
- 2019年5月(13)
- 2019年4月(7)
- 2019年3月(7)
- 2019年2月(5)
- 2019年1月(7)
- 2018年12月(15)
- 2018年11月(12)
- 2018年10月(15)
- 2018年9月(10)
- 2018年8月(7)
- 2018年7月(6)
- 2018年6月(10)
- 2018年5月(12)
- 2018年4月(11)
- 2018年3月(5)
- 2017年12月(11)
- 2017年11月(13)
- 2017年10月(12)
- 2017年9月(11)
- 2017年8月(12)
- 2017年7月(10)
- 2017年6月(10)
- 2017年5月(17)
- 2017年4月(10)
- 2017年3月(13)
- 2017年2月(4)
- 2016年12月(15)
- 2016年11月(12)
- 2016年10月(14)
- 2016年9月(12)
- 2016年8月(12)
- 2016年7月(15)
- 2016年6月(9)
- 2016年5月(9)
- 2016年4月(11)
- 2016年3月(10)
- 2016年2月(7)
- 2015年12月(5)
- 2015年11月(6)
- 2015年10月(4)
- 2015年9月(6)
- 2015年8月(2)
- 2015年7月(5)
- 2015年6月(6)
- 2015年5月(7)
- 2015年4月(4)
- 2015年3月(4)
- 2015年2月(10)
- 2015年1月(11)
- 2014年12月(10)
- 2014年11月(6)
- 2014年10月(9)
- 2014年9月(9)
- 2014年8月(5)
- 2014年7月(3)
- 2014年6月(3)
- 2014年5月(5)
- 2014年4月(6)
- 2014年3月(9)
- 2014年2月(5)
- 2013年12月(13)
- 2013年11月(14)
- 2013年10月(16)
- 2013年9月(15)
- 2013年8月(8)
- 2013年7月(9)
- 2013年6月(9)
- 2013年5月(9)
- 2013年4月(10)
- 2013年3月(9)
- 2013年2月(3)
- 2012年12月(7)
- 2012年11月(3)
- 2012年10月(10)
- 2012年9月(7)
- 2012年8月(9)
- 2012年7月(5)
- 2012年6月(8)
- 2012年5月(8)
- 2012年4月(8)
- 2012年3月(10)
- 2012年2月(8)
- 2011年12月(6)
- 2011年11月(6)
- 2011年10月(7)
- 2011年9月(9)
- 2011年8月(10)
- 2011年7月(5)
- 2011年6月(5)
- 2011年5月(9)
- 2011年4月(7)
- 2011年3月(8)
- 2011年2月(4)
ブログ最新記事
- モチーフで見る部員の部屋 (11/07 00:32)
- 自己開示 (10/31 13:42)
- ポスト考古学実習 (10/28 21:23)
- 白球に魅せられて (10/25 18:37)
- LoveType16 (10/25 11:46)
- 休みたい (10/25 07:09)
- No pain, no gain. (10/24 12:29)
- 銀杏 (10/18 07:50)
- ラグビーマン決戦・徳島頂上バトル (10/17 19:33)
- 名古屋に行きました。 (10/17 00:13)
- 勇気のいらない親切 (10/13 16:15)
- 懐かしのDAYS (10/10 16:14)
- アレルギー (10/04 23:56)
- 炎 (10/02 23:50)
- タックル怖くね? (09/29 22:08)
- surprise! mf (09/26 22:52)
- 気まずいよ展 (09/26 19:48)
- ライブハウスで会おうぜ (09/23 17:15)
- Work with ChatGPT? Talk with ChatGPT. (09/20 17:58)
- 素人はSNSするな、僧侶コスプレ、オープンマリッジ (09/19 00:04)





.jpg)