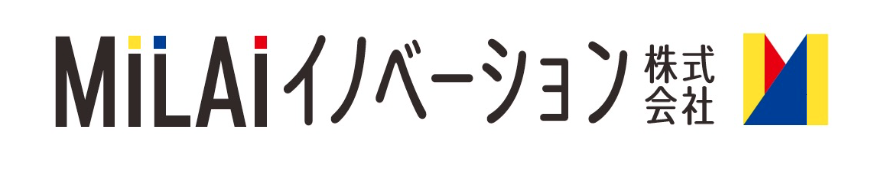- トップ
- 全体トップ
- 東京大学ラグビー部リレー日記
- ラグビー部リレー日記
ラグビー部リレー日記
| <<前へ | 次へ>> |
new playlist
投稿日時:2025/06/27(金) 22:30
美玖さんからバトンを受け取りました。2年の玉置です。美玖さんはいつも落ち着いた雰囲気でスタッフの仕事をしている印象がありますが、同期スタッフによるとたまに見せるお茶目な姿が魅力のようです。ぜひ仲良くさせてください!また最近は様々なこじれを直すための行動が目についてしまっているようです。中身はまだ誠実だと思うのでまた合コン開いてください。
1ヶ月ほど前にトレーナーの方々や先輩方、同期のおかげで無事フルコン復帰することができ、試合に出られるようになりました。本当にありがとうございました。そこで、自分は試合前、会場に向かう電車の中でよく音楽を聴くのですが、いつも同じ曲を聴いている気がしたのでそれらをまとめてプレイリストを作ってみようと思います。
①ケセラセラ / Mrs. GREEN APPLE
まず1番目の曲はミセスさんのケセラセラにします。ラグビー部内にはミセスさんのアンチの方々が多いと聞きました。確かにミセスさんが女性うけを狙っているようで気に食わないという意見も理解できます。この曲について言うと、自分は「わかっているけれど私を愛せるのは私だけ/生まれ変わるならまた私だね」のところがとても好きでリピートしてしまいます。このような自信に満ち溢れた歌詞を軽く歌いきってしまう歌い手の圧倒的自信に憧れ、自信をもって試合に臨みいいプレーをしたいと強く感じます。また、平時に聴くと一生独り身でいることを肯定してくれるように感じられます。
②W / X / Y / Tani Yuuki
2番目の曲はTani YuukiさんのW / X / Yにします。こちらもラグビー部内にアンチの方々が多いと聞きました。確かに歌手の名前が日本語ではなく英字表記となっているところに若干の違和感を覚えてしまうのは仕方がないと思います。自分はこの曲の「つい、繰り返すと忘れてしまいそうになるよ/振り返ると日々が当たり前じゃないこと」、「君がいなきゃ今もどこかで動けないままの僕で/ありがとうを伝えたいのですこれからは僕が支えてくって」の部分を何回も聴いてしまいます。この曲はおそらく恋についての曲ですが、試合前に聞くとこの時間をラグビー部の仲間と共有できることの喜びと、そこからくる試合での責任感のようなものも感じ身が引き締まります。
③レオ / 優里
3番目の曲は優里さんのレオにします。この曲を聴くと間が抜けたような顔をした星の顔が思い浮かびます。星とはいろいろとこじれ合う仲ではありますが、星の思い切ったプレー、ハードなプレーを思い出すと力をもらえます。そんな星ですが現在は肩の怪我でリハビリに励んでいます。そういえば、彼は僕の復帰戦の前に「防衛大学の自販機安いんだよね。活躍したら俺にジュース奢れよ。」とよくわからないことを言ってくれました。奢るのを忘れてしまったので復帰戦の時に活躍してチャラにしてください。
④Unstoppable / Sia
4番目の曲はSiaさんのUnstoppableにします。この曲はunstoppableという言葉が大量に出てくるのでBBBのうちの一つであるBecome Unstoppableが強烈に意識されます。数えてみたらunstoppable todayという歌詞が23回も出てきました。曲調も熱い感じなので最後にテンションをあげるのに良い曲です。
これからの試合はこのプレイリストを利用して良いマインドで試合に臨むとともに、試合でより良いプレーができるように精進していかなければと思います。
次は猿渡さんにバトンを渡します。猿渡さんは言葉遣いが丁寧すぎるほどで、スクラムやラインアウトの確認もまた丁寧で自分も見習わなければと感じます。またお台場でのレクはとても楽しかったです。亀井と3人で開いたAMFはいい思い出です。
焼肉屋さん
投稿日時:2025/06/22(日) 18:30
今日の立教戦での怪我からのスタメン復帰おめでとうございます。りんたろうさん率いる福元組の活動はあと半年となりましたが、チームのより良い結果につながるよう頑張ります。
りんたろうさんのいじりスキルがすごいと噂で聞いていたので、どんな紹介をされるのかドキドキしていましたが、良く書いていただきありがとうございます。今は野球と同じくらいラグビーも大好きです。
りんたろうさんの紹介を書きたかった人はたくさんいると思うので、大したことを書けなくて申し訳ないです。
さて、毎回リレー日記のテーマにはだいぶ悩みますが、今回は焼肉屋さんについて話そうと思います。本当はもっと深い話をしたかったのですが、最近時間が取れなかったので浅めの内容となることをお許しください。
私は、焼肉が大好きでいろんなお店に行くので、その中でもおすすめだなと思ったお店を紹介したいと思います。じめじめと暑くなってきましたので、スタミナのためにもよさそうなのがあったらぜひ行ってみてください。
・焼肉冷麺だいじゅ
大塚駅から徒歩2分ほど。
タンとユッケが美味しかったです。ユッケは完全に生ではなく、ちょっとホイルの上で焼く感じでした。
・味道苑
小規模なチェーン店のようです。私は池袋店に行きました。
値段が安めなのに美味しかったです。あとお皿がおしゃれ。
・新宿焼肉芝浦ホルモン
新宿駅の西口あたりにあります。
一人前の量が多めで美味しかったです。
レバ刺しが美味しすぎました。さすがホルモン屋さん。
・たれ焼肉 金肉屋
三軒茶屋の本店に行きました
なんか似たような名前のお店が渋谷とかにもあるみたいなんですが、系列店ってことなんですかね。
タンとミルフィーユなんたらみたいなの(名前忘れました)が美味しかったです。
・焼肉うしこぞう
歌舞伎町のど真ん中!みたいな、ちょっと治安がアレってところにありますが、お店の外装と内装はとても綺麗で、肝心のお肉もとても美味しかったです。
タンとユッケと上ミノが美味しかったです。多分特に塩物が美味しいんだと思います。
5個くらいにしておきます。
次は2年生の玉置にバトンを渡します。
玉置は未経験ながら着実に体と実力を成長させ、怪我から復帰してからAチームのスタメンに定着しているすごい後輩です。大人や先輩など、いろんな人の玉置に対する話を聞いて、すごい期待されていてすごいなあと良く思います。勝手に寡黙な感じなのかなと思っていましたが、特に最近何だか色々イメージと違う話を聞くので、ぜひ話してみたいです。
Enjoy
投稿日時:2025/06/21(土) 20:08
悪いことをすると思っているから声をかけているなんてことは全くありません。何か後ろめたいことでもあるのでしょうか?
復帰してからちょうど1ヶ月経ちました。田崎先生、工藤さん、笠原さんをはじめとする様々な方のサポートのおかげで復帰することができました。本当にありがとうございました。
ラグビー部に入ってから何度かDLに入ることがありましたが、その原因のほとんどが下肢の怪我でした。多少肘や肩が痛むことは下級生の頃にもありましたが、まともに片腕が使えなくなるというのは今回が初めてのことでした。ポジション柄、ラグビーといえばパスという程に、個人練習の時間はパスに割いてきました。今までは、怪我をしたとしてもパスの練習をしている間、ラグビーをしている感じを多少なりとも味わうことができました。しかし、今回パスをまともに投げることすら許されない状況になり、とても困りました。
そのため、何ヶ月ぶりかにパスを投げられるようになった時はとても嬉しかったです。なんてことのないアップのランパスすらとても楽しく、鷲頭を長々と付き合わせてしまったことを覚えています。また、ノーコンタクトの練習に参加できるようになり、ユニットで4vs3などの実践的な練習に参加できた時は、ラグビーができる喜びをとても感じました。久々に心の底からラグビーが楽しいと思えた瞬間でした。
勝ちたいという思いや、こうあらねばならないというものに捉われることによって、ついラグビーを楽しむというところから遠く離れた感情でプレーすることになりがちだったことに気付かされました。
勝ちたいという思いや、上手くなりたいという思いは成長するために必要不可欠なものだと思います。ですがそのような感情ばかりが先行しすぎると、理想の自分に至らないことを不甲斐なく思うことや、上手くいかないことを悔しく思うことばかりになり、ラグビーを楽しむという感情を忘れるようなことになり得ます。
ラグビーができるということは決して当たり前のことではないです。ラグビーが好きで、たくさんの人に支えていただきながら大学でまでプレーさせていただいている。この恵まれた状況へ感謝しながら、ラグビーを最大限楽しめるように日々真摯に取り組みたいです。
次はみくちゃんにバトンを渡します。1年生の頃から広報セクションで大活躍でしたが、今年は副務としてもチームを支えてくれています。いつもありがとうございます。
みくちゃんと言えば無類の野球好きのイメージですが、まだ好きなスポーツランキング1位は野球のままですか?そろそろラグビーが野球においついてきましたか?
玉ねぎ
投稿日時:2025/06/17(火) 17:09
目黒からバトンを受け取りました、3年生の木村デイビス友志です。決勝にトライ取った目黒、かっこいいと思う。今年と来年の活躍を楽しみにしている。
最近、料理をもっとするようになったけど、ひとつ問題があって、玉ねぎに目が弱すぎて涙が止まんない。涙が出ないようにいろんな方法を試してみた。効いたものとダメだったものまとめます。
玉ねぎを冷やす
切る30分前くらいに玉ねぎを冷蔵庫に入れておいたら、マシになった。ほとんど涙出ませんでした。冷凍庫に10~15分入れるのもアリだけど、ちょっと硬くなって切りづらくなった。
よく切れる包丁を使う
よく研いだ包丁に変えたら、涙の量が減った。スパッと切れて、目がほとんど痛くならなかった。地味だけど、大事。
扇風機で風を流す
横に小さい扇風機を置いて風を横に流すのも良い。目に何も来なくて、ラクに切れた。
ゴーグルをつける
簡単で効果的やけど、ダサイ。
濡らしたキッチンペーパーを置く
濡れたキッチンペーパーを近くに置いてみたら、ちょっとだけマシになった気がした。すごい効果ではない。
効かなかったやつ
ガム噛んだり、パンくわえたり、ロウソクつけたり、水飲みながら切ったり…。全部やってみたけど、効果なし。
読んでくれてありがとう、お役に立てれば幸いです。
次は福元キャプテンにバトンを渡します。福元さんはとても優しい人だから、いつも俺の様子を伺ってくる。でもそれは、俺が何か悪いことをすると思っているからかもしれない。
同期
投稿日時:2025/06/16(月) 18:00
こっからは同期紹介をしたいと思います。過去に何人かやってますが、僕目線でみんながどう見えているのかや、近況について書きたいと思います。
池田 琥士郎 ウイング <運動神経 ★★★★★>
今年から試合でバンバン活躍しているこじろーです。ラグビーのセンスが高く、努力家でもあります。駒場の近くに引越してきたそうなので今度行きます。
伊藤 慎 スタッフ <飲み適正 ★★★★★>
最近学校が忙しい原井くんの代わりにたくさん笛を吹いています。そんな彼はお酒を飲ませると豹変します。普段寡黙なのにいきなり肩を組んでイキってきます。酒の席では彼にシンビンが必要です。
小川 雄大 センター <文系 ★★★★★>
いかにも文系大学生なゆうだいです。ファッションに力を入れており、参考になる一方で髪型をパイナップルと揶揄されたりしています。謎の財団に所属しており、最近は謎の薄い本を読んでいます。根はいい人です。
亀井 亮衛 フランカー <肩幅 ★★★★★>
ちょうちょ研究家兼インターネットヒーローの亀ちゃんです。彼にしか通じないような話がたくさんあるので欠かせない存在です。平パスがうまい。
河村 達哉 プロップ <家の広さ ★★★★★>
ムードメイカーであり数々の逸話を残す河村。かつて神童と呼ばれた彼はこれからプロップに挑戦するようです。最近は怪我が多いのが心配です。家がとても快適です。
カンリフ 慈英斗 センター <サイズ ★★★★★>
期待の大型センター。AMFの時はよく、"He can’t speak Japanese." と紹介されるなど外国人いじりをされています。ですがこの前行ったカラオケでは合唱曲Believeを歌っていたので、中身はしっかり日本人なんだとわかりました。
久代 凌士 センター <リア充 ★★★★★>
新しく入った彼はむさ苦しいラグビー部に真の陽キャの風をもたらしました。ゆうだいとかみなととか自称陽キャも比になりません。黙々と練習していたり、熱心に試合を見る姿からラグビー愛が伝わってきます。まだまだ知らないことが多いので掘り進めていきたいです。
坂田 大樹 センター <胸板 ★★★★★>
東大の秘密兵器であり、ゲーム仲間でもある坂田です。もうすぐ怪我から復帰するらしいのですが、このリハビリ中に一回り大きくなっていて、期待がもてます。最近は合コンを前日にドタキャンしたそうで、体のデカさとは裏腹に奥手なところもまた魅力です。
玉置 雄大 フランカー <漢 ★★★★★>
ガチムチ玉置です。バイトを始めたそうです。きっと制服もはちきれんばかりだと思います。最近は恋愛にも本気だそうで、試合でボールを持った時の彼のように女の子にもpenetrateしていって欲しいと思います。
長岡 琴音 スタッフ <おもてなし ★★★★★>
いつもテーピング等ありがとうございます。最近はなんだか部の話題の中心にいることが多く、彼女の人気を物語っています。幸せそうですね。
野村 晃一朗 ロック <丁寧な暮らし ★★★★★>
落ち着いた空気のあるノムさん。練習中に疑問や意見があればコーチや先輩に積極的に相談し、学んでいる姿が印象的です。でもラグビーよりサッカーの方が好きらしい。
原田 皓生 プロップ <passion ★★★★★>
いつも元気なはらこーです。くだらないけど吹き出してしまう彼のネタは個人的に好きです。イギリス仕込みのレインボーなワードセンスをこれからも保って欲しいです。
星 玲凰 フッカー <愛嬌 ★★★★★>
いつも笑顔で、そしてなぜかいつも部室にいる星。手術を終えてリハビリ中ですが、きつい中でもその笑顔を絶やさないでもらいたいです。そして新たに魅力的な人を見つけてほしい。
細尾 匡彦 スタッフ <京都人 ★★★★★>
彼からは部内で一番関西人らしさを感じます。初対面の時のツッコミの鋭さには驚きました。もっと話せる機会が増えればいいなあ。
三上 昭文 ロック <実らぬ恋 ★★★★★>
体も声も態度もでかいけれど、うまくいかないこともあるようです。それでもポジティブにいきましょう。麻布で金髪だった頃を思い出してください。
湊 大樹 スタンドオフ <理一ドイツ語 ★★★★★>
最近は女の子を沼らせるクズ男を目指しているというみなと。服装から聴いている音楽、口調まで寄せていっているらしいのですが、本質的な部分は変わってないと思います。
個性あふれる楽しい仲間がいて嬉しいです。
次は東大のトライゲッターゆうしにバトンを渡します。とてもスタイルが良くて羨ましいです。今後の活躍も楽しみです。
| «前へ | 次へ» |
アーカイブ
- 2025年12月(1)
- 2025年11月(12)
- 2025年10月(13)
- 2025年9月(11)
- 2025年8月(11)
- 2025年7月(11)
- 2025年6月(10)
- 2025年5月(8)
- 2025年4月(9)
- 2025年3月(9)
- 2025年2月(7)
- 2024年12月(18)
- 2024年11月(12)
- 2024年10月(12)
- 2024年9月(13)
- 2024年8月(11)
- 2024年7月(12)
- 2024年6月(8)
- 2024年5月(9)
- 2024年4月(8)
- 2024年3月(8)
- 2024年2月(11)
- 2024年1月(5)
- 2023年12月(9)
- 2023年11月(12)
- 2023年10月(11)
- 2023年9月(12)
- 2023年8月(11)
- 2023年7月(11)
- 2023年6月(8)
- 2023年5月(7)
- 2023年4月(8)
- 2023年3月(7)
- 2023年2月(9)
- 2023年1月(3)
- 2022年12月(23)
- 2022年11月(14)
- 2022年10月(13)
- 2022年9月(14)
- 2022年8月(14)
- 2022年7月(16)
- 2022年6月(10)
- 2022年5月(11)
- 2022年4月(12)
- 2022年3月(10)
- 2022年2月(9)
- 2021年12月(12)
- 2021年11月(12)
- 2021年10月(14)
- 2021年9月(12)
- 2021年8月(12)
- 2021年7月(12)
- 2021年6月(11)
- 2021年5月(12)
- 2021年4月(11)
- 2021年3月(13)
- 2021年2月(4)
- 2021年1月(14)
- 2020年12月(11)
- 2020年11月(12)
- 2020年10月(13)
- 2020年9月(12)
- 2020年8月(14)
- 2020年7月(12)
- 2020年6月(12)
- 2020年5月(13)
- 2020年4月(12)
- 2020年3月(13)
- 2020年2月(5)
- 2019年12月(10)
- 2019年11月(15)
- 2019年10月(11)
- 2019年9月(13)
- 2019年8月(13)
- 2019年7月(10)
- 2019年6月(8)
- 2019年5月(13)
- 2019年4月(7)
- 2019年3月(7)
- 2019年2月(5)
- 2019年1月(7)
- 2018年12月(15)
- 2018年11月(12)
- 2018年10月(15)
- 2018年9月(10)
- 2018年8月(7)
- 2018年7月(6)
- 2018年6月(10)
- 2018年5月(12)
- 2018年4月(11)
- 2018年3月(5)
- 2017年12月(11)
- 2017年11月(13)
- 2017年10月(12)
- 2017年9月(11)
- 2017年8月(12)
- 2017年7月(10)
- 2017年6月(10)
- 2017年5月(17)
- 2017年4月(10)
- 2017年3月(13)
- 2017年2月(4)
- 2016年12月(15)
- 2016年11月(12)
- 2016年10月(14)
- 2016年9月(12)
- 2016年8月(12)
- 2016年7月(15)
- 2016年6月(9)
- 2016年5月(9)
- 2016年4月(11)
- 2016年3月(10)
- 2016年2月(7)
- 2015年12月(5)
- 2015年11月(6)
- 2015年10月(4)
- 2015年9月(6)
- 2015年8月(2)
- 2015年7月(5)
- 2015年6月(6)
- 2015年5月(7)
- 2015年4月(4)
- 2015年3月(4)
- 2015年2月(10)
- 2015年1月(11)
- 2014年12月(10)
- 2014年11月(6)
- 2014年10月(9)
- 2014年9月(9)
- 2014年8月(5)
- 2014年7月(3)
- 2014年6月(3)
- 2014年5月(5)
- 2014年4月(6)
- 2014年3月(9)
- 2014年2月(5)
- 2013年12月(13)
- 2013年11月(14)
- 2013年10月(16)
- 2013年9月(15)
- 2013年8月(8)
- 2013年7月(9)
- 2013年6月(9)
- 2013年5月(9)
- 2013年4月(10)
- 2013年3月(9)
- 2013年2月(3)
- 2012年12月(7)
- 2012年11月(3)
- 2012年10月(10)
- 2012年9月(7)
- 2012年8月(9)
- 2012年7月(5)
- 2012年6月(8)
- 2012年5月(8)
- 2012年4月(8)
- 2012年3月(10)
- 2012年2月(8)
- 2011年12月(6)
- 2011年11月(6)
- 2011年10月(7)
- 2011年9月(9)
- 2011年8月(10)
- 2011年7月(5)
- 2011年6月(5)
- 2011年5月(9)
- 2011年4月(7)
- 2011年3月(8)
- 2011年2月(4)
ブログ最新記事
- パワーグリップの詩 (12/01 21:08)
- Marry Me Chicken (11/28 10:31)
- 愉快で最高な仲間たち (11/26 18:43)
- 男磨きはボディビルへ (11/25 16:43)
- fall season (11/22 22:18)
- 類まれな才能 (11/20 09:32)
- しんらい (11/19 23:02)
- あの坂田が!?!?泣いたアニメ (11/19 18:27)
- 埼玉旅行記 (11/16 18:05)
- 渋谷のサグラダ・ファミリア (11/15 20:40)
- 逆ナンなん? (11/13 16:34)
- バイト (11/12 10:31)
- モチーフで見る部員の部屋 (11/07 00:32)
- 自己開示 (10/31 13:42)
- ポスト考古学実習 (10/28 21:23)
- 白球に魅せられて (10/25 18:37)
- LoveType16 (10/25 11:46)
- 休みたい (10/25 07:09)
- No pain, no gain. (10/24 12:29)
- 銀杏 (10/18 07:50)





.jpg)