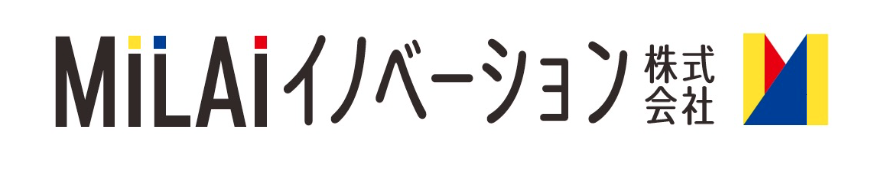ブログ
| <<前へ | 次へ>> |
卵かけご飯[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2022/09/20(火) 20:06
僕の推しはメジャーの大谷翔平選手で、最近もヤンキースのアーロン・ジャッジ選手と一騎討ちのMVP争いをしているので毎日応援していますが、推しを神棚に祀るほどの“推し活”はできていません。もっと頑張ろうと思います。
今回は僕の朝食について書こうと思います。3年前から、朝食には決まって米1合に卵3つを入れた卵かけご飯を食べています。朝起きてレンジでご飯をチンして、卵をカカカッと割って醤油を混ぜて食べるのがルーティーンです。こうなったのは3年前に部で朝から規定以上の栄養を補給しようという「朝ごはんチャレンジ」が始まったことがきっかけです。試行錯誤の末、卵かけご飯に落ち着きました。理由には、①タンパク質を摂れる…卵1つにはタンパク質が6g含まれていて、3つで20gほどのタンパク質が摂れる。(追加でプロテインも飲みます)②安い…1食で100円もかかっていないと思います。③準備が楽…早起きは苦手なので朝からフライパンで何かを焼いたりするのは大変。④あっさりしている…個人的に、肉などと違って卵なら朝でも食べやすい。⑤短時間でスルスルと食べられる。などがあります。
毎日3個卵を割り続けていると面白いことがあります。他より殻が硬い卵、細い形をした卵などほんの少しの違いも気づくようになりました。また、割ってみると黄身が二つある双子のこともあります。大体一年に一回くらいしか見ないので1000個に1個くらいの確率なのでしょうか。双子の卵だった時はさすがにその日良いことがありそうな気がします。卵かけご飯の味自体は特に好きではなく、部活を引退したら間違いなく食べなくなってしまうので12月末までにあと一回双子の卵に遭遇できたら良いなと思います。
4年間を振り返ると、練習やウエイト食事と色々なことを継続してきました。たかが朝食の卵かけご飯のような些細なことでも、継続したことで間違いなく自分の力になっています。ついに対抗戦シーズンが始まりましたが、グラウンドに1分でも長く立ち、これまで積み重ねてきたものを全てぶつけたいです。
次は、僕よりパスが上手でブロンコも速そうなようこちゃんにバトンを渡します。今年のS&Cセクションは学年別で分かれていてあまり関わりがないですが、いつもS&Cの仕事をしてくれていて感謝しています。
初バイトの話[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2022/09/18(日) 17:50
さて、大学1年の夏休みも半ばを過ぎ、僕は最近人生初バイトを始めました。某有名雑貨店で品出しやレジの仕事をしております。同年代の女性の方が多く、大変キラキラした職場です。入ってから2週間が経ち、見よう見まねで始めたレジ打ちは、今やお客さんが来れば「いらっしゃいませ。有料のレジ袋はご利用ですか?」とお尋ねし、現金のみならずクレジットや電子マネーなど様々なお支払い方法に素早く対応、とお手のものです。ただ僕のいるフロアは扱っている商品の種類が非常に多く、品出しという店頭で商品を補充する仕事の方はまだまだ先輩に頼りっきりです。
そんな品出し作業中にお客さんからは商品の在庫や詳細について尋ねられます。もちろん接客も仕事のうちです。先日、金封コーナーで作業していると、お客さんから「香典袋の、“御霊前”と書いてあるのと“御仏前”というのとはどう違うんでしたっけ?」と訊かれました。商品の大体の位置なら答えることができるようになりましたが、今回の質問は答えることができませんでした。仏教とかキリスト教とかお葬式の様式の違いで使い分けるのかな、などと適当なことが頭に浮かびましたが、それをそのまま答えるわけにも行きません。スマホは貴重品ロッカーにしまってあり調べることができないので、無線機で先輩に問い合わせていると、その話を聞いていた別のお客さんが「四十九日の法要以降は“御仏前”と書かれたものを使い、それより前なら“御霊前”を使うらしいですよ。」とその場で調べて代わりに答えてくれました。この歳でお葬式に出る機会はなかなか少ないので、香典袋にまつわる知識など持ち合わせるのは難しいですが、お客さんの質問に答えることができなかったことが悔しいです。東大生なら知っている人も多いのではないでしょうか。売り場を回っていると、見慣れないものや新たな発見が多くあり刺激に溢れています。この仕事を見つけることができてよかったと思っています。
ところで、今若い女性を中心に売れ筋なのが、いわゆる“推し活”アイテムです。推し活とは、自分のお気に入りの対象(推し)を応援する活動のことです。推し活をする人の中には、グッズで部屋を埋め尽くす人もいます。僕の働く店には、応援用うちわを始め、推しのグッズを飾るための“推しを祀る神棚”や、“推し専用ATM”ステッカーなどの商品があります。先日の上智戦は大変盛り上がりましたが、”東大ラグビー部推し”の人がもっと増えてくれるといいなと思っています。ちなみに”石割推し”も大歓迎です。
次は4年の頼れる先輩河内さんにバトンを渡します。最近僕はfwをやっているのでスクラムの練習などでお世話になっています。今の先輩の“推し”はなんですか?何かあったら教えてください。
TRUST[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2022/09/16(金) 16:25
早いもので引退まで4ヶ月を切り、最後の対抗戦が始まってしまった。入れ替え戦に出場し、歴史を塗り替えられるチャンスは残り1回となった。
振り返ってみると4年生になってから、それまでの3年間に感じたことのない不安を感じていたように思う。3年生の頃から学年ミーティングを重ね、チームづくりに関して全員で話しあっていた。全員で納得して決めたはずのことでも、本当にこれでいいのか、他の選択肢の方が強くなる可能性があるのではないか、とどこか不安に思うことが多かった。
2月頭に國枝組が始動し、昨年は行っていなかったBBCや練習中の間食など、新しく始めたことも多かった。しかし、それらが本当に強くなることに繋がっているのか、週5回の練習で本当に足りるのか、と思うこともあった。3年生までは練習内容や回数をチーム強化につながるかどうかの点から見たことはほとんどなかった。しかし、4年生になり、入れ替え戦出場という目標にチャレンジできる最後の年であるという現実に直面した結果、あらゆることに対して本当にこれでいいのかという漠然とした不安を感じることになったのだろう。
この不安が徐々に晴れてきたのは、やはり春シーズンに試合に勝利し始めた頃だと思う。そこまで単純なことではないと思うが、やはり勝つことができればこれまで積み重ねてきたものが間違っていなかったことが証明される気がする。そして、合宿中の山学との練習試合や慶應戦でのプレーを見て、不安は無くなった。これが対抗戦でできたら本当に入れ替え戦にいけると思った(素人目すぎるので、的外れで失礼であればごめんなさい)。
先週末、対抗戦初戦となる上智大学戦が駒場で行われ、対抗戦がついに開幕した。試合1週間前からふとした時に動悸がするようになっていた。これまで自分が試合メディカルをすることに対して緊張することはあったが、試合そのものに対してこれほど緊張したことはなかった。これが4年生ということか。
多くのOBさんの声かけにより観客は300人近くを予定し、駒場開催の試合で史上最大規模の人数となった。多くの人に見守られ始まった試合だったが、やはり勝負はそう簡単には行かず、前半は先制を許すなど苦しい展開となった。しかし、私は絶対に勝つと思っていた。4年間ラグビーをしているところを近くで見てきたことから生まれた感情だろう。
多くのサポーターからの期待に応え、無事勝利してくれたわけだが、これは私たちの目標の第1歩にすぎない。私は入れ替え戦に出場できると信じている。残り3ヶ月と少し、悔いのないように自分にできることを精一杯して、勝利に少しでも繋がってくれれば。選手の皆さん、素敵な景色が見たいです。頭の中のことを書いてみたら散漫な文章になってしまいました。
次は1年生のまことにバトンを渡します。彼は新歓の際に担当になった新入生で唯一入部してくれた子なので、元気に部活を続けてくれていることがとても嬉しいです。先日の部内マッチでもFWながら走行距離が一番長かったりと才能を見せているようでこれからがとても楽しみです。
earth meal feat. asmi[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2022/09/14(水) 19:00
いろんな話を。少し長くなるかもしれない。これが最後のリレー日記になるかもしれないから。明日隕石が落ちてくる可能性だってあるんだし。
中学校の読書感想文の課題で選んだ本を最近読み返した。
”八年後に小惑星が衝突し、地球は滅亡する。そう予告されてから五年が過ぎた頃。当初は絶望からパニックに陥った世界も、いまや平穏な小康状態にある。仙台北部の団地「ヒルズタウン」の住民たちも同様だった。”
集英社文庫の裏表紙に書いてある紹介文が内容を端的に表している。こんな設定の中、さまざまな事情を持った住人たちが毎日を送る様子を描いた短編小説集だ。夏休みの課題を1枚にまとめたA3のプリントの右下に読書感想文におすすめの本が3冊紹介されていた。早く課題を終わらせたかったし、ちょうどその時兄が読んでいた小説の作家ということもあって選んだ。「いい小説だな」というなんとも思ってないものに対して抱く感想のみ起こり、指定の枚数分の文章を捻り出したのち、僕の中でこの本は役目を終え本棚の奥の方にしまわれた。しかし、なんのきっかけか、小説の中に散りばめられた言葉が8年越しに発芽している。
「生きられる限り、みっともなくてもいいから生き続けるのが、我が家の方針だ」
「死にもの狂いで生きるのは権利じゃない義務だ」
スマートに生きることに価値を感じ、失敗すること、ダサいことは避けようとする自分に気づく。どうして生きているのか。小学校の道徳の授業で通過しそうなこの問いは、辛くなったときふと考えることがある。そんなときに思い出せたら、少しは力になるだろうか。小説の中の登場人物やセリフ、生き方はいつ自分の中で大事なものになるかわからない。
急にやってくるのは隕石だけじゃない。時代の移り変わりも気づかないところで起こっていたりする。
最近コテンラジオというコンテンツを視聴するようになった。YouTubeやPodcastなどで配信されている。
”歴史を愛し、歴史を知りすぎてしまった歴史GEEK2人と圧倒的歴史弱者がお届けする歴史インターネットラジオです。 歴史というレンズを通して「人間とは何か」「私たち現代人の抱える悩み」「世の中の流れ」を痛快に読み解いていく!? 笑いあり、涙ありの新感覚・歴史キュレーションプログラム!”
と紹介文に書いてある通り、歴史に関する出来事を何十、何百もの文献を参考にしつつ、面白く伝えようとしてくれている点に惹かれた。参考文献の量が多いため、織田信長がテーマの際に、奈良時代の律令制から始まったこともある。一方でたった1人の人生をひたすら何時間も話していることもある。学校の先生が、教科書の話をしているときは全然授業が面白くないのに、ちょっと脱線するとめちゃくちゃ面白くなるあのおもしろ話が体験できるコンテンツだと思う。
日露戦争の回があった。例に漏れず、そこに至る流れを扱うため最初は幕末から始まった。舞台は日本に限らず、ヨーロッパ、東アジアなど、各地域で何が行われていたのか、丁寧に説明する。アジア諸国が西欧列強の影響を受け始めた時代。長い間平穏だった東アジア諸国は、どの国も同じような選択に迫られる。腐敗した政治体制を正して伝統を守るか、新しい政治体制を作るか。結果的には西洋式の新しい政治体制を作った(コテンラジオでは新しいOSをインストールしたと表現していた)国が政治経済で他の国をリードすることになるが、歴史を見るときにやってはいけないことは伝統的な政治体制を正そうとした人たちを、「情勢が見えていない」とか「無能だった」とか安易な言葉で片付けて思考を停止することだ。コテンラジオでは「ファクト認識は難しいんだよ」とよく話題になるが、僕たちが同じ立場だったらどのような選択を取るだろうか。今の状況で同じような状況はないか考えなければいけない。
僕は「この部活は先輩が後輩に命令して仕事をさせるんじゃなくて、先輩が後輩より仕事をするんだ」という言葉に惹かれてラグビー部に入ったのかもしれない。もう誰が言っていたのか、実際のところどうだったのか今になってはわからないが、少なくともその時はそう見えた。部室に溜まったゴミを片付ける。ケビンを掃除する。そういう小さな仕事しか見えなかったが、率先して取り組む先輩に憧れた。時間が経ってみると、部室やケビンは汚くないし、支援課から借りたものが期限内に返されていない、ゴミが片付けられない、DLが使う木箱を野ざらしにして腐らせる、期限後の提出物の催促が延々とされている。良いチームでありたいと思っても足りない点があって、自分の力不足を常に感じる。毎日提出を促すラインを送るうちに疑問がわく。どうして毎日急かされているのに、今日も提出してくれないのだろう。どうしてに規律違反を訴えるメッセージのことは誰も気にしないのだろう。そんな疑問を持つときに上のラジオを聴いた。一つの答えを見た気がする。時代が変わったのだ、自分が価値あると思っていたものがみんなにとって価値があるとは限らない。西洋列強に対抗するために列強のやり方を真似たように、強いチームに勝つことを目標にするには、新しい価値観が必要なのだと思う。自分が正しいと思っていたものが、誰かにとってはそうでもないという事実は辛いものだ。
大奥という漫画で勝海舟が言っていた。「惚れたお方に頼まれちまったんだから最後まで面倒を見る・・・それだけのことですよ。」僕も一度惚れたものは最後まで自分の向き合い方をするべきだ。みっともなかったとしても。
小学生のとき「鬼瓦」を作った。僕の地元、岡崎市ではおかざっき子展という岡崎市中の小中学生の美術作品を集めた展覧会が1年に一回行われる。テーマは各学校の先生が学年ごとに指定する。どういう経緯か、その年は鬼瓦を作ることになった。専用の粘土でA4サイズの鬼瓦のようなものを作る。本物の鬼瓦をイケメンと感じる人は少ないだろうが、小学生の作った鬼瓦は、それはそれはみっともない顔をしていた。
怒られるかもしれないが、ラグビーをしているときのみんなの顔は綺麗とは言い難い。どちらかというとみっともない。でもカッコ悪くはない。小学生の作る鬼瓦のようにどんなにみっともない顔になっても、力を出し続けられる限りは、死に物狂いで力を出し続けてほしいと思う。
僕もやれる限り頑張ります。
次は、はるぴーことかわはるにバトンを渡します。ピッタリはまるあだ名がない自分にとっては、適切なあだ名をもらっていることが羨ましいです。僕の地元の岡崎市で活躍するユーチューバーが好きみたいなのでいつか一緒に岡崎観光したいですね。いや、やっぱり実家でダラダラしている方が幸せなので観光はまたの機会にしましょう。ごめんなさい。
いけがみあきら[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2022/09/12(月) 09:27
僕のことが大好きで仕方ない2年の池上暁雄くんからバトンを受け取りました、3年の鈴木陸人です。彼はラグビーのみならず学業においても非常に優秀で、後輩ながら僕の進級の助けとなってくたことがあります。僕が工学部の3年生として日々勉学に励めているのは彼のおかげなのです。愛しています。
池上暁雄と聞いて真っ先に連想するのはやはり池上彰さんでしょう。名前がとっても似ていますね。
先日自宅でテレビをつけたら、「池上彰のニュースそうだったのか!!」という番組が放送されていました。池上彰さんが話題のニュースについて基礎から丁寧に解説する番組です。ご存じの方も多いかもしれません。
僕が見た回では、SDGs、ロシア・ウクライナにまつわる話題、最近の円安などについて取り扱っていました。環境問題については最低限の知識や理解はあるし、ロシア関連についても毎日のようにニュースで見ていたので一応話に付いていけたのですが、円安の話題になった途端よくわからなくなってしまいました。お恥ずかしい話ではありますが、僕は金融・経済に関してはおそらく一般常識レベルの理解すら持ち合わせていないのです。堪らず父に解説を求めたのですが、僕の理解力の低さゆえに(皮肉でも何でもないです)分かったような分からないようなという感じで終わってしまいました。
もっとニュース見たり新聞読んだりして、社会について知らなければいけないと少し焦りを感じました。こんな僕でもおそらく数年後には社会人になるのです。東大卒のくせに社会のこと何も知らんのだなとか思われたらたまったもんじゃありません。これからは、ゲームばかりしてないでもう少し社会に目を向けて生きていこうと思います。
次は、S&Cの仕事などで大いに活躍して下さっている4年のあきらさんにバトンを回します。あきらさんがやって下さっている膨大な量の仕事を来年僕らの代がプレイヤーと両立しながらこなさなければいけないと考えると夜も眠れません。まあS&Cは僕の担当ではないですが。それはさておき、いつも本当にありがとうございます。これからもウエイト頑張ります。今度飯連れてってください。
| <<前へ | 次へ>> |
2025年11月
| <<前月 | 翌月>> |
| |
アーカイブ
- 2025年11月(1)
- 2025年10月(13)
- 2025年9月(11)
- 2025年8月(11)
- 2025年7月(11)
- 2025年6月(10)
- 2025年5月(8)
- 2025年4月(9)
- 2025年3月(9)
- 2025年2月(15)
- 2025年1月(2)
- 2024年12月(18)
- 2024年11月(12)
- 2024年10月(12)
- 2024年9月(13)
- 2024年8月(11)
- 2024年7月(12)
- 2024年6月(8)
- 2024年5月(9)
- 2024年4月(8)
- 2024年3月(8)
- 2024年2月(19)
- 2024年1月(7)
- 2023年12月(9)
- 2023年11月(12)
- 2023年10月(11)
- 2023年9月(12)
- 2023年8月(11)
- 2023年7月(11)
- 2023年6月(8)
- 2023年5月(7)
- 2023年4月(8)
- 2023年3月(7)
- 2023年2月(15)
- 2023年1月(7)
- 2022年12月(23)
- 2022年11月(14)
- 2022年10月(13)
- 2022年9月(14)
- 2022年8月(14)
- 2022年7月(16)
- 2022年6月(10)
- 2022年5月(11)
- 2022年4月(12)
- 2022年3月(10)
- 2022年2月(15)
- 2022年1月(4)
- 2021年12月(12)
- 2021年11月(12)
- 2021年10月(14)
- 2021年9月(12)
- 2021年8月(12)
- 2021年7月(12)
- 2021年6月(11)
- 2021年5月(12)
- 2021年4月(11)
- 2021年3月(13)
- 2021年2月(10)
- 2021年1月(21)
- 2020年12月(11)
- 2020年11月(12)
- 2020年10月(13)
- 2020年9月(12)
- 2020年8月(14)
- 2020年7月(12)
- 2020年6月(12)
- 2020年5月(13)
- 2020年4月(12)
- 2020年3月(13)
- 2020年2月(12)
- 2020年1月(4)
- 2019年12月(10)
- 2019年11月(15)
- 2019年10月(11)
- 2019年9月(13)
- 2019年8月(13)
- 2019年7月(10)
- 2019年6月(8)
- 2019年5月(13)
- 2019年4月(7)
- 2019年3月(7)
- 2019年2月(5)
- 2019年1月(7)
- 2018年12月(15)
- 2018年11月(12)
- 2018年10月(15)
- 2018年9月(10)
- 2018年8月(7)
- 2018年7月(6)
- 2018年6月(10)
- 2018年5月(12)
- 2018年4月(11)
- 2018年3月(5)
- 2017年12月(11)
- 2017年11月(13)
- 2017年10月(12)
- 2017年9月(11)
- 2017年8月(12)
- 2017年7月(10)
- 2017年6月(10)
- 2017年5月(17)
- 2017年4月(10)
- 2017年3月(13)
- 2017年2月(4)
- 2016年12月(15)
- 2016年11月(12)
- 2016年10月(14)
- 2016年9月(12)
- 2016年8月(12)
- 2016年7月(15)
- 2016年6月(9)
- 2016年5月(9)
- 2016年4月(11)
- 2016年3月(10)
- 2016年2月(7)
- 2015年12月(8)
- 2015年11月(11)
- 2015年10月(10)
- 2015年9月(10)
- 2015年8月(5)
- 2015年7月(7)
- 2015年6月(11)
- 2015年5月(13)
- 2015年4月(8)
- 2015年3月(9)
- 2015年2月(12)
- 2015年1月(11)
- 2014年12月(12)
- 2014年11月(10)
- 2014年10月(12)
- 2014年9月(12)
- 2014年8月(12)
- 2014年7月(6)
- 2014年6月(5)
- 2014年5月(13)
- 2014年4月(11)
- 2014年3月(14)
- 2014年2月(7)
- 2013年12月(23)
- 2013年11月(29)
- 2013年10月(32)
- 2013年9月(30)
- 2013年8月(14)
- 2013年7月(15)
- 2013年6月(23)
- 2013年5月(33)
- 2013年4月(27)
- 2013年3月(20)
- 2013年2月(10)
- 2013年1月(1)
- 2012年12月(13)
- 2012年11月(11)
- 2012年10月(24)
- 2012年9月(13)
- 2012年8月(9)
- 2012年7月(5)
- 2012年6月(8)
- 2012年5月(11)
- 2012年4月(9)
- 2012年3月(10)
- 2012年2月(8)
- 2011年12月(6)
- 2011年11月(6)
- 2011年10月(7)
- 2011年9月(9)
- 2011年8月(10)
- 2011年7月(5)
- 2011年6月(5)
- 2011年5月(9)
- 2011年4月(7)
- 2011年3月(8)
- 2011年2月(4)
ブログ最新記事
- モチーフで見る部員の部屋 (11/07 00:32)
- 自己開示 (10/31 13:42)
- ポスト考古学実習 (10/28 21:23)
- 白球に魅せられて (10/25 18:37)
- LoveType16 (10/25 11:46)
- 休みたい (10/25 07:09)
- No pain, no gain. (10/24 12:29)
- 銀杏 (10/18 07:50)
- ラグビーマン決戦・徳島頂上バトル (10/17 19:33)
- 名古屋に行きました。 (10/17 00:13)
- 勇気のいらない親切 (10/13 16:15)
- 懐かしのDAYS (10/10 16:14)
- アレルギー (10/04 23:56)
- 炎 (10/02 23:50)
- タックル怖くね? (09/29 22:08)
- surprise! mf (09/26 22:52)
- 気まずいよ展 (09/26 19:48)
- ライブハウスで会おうぜ (09/23 17:15)
- Work with ChatGPT? Talk with ChatGPT. (09/20 17:58)
- 素人はSNSするな、僧侶コスプレ、オープンマリッジ (09/19 00:04)





.jpg)