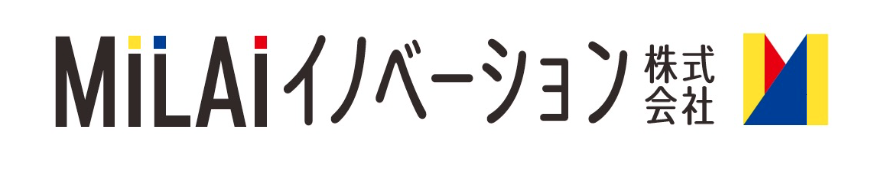ブログ 伊藤 佑樹さんが書いた記事
ただいま合宿中。[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2025/08/17(日) 15:51
3年同期で前期課程のころは同じ理一ドイツ語だった佐藤琉海君からバトンをもらいました,伊藤佑樹です。化学科が忙しいといわれていますが,実は単位数で見るとシステム創成学科と比べ9.5単位も少ないので,忙しいという指摘は当たらないと思います。それはさておき彼からはエネルギー分野に取り組みたい,そのためにシステム創成学科に行くのだと強い動機を聞きました。商社に行きたがっていた高校のクラスメイトからも色々聞きましたが,やはりエネルギー分野などは人文学や社会科学を含めて学際的なシステム創成学科で学ぶことが見方としては非常に重要なのだろうと思います。私にとっては化学1つ学ぶだけでも大変なのにそこから「総合知のアプローチ」などやっていくのは私にはなかなか負えません。システムの創成は彼や中村君,定浪君(予定)に任せることにして,私は分子を適当にいじっておくこととします。理一ドイツ語といえば葦扱いされていた目黒君も理一ドイツ語です。今度理一ドイツ語会でもしましょう。
さて,かなり重い夏バテに苦しめられ,麵ものどを通らないような状況であるため,あまり長く書くようなことはできません。残念ながら読書は相変わらず進んでおらず,ほかにそれほど書くようなネタがあるわけでもないです。とりあえずのテーマとして合宿について諸々ちょっとした思い出を語りたいと思います。
現在ラグビー部では合宿を続けて行っており,8月6日から8月12日に山中湖で合宿を行った後,昨日8月16日から菅平で合宿を行っています。
合宿でなんだかんだ一番重要なのは天候ではないかと思っています。なんだかんだ標高の高いところに行くというのもあって,合宿での天気が通して安定していたことはあまりありません。やはり一番心配なのは雷です。今年の山中湖合宿では何とか期間中落雷はありませんでしたが,これまでの合宿では結構ひやひやするようなこともありました。特に普段いる駒場ラグビー場と違ってすぐに退避できるわけでもないので,早めの判断が重要であるところですが,どうしてもギリギリのところでやりすぎてしまうことが多くありました。1年生のころ気象予報士試験に落ちた私ですが,今年はこの判断について原井君を主としつつ私も担当しています。駒場では早めの認識がしっかり効いたので,これを合宿中も行いたいです。
雷でなくとも,雨が降るとなかなかつらいものがあります。山中湖の合宿中もなかなか強かったです。それほど長くは続かないですが,天然芝も相まってスタッフにとってもしんどいです。幸い菅平に来てからの2日間は晴れており,山々に囲まれた中の日差しがあり,心地よい風が吹いています。
菅平での私の楽しみは散歩です。昨年2年生としてはちょうど進学選択の時期で,上に書いてある結局進んだ理学部化学科にしようか,全然違う分野に身を置こうかとほぼ毎日,グラウンドからホテルの帰り道や,あるいは全然違う別荘地を一人歩きながら悩んだものです。レタス畑があり,木々がある中で,若干虫は怖いですが,いろいろめぐり,上り下りしたものです。山中湖も東京と比べれば涼しいですが,菅平は全く別の次元で,何時間でも歩き回れるものです。今年もさっそくきた初日から40分ほど歩き回りました。見知らぬグラウンドの番号を確認しながらホテルへと戻る道にはつねに緑があります。昨年は菅平高原のある上田市と隣接した須坂市との市境にも,長野市との市境にも歩いていきました(昨年1回部車に同乗したときにも誤って長野市のほうに下っていきそうになったことがありました)。今年はぜひ群馬県との県境まで歩きたいところですが,さすがにそこまでの時間はなさそうです。
……
すみません。実はまだ今年は菅平に私は行っておらず,上に書いたことはでっちあげです。私が菅平につくのはもう何日か後です。今は某所に籠っています。天気と散歩のつまらない話でした。菅平に行ったときには散歩できたらと思います。
次は2年の三上君(昨日誕生日だったみたいです。普段あまり人の誕生日を祝うことはないですがおめでとうございます)が書きます。個人的には彼とは昨年一緒の班で,山中湖でSUPを昨年行ったのを思い出します。広い山中湖の上に三上君が立った姿は,グラウンドでの勇姿にも劣らず神々しいものさえありました(ただ彼はSUPに苦戦していました)。そんな三上君は無人島で自給自足サバイバルができるようになる学科に進みたいとしていました) 。残念ながら私の知る限り直接そのような学科はないですが,そのためのヒントを得るためには,結局のところ,毒を見極めることなどで分子的な視点が一番重要ではないかと思いますし(ちょっと例が下手すぎましたが),何より三上君自身化学が得意であると,先日素晴らしいリレー日記を執筆された猿渡さん(残念ながら結構重大な誤字がありました)をはじめとする化学系の学科の先輩の前で常々豪語していたと記憶しています。私は理学部化学科に在籍しているのですが,三上君こそまさにこの分子的な視点の探究を担っていく人財だと思います。なので三上君,化学科で待っています(進学選択直前できっと昨年の私みたいに悩んでいる時期にこんなことを書かれると彼も大変だと思います。大変申し訳ございませんでした)。
さて,かなり重い夏バテに苦しめられ,麵ものどを通らないような状況であるため,あまり長く書くようなことはできません。残念ながら読書は相変わらず進んでおらず,ほかにそれほど書くようなネタがあるわけでもないです。とりあえずのテーマとして合宿について諸々ちょっとした思い出を語りたいと思います。
現在ラグビー部では合宿を続けて行っており,8月6日から8月12日に山中湖で合宿を行った後,昨日8月16日から菅平で合宿を行っています。
合宿でなんだかんだ一番重要なのは天候ではないかと思っています。なんだかんだ標高の高いところに行くというのもあって,合宿での天気が通して安定していたことはあまりありません。やはり一番心配なのは雷です。今年の山中湖合宿では何とか期間中落雷はありませんでしたが,これまでの合宿では結構ひやひやするようなこともありました。特に普段いる駒場ラグビー場と違ってすぐに退避できるわけでもないので,早めの判断が重要であるところですが,どうしてもギリギリのところでやりすぎてしまうことが多くありました。1年生のころ気象予報士試験に落ちた私ですが,今年はこの判断について原井君を主としつつ私も担当しています。駒場では早めの認識がしっかり効いたので,これを合宿中も行いたいです。
雷でなくとも,雨が降るとなかなかつらいものがあります。山中湖の合宿中もなかなか強かったです。それほど長くは続かないですが,天然芝も相まってスタッフにとってもしんどいです。幸い菅平に来てからの2日間は晴れており,山々に囲まれた中の日差しがあり,心地よい風が吹いています。
菅平での私の楽しみは散歩です。昨年2年生としてはちょうど進学選択の時期で,上に書いてある結局進んだ理学部化学科にしようか,全然違う分野に身を置こうかとほぼ毎日,グラウンドからホテルの帰り道や,あるいは全然違う別荘地を一人歩きながら悩んだものです。レタス畑があり,木々がある中で,若干虫は怖いですが,いろいろめぐり,上り下りしたものです。山中湖も東京と比べれば涼しいですが,菅平は全く別の次元で,何時間でも歩き回れるものです。今年もさっそくきた初日から40分ほど歩き回りました。見知らぬグラウンドの番号を確認しながらホテルへと戻る道にはつねに緑があります。昨年は菅平高原のある上田市と隣接した須坂市との市境にも,長野市との市境にも歩いていきました(昨年1回部車に同乗したときにも誤って長野市のほうに下っていきそうになったことがありました)。今年はぜひ群馬県との県境まで歩きたいところですが,さすがにそこまでの時間はなさそうです。
……
すみません。実はまだ今年は菅平に私は行っておらず,上に書いたことはでっちあげです。私が菅平につくのはもう何日か後です。今は某所に籠っています。天気と散歩のつまらない話でした。菅平に行ったときには散歩できたらと思います。
次は2年の三上君(昨日誕生日だったみたいです。普段あまり人の誕生日を祝うことはないですがおめでとうございます)が書きます。個人的には彼とは昨年一緒の班で,山中湖でSUPを昨年行ったのを思い出します。広い山中湖の上に三上君が立った姿は,グラウンドでの勇姿にも劣らず神々しいものさえありました(ただ彼はSUPに苦戦していました)。そんな三上君は無人島で自給自足サバイバルができるようになる学科に進みたいとしていました) 。残念ながら私の知る限り直接そのような学科はないですが,そのためのヒントを得るためには,結局のところ,毒を見極めることなどで分子的な視点が一番重要ではないかと思いますし(ちょっと例が下手すぎましたが),何より三上君自身化学が得意であると,先日素晴らしいリレー日記を執筆された猿渡さん(残念ながら結構重大な誤字がありました)をはじめとする化学系の学科の先輩の前で常々豪語していたと記憶しています。私は理学部化学科に在籍しているのですが,三上君こそまさにこの分子的な視点の探究を担っていく人財だと思います。なので三上君,化学科で待っています(進学選択直前できっと昨年の私みたいに悩んでいる時期にこんなことを書かれると彼も大変だと思います。大変申し訳ございませんでした)。
格子定数[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2025/04/23(水) 18:50
2年の野村君からバトンを受け取りました,3年の伊藤佑樹です。
野村君の書いている通り,ホームページ関係などSEセクションとしてやっています。
中学生のころ学校のホームページを実質更新していた身としてはこのSEセクションの仕事は天職みたいなものですが,
それゆえ変な自信から空回りしてしまうところも多くあります。
ぜひ野村君にもSEセクションに興味があるならまじめな彼に一緒にやってほしいところです。
さて,申し訳ございませんが,『トム・ブラウンの学校生活』についてはいまだ読めていません。プロジェクト・グーテンベルクにあるのでそこで読もうとは思っていましたが,昔の英語についていけずまだ読み進めることができていません。またこうした過去の英語について読む機会があればと思います。
そのようなことなので,今回は野村君から提示された疑問に対して答えたいと思います。多分以下の回答というのは必ずしも良いものではなく,賛否両論あるのは間違えなくいえると思います。なかなか言葉にするのが難しいところもあり,いつも以上につたない文章になっていますが,読んでいただければ嬉しいです。
ところで,前回の野村君のリレー日記は読まれましたでしょうか。こちらですが,最後に私の同期スタッフの原井君にバトンを渡しているのですが,ここでも「いとしん」と「格」という2語が使われています。これは私には偶然とは思えないです。きっと伊藤慎君は野村君にとって標準水素電極みたいな存在なのでしょう。ふたりの間で怪しい取引がないか今後注視したいと思います。
「伊藤として格上」ということに関して,伊藤慎君と話した中では彼と私伊藤佑樹との間での格の違いは特にないだろうという結論に至りました。もしかしたらお互いに自分のほうが上だと思っているのかもしれませんが。伊藤というのは現在生きている人だけで100万人ぐらいいますが,その間に格というのを考えて100万人に順位をつけるというのは私は思想として危険なようにも感じますし,実際にできるものでもないと思います。名前の50音順だったら私のほうが後になる,といった具合でしか現実に考えることはできないでしょう。さかのぼっていったときに本当の発祥という意味での本家の伊藤さんだったら格上だとか考えることもできるかもしれませんが,とくに私たち2人はそういったものではなさそうです。
ただ,このような書き方をすると問題があるかもしれませんが,後輩の野村君から,後輩の伊藤慎君との格を比べられたということに関しては,私自身として問題意識を持たなくてはならないと感じています。決して先輩としての威厳がどうということではないですが,実際比べられてしまうのは,私自身部で格下に見えているところがあるのだろうと思います。いろいろ部での仕事に関してうまくできないことも多く,私のせいで停滞してしまったことも多くあります。
では,自身として格上であるべきなのか,と問われるとそれは違うように思います。多分格上だと思って物事を進めると私の場合どこかでそれが転落してしまう点があるのだろうと思っています。高校生の頃も部活でそのようなことがあり,今のラグビー部での立場ももしかしたらそのようなところがあるかもしれません。同期スタッフの中で最初に当番制の少し大変な仕事をしたのも私でしたから,なにかそのように思ってしまっていたところがあるのかもしれません。1年生のころそれなりに大きな失敗をし,そこからいまだ立ち直っていないようにも思います。
格というのは考えるべきではないと思うところですが,ある程度気にしてしまうところがあるのが難しいところです。
具体性のない文章になりましたが,格という枠組みから私は抜け出さなければならないと思っていますし,現実難しいところはありますが,そのように行動したいと思います。
次は4年副将・領木彦人さんにバトンを渡します。最近私も坊主に近いような髪型にしましたが,長すぎると彦人さんから言われました。先輩を見習って次はもっと短くしたいと思います。
野村君の書いている通り,ホームページ関係などSEセクションとしてやっています。
中学生のころ学校のホームページを実質更新していた身としてはこのSEセクションの仕事は天職みたいなものですが,
それゆえ変な自信から空回りしてしまうところも多くあります。
ぜひ野村君にもSEセクションに興味があるならまじめな彼に一緒にやってほしいところです。
さて,申し訳ございませんが,『トム・ブラウンの学校生活』についてはいまだ読めていません。プロジェクト・グーテンベルクにあるのでそこで読もうとは思っていましたが,昔の英語についていけずまだ読み進めることができていません。またこうした過去の英語について読む機会があればと思います。
そのようなことなので,今回は野村君から提示された疑問に対して答えたいと思います。多分以下の回答というのは必ずしも良いものではなく,賛否両論あるのは間違えなくいえると思います。なかなか言葉にするのが難しいところもあり,いつも以上につたない文章になっていますが,読んでいただければ嬉しいです。
ところで,前回の野村君のリレー日記は読まれましたでしょうか。こちらですが,最後に私の同期スタッフの原井君にバトンを渡しているのですが,ここでも「いとしん」と「格」という2語が使われています。これは私には偶然とは思えないです。きっと伊藤慎君は野村君にとって標準水素電極みたいな存在なのでしょう。ふたりの間で怪しい取引がないか今後注視したいと思います。
「伊藤として格上」ということに関して,伊藤慎君と話した中では彼と私伊藤佑樹との間での格の違いは特にないだろうという結論に至りました。もしかしたらお互いに自分のほうが上だと思っているのかもしれませんが。伊藤というのは現在生きている人だけで100万人ぐらいいますが,その間に格というのを考えて100万人に順位をつけるというのは私は思想として危険なようにも感じますし,実際にできるものでもないと思います。名前の50音順だったら私のほうが後になる,といった具合でしか現実に考えることはできないでしょう。さかのぼっていったときに本当の発祥という意味での本家の伊藤さんだったら格上だとか考えることもできるかもしれませんが,とくに私たち2人はそういったものではなさそうです。
ただ,このような書き方をすると問題があるかもしれませんが,後輩の野村君から,後輩の伊藤慎君との格を比べられたということに関しては,私自身として問題意識を持たなくてはならないと感じています。決して先輩としての威厳がどうということではないですが,実際比べられてしまうのは,私自身部で格下に見えているところがあるのだろうと思います。いろいろ部での仕事に関してうまくできないことも多く,私のせいで停滞してしまったことも多くあります。
では,自身として格上であるべきなのか,と問われるとそれは違うように思います。多分格上だと思って物事を進めると私の場合どこかでそれが転落してしまう点があるのだろうと思っています。高校生の頃も部活でそのようなことがあり,今のラグビー部での立場ももしかしたらそのようなところがあるかもしれません。同期スタッフの中で最初に当番制の少し大変な仕事をしたのも私でしたから,なにかそのように思ってしまっていたところがあるのかもしれません。1年生のころそれなりに大きな失敗をし,そこからいまだ立ち直っていないようにも思います。
格というのは考えるべきではないと思うところですが,ある程度気にしてしまうところがあるのが難しいところです。
具体性のない文章になりましたが,格という枠組みから私は抜け出さなければならないと思っていますし,現実難しいところはありますが,そのように行動したいと思います。
次は4年副将・領木彦人さんにバトンを渡します。最近私も坊主に近いような髪型にしましたが,長すぎると彦人さんから言われました。先輩を見習って次はもっと短くしたいと思います。
予告と異なりすみません[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2024/08/03(土) 18:45
4年の木村デイビス泰志さんからバトンを受け取りました、2年の伊藤佑樹ですです。昨年の合宿ではできることがあまりなく、ずっと部屋にいましたので、かなりいろいろとその中でコミュニケーションを取ることがあり、デイビスさんのことをよく知る機会となりました。今年の夏合宿はこうした状況にはならないとよいですが、貴重な経験ではありました。
さて、前回のリレー日記では『トム・ブラウンの学校生活』について書くと予告していました。その時は夏休み中にゆっくり読もうかなと思っていましたが、思いの外バトンが早く回ってきてしまい、残念ながらまだ最初の部分しか読むことができていません。夏休みであれば、もちろん部活は合宿や対抗戦など忙しくはなりますが、それでも授業がない分時間をかけて読むことができると思っていたところでした。少し古い英語の調子で書かれていることもあり(日本語訳もありますが)、読むのにはもう少し時間がかかりそうです。また別の機会があれば『トム・ブラウンの学校生活』について書くことにして、今回は外国の作品というところでちょっと外国語の学習について感じることについて書こうと思います。
この間までの学期では、これまであまり学ぶことがなかった外国語について、いくつかの言語の授業を受けました。これらの科目では、文法を中心に学ぶことになりました。私自身として、あまり文法について学ぶ機会がなかったもので、しっかりと学んだのは今回が初めてだと思います。英語については前回書いた通り少しアメリカにいたのである程度はできるところがあり、あまり文法を中心に学ぶような姿勢ではなかったです。また大学に入って1年次より学んできたドイツ語の方も、どちらかというと会話のようなところを中心として学んできたので、文法を意識することはもちろんありましたが、文法を中心とするようなことはありませんでした。高校生の頃を思い出すと、英語の授業で文法事項というのは一通り扱っていましたが、それを知ることについてはあまり意味を感じていませんでした。文法というのは、それ自体が言語を成り立たせているものというよりは、その言語が先にあって、そこから帰納的に見つけられるものとして英語には臨んできて、ある程度文に触れることによって納得のいく考えを得る必要があるのではないかと思っていました。ところが、特にラテン語のような場合にこの方法は難しく、いろいろ読んでいくよりもその文法に即して見ていくということのほうが基本になるのだろうと思います。外国語学習の目的としては、コミュニケーションをとりたいということや、文献を読めるようになりたいというところはあると思いますが、その文法を知るということだけでもいろいろな言語の違いというのが見えて面白かったところです。
そうなった時にこれまで何でそういったことを学んでこなかったのか、ということになりますし、色々私自身の学習態度として反省するところがあります。特に外国語についてはどうしても実用性というところを求めてしまうところが大きく、私にとって少なくとも英語に関しては文法を学ぶことにはメリットを感じなかったところでした。今後も外国語については色々と学んでみたいと思いますが、まず夏休みは一旦『トム・ブラウンの学校生活』を読みたいと思います。
次は4年辻翔太さんにバトンを渡します。辻さんはタッチジャッジをするのがお好きなようで、機会があるたびに立候補しています。私も以前にタッチジャッジをする機会がありましたが、その時は動きがあまりにもひどく反省すべき点が多かったです。もっと他に聞くべき人がいるようにも思いますが、辻さんにもタッチジャッジについて聞きたいと思います。
さて、前回のリレー日記では『トム・ブラウンの学校生活』について書くと予告していました。その時は夏休み中にゆっくり読もうかなと思っていましたが、思いの外バトンが早く回ってきてしまい、残念ながらまだ最初の部分しか読むことができていません。夏休みであれば、もちろん部活は合宿や対抗戦など忙しくはなりますが、それでも授業がない分時間をかけて読むことができると思っていたところでした。少し古い英語の調子で書かれていることもあり(日本語訳もありますが)、読むのにはもう少し時間がかかりそうです。また別の機会があれば『トム・ブラウンの学校生活』について書くことにして、今回は外国の作品というところでちょっと外国語の学習について感じることについて書こうと思います。
この間までの学期では、これまであまり学ぶことがなかった外国語について、いくつかの言語の授業を受けました。これらの科目では、文法を中心に学ぶことになりました。私自身として、あまり文法について学ぶ機会がなかったもので、しっかりと学んだのは今回が初めてだと思います。英語については前回書いた通り少しアメリカにいたのである程度はできるところがあり、あまり文法を中心に学ぶような姿勢ではなかったです。また大学に入って1年次より学んできたドイツ語の方も、どちらかというと会話のようなところを中心として学んできたので、文法を意識することはもちろんありましたが、文法を中心とするようなことはありませんでした。高校生の頃を思い出すと、英語の授業で文法事項というのは一通り扱っていましたが、それを知ることについてはあまり意味を感じていませんでした。文法というのは、それ自体が言語を成り立たせているものというよりは、その言語が先にあって、そこから帰納的に見つけられるものとして英語には臨んできて、ある程度文に触れることによって納得のいく考えを得る必要があるのではないかと思っていました。ところが、特にラテン語のような場合にこの方法は難しく、いろいろ読んでいくよりもその文法に即して見ていくということのほうが基本になるのだろうと思います。外国語学習の目的としては、コミュニケーションをとりたいということや、文献を読めるようになりたいというところはあると思いますが、その文法を知るということだけでもいろいろな言語の違いというのが見えて面白かったところです。
そうなった時にこれまで何でそういったことを学んでこなかったのか、ということになりますし、色々私自身の学習態度として反省するところがあります。特に外国語についてはどうしても実用性というところを求めてしまうところが大きく、私にとって少なくとも英語に関しては文法を学ぶことにはメリットを感じなかったところでした。今後も外国語については色々と学んでみたいと思いますが、まず夏休みは一旦『トム・ブラウンの学校生活』を読みたいと思います。
次は4年辻翔太さんにバトンを渡します。辻さんはタッチジャッジをするのがお好きなようで、機会があるたびに立候補しています。私も以前にタッチジャッジをする機会がありましたが、その時は動きがあまりにもひどく反省すべき点が多かったです。もっと他に聞くべき人がいるようにも思いますが、辻さんにもタッチジャッジについて聞きたいと思います。
ラグビーについて[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2024/06/05(水) 18:45
3年の石澤さんからバトンをもらいました,2年の伊藤佑樹です。「みんなが気づかないこと」に気づくと石澤さんに言われましたが,気づくべきところには気づけていないのが残念ながら私の現状です。記憶も曖昧なのにそれを書き留めず何も残らない私とは違い,石澤さんは色々と覚え記録も工夫されていると聞きました。何とか私は行動を改善しなければならないのですがなかなか難しいです。何かスモブラの機会にでも相談したいです。
(以下もちろんタイトルの通り「ラグビー」の話はしますが,スポーツのラグビーについてはほとんど記載がありません。騙すようなお題になっていますがご了承ください。)
さて,私は以前アメリカに住んでいたことがありまして,当時いた地域についてインターネットで調べ風景を見て懐かしむようなことを時々します。昔住んでいた家,通っていた学校,市街地や道路の風景などいろいろ見て楽しいところがありますし,変化してきたところを見ても面白いです。ただなかなか眺めていても気が付かないことがあるわけで,最近私の住んでいたすぐ近くに当時はなかった矯正歯科医院があるのを発見したのですが,実はそれが5年以上前からあったようです。
そうして眺めていた中で先日良く見慣れた名前を地図で見つけてしまいました。”Rugby”というところが私の以前住んでいた郡にあったのです。住んでいた当時から今に至るまでまったくこれには気が付きませんでした。同じ郡とは言っても郡の面積が1,000㎢以上あるのですが,それでも比較的身近なところにラグビーという地名があったわけです。おそらく住んでいた当時ラグビーの半径5km以内には入ったことがあるのですが,ラグビーに行ったことはなかったのではないかと思います。
ちょっとラグビーがどんなところか風景を見てみると,トウモロコシや大豆の畑が広がる中何軒か家が道路沿いに並び,さらに脇にもちょっとした道があり,もう何軒か家がある,そんな具合の小さな集落でした。町として行政的に組織されているような場所ではなく,人口も少なく,基本的に隣の町と関係しながら生活するようなことなのだろうと思います。それでもそこにはチャペルがあり,日曜礼拝をおこなっているようで,ラグビー地区の中心になっているのだろうと思います。
ここで私が疑問に思ったのは,なんでこの場所にラグビーという場所があるのかということで,地名の由来を調べてみたくなりました。アメリカの場合は植民地としての開拓に関わった人などが由来になっていることがあり,そうしたところでこのラグビーという地名も誰かの名前に由来するのか,あるいはイギリスのラグビーから移住してきたのか,色々と考えられるわけです。昔の資料をインターネットで調べようともしましたが,あまりはっきりしなかったところ,上述のチャペルのウェブサイトに地名の由来が記されていました。「ラグビー」になる前の住人が,”Tom Brown’s School Days at Rugby”に基づきラグビーと名付けたようです。この「トム・ブラウンの学校生活」というのはイギリスの「ラグビースクール」での体験をトマス・ヒューズが書いた本として非常に有名なようですが,私自身読んだことは残念ながらありません。次,リレー日記のバトンが回ってきたときにこの本を紹介できればと思います。ラグビースクールについてはもちろんスポーツのラグビーの歴史としても知りたいところがあるので,ぜひ読みたいと思います。
次は2年同期の定浪君にバトンを渡します。先日部での洗濯物を干すのを1年生と手伝ってくれていた時にいろいろと話しましたが,人間関係に対する持論には興味深いものがありました。今後もぜひお話ししたいと思うのですが,何か派閥みたいになっていくと難しいところがあります。ほどほどの関係でお願いします。
参考: About Our Church. (2024年4月24日). Rugby Chapel. https://www.rugbychapel.com/about/about-our-church.
(以下もちろんタイトルの通り「ラグビー」の話はしますが,スポーツのラグビーについてはほとんど記載がありません。騙すようなお題になっていますがご了承ください。)
さて,私は以前アメリカに住んでいたことがありまして,当時いた地域についてインターネットで調べ風景を見て懐かしむようなことを時々します。昔住んでいた家,通っていた学校,市街地や道路の風景などいろいろ見て楽しいところがありますし,変化してきたところを見ても面白いです。ただなかなか眺めていても気が付かないことがあるわけで,最近私の住んでいたすぐ近くに当時はなかった矯正歯科医院があるのを発見したのですが,実はそれが5年以上前からあったようです。
そうして眺めていた中で先日良く見慣れた名前を地図で見つけてしまいました。”Rugby”というところが私の以前住んでいた郡にあったのです。住んでいた当時から今に至るまでまったくこれには気が付きませんでした。同じ郡とは言っても郡の面積が1,000㎢以上あるのですが,それでも比較的身近なところにラグビーという地名があったわけです。おそらく住んでいた当時ラグビーの半径5km以内には入ったことがあるのですが,ラグビーに行ったことはなかったのではないかと思います。
ちょっとラグビーがどんなところか風景を見てみると,トウモロコシや大豆の畑が広がる中何軒か家が道路沿いに並び,さらに脇にもちょっとした道があり,もう何軒か家がある,そんな具合の小さな集落でした。町として行政的に組織されているような場所ではなく,人口も少なく,基本的に隣の町と関係しながら生活するようなことなのだろうと思います。それでもそこにはチャペルがあり,日曜礼拝をおこなっているようで,ラグビー地区の中心になっているのだろうと思います。
ここで私が疑問に思ったのは,なんでこの場所にラグビーという場所があるのかということで,地名の由来を調べてみたくなりました。アメリカの場合は植民地としての開拓に関わった人などが由来になっていることがあり,そうしたところでこのラグビーという地名も誰かの名前に由来するのか,あるいはイギリスのラグビーから移住してきたのか,色々と考えられるわけです。昔の資料をインターネットで調べようともしましたが,あまりはっきりしなかったところ,上述のチャペルのウェブサイトに地名の由来が記されていました。「ラグビー」になる前の住人が,”Tom Brown’s School Days at Rugby”に基づきラグビーと名付けたようです。この「トム・ブラウンの学校生活」というのはイギリスの「ラグビースクール」での体験をトマス・ヒューズが書いた本として非常に有名なようですが,私自身読んだことは残念ながらありません。次,リレー日記のバトンが回ってきたときにこの本を紹介できればと思います。ラグビースクールについてはもちろんスポーツのラグビーの歴史としても知りたいところがあるので,ぜひ読みたいと思います。
次は2年同期の定浪君にバトンを渡します。先日部での洗濯物を干すのを1年生と手伝ってくれていた時にいろいろと話しましたが,人間関係に対する持論には興味深いものがありました。今後もぜひお話ししたいと思うのですが,何か派閥みたいになっていくと難しいところがあります。ほどほどの関係でお願いします。
参考: About Our Church. (2024年4月24日). Rugby Chapel. https://www.rugbychapel.com/about/about-our-church.
ルール[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2023/11/18(土) 19:00
3年の塩谷さんからバトンをもらいました,1年スタッフの伊藤です。塩谷さんには様々な点で人を惹き付けられる力強さを持っているとプレー以外でも感じます。意外な切り口と塩谷さんはおっしゃっていますが実際にはただひねくれているだけです。
さて,私はこのラグビー部に入ってから半年以上が立ち,入る前はほとんど知らなかったラグビーのルールについてかなり知るようになりました(rules ではなくlawsというのはもっともなのだが,日本協会がルールという言葉を使っているので以下でもルールとします 参照: https://www.rugby-japan.jp/future/rule/)。ルールがわかるようになると試合がどのように展開されていくのか,詳しくわかるようになり,試合を見ながらどういったことが進んでいるのかわかるようになってきました。なんとなくゴールラインを目指している,ということぐらいはルールをそれほど知らなくてもわかると思いますが,その時の具体的な動きというところになると,ルールについてある程度知っていないと理解するのが難しいです。一方,ルールについて詳しくないからと言って,観戦を楽しめないのかといえば,そんなことはなく,それは見方の違いにすぎないように思います。私自身何年か前にたまたまテレビでラグビーの試合を見たときに,ルールについてはほとんど知らなかったものの,それは面白かったと記憶しています。つまり,ルールというのを知らなかったとしても見て様々なことを感じることができ,ルールを知るということによって考えるという次元が増えるということではないかと思います。
こうしたことは様々なスポーツであるわけです。中学生のころ興味本位で審判講習会に行ってからは,サッカーの試合においてオフサイドについてよく見るようになりました。しかし,別にオフサイドというのを考えなかったとしても見ていて面白いわけです。そうした形でなくても,例えばオリンピックで色々な競技を見ているうちに最初とは少し違った見方にをするようになるということはあると思います。その場合もそもそも何か面白いから最初に見ているのであって,別にそれはルールの知識とはあまり関係ないことです。
ここまではスポーツを観戦するという視点でルールとの関係で私が感じてきたことを書いてきましたが,スポーツ自体についても,ルールというものの性質は同じなのではないかと思います。スポーツというのは別にルールが先にあって成り立っているのではなく,何か軸となるものがあって,それに合わせてルールが作られていくように思います。もともとラグビー自体ももととなるフットボールでのルール違反により生まれた競技とされていますが,そうだとすると元の競技としてはルールが存在したわけであり,ラグビーというのはそれがまとめられたルール体系よりもむしろ別の競技性の基礎が根底にあるわけです。そのうえで,ルールというものがラグビーに限らずスポーツを実際の形に作り上げているわけで,ルールがあることによって具体的な戦術を考えることができるようになっているといえるのではないかと思います。私みたいにルールをある程度知ったとはいえまだまだ十分に分かっていないものが言うことではないのかもしれませんが,ラグビーとは何か見つけていきたいです。
あまりルールについて書きすぎると,麻雀のルールを覚えるように多方面から言われてしまいそうなので,このくらいにしておきたいと思います。次は2年の辻金大さんにバトンを渡します。金大さんは膝のけがのためしばらく練習からは休んでいますが,そんな中でも食事などできることをしていらっしゃるようです。
さて,私はこのラグビー部に入ってから半年以上が立ち,入る前はほとんど知らなかったラグビーのルールについてかなり知るようになりました(rules ではなくlawsというのはもっともなのだが,日本協会がルールという言葉を使っているので以下でもルールとします 参照: https://www.rugby-japan.jp/future/rule/)。ルールがわかるようになると試合がどのように展開されていくのか,詳しくわかるようになり,試合を見ながらどういったことが進んでいるのかわかるようになってきました。なんとなくゴールラインを目指している,ということぐらいはルールをそれほど知らなくてもわかると思いますが,その時の具体的な動きというところになると,ルールについてある程度知っていないと理解するのが難しいです。一方,ルールについて詳しくないからと言って,観戦を楽しめないのかといえば,そんなことはなく,それは見方の違いにすぎないように思います。私自身何年か前にたまたまテレビでラグビーの試合を見たときに,ルールについてはほとんど知らなかったものの,それは面白かったと記憶しています。つまり,ルールというのを知らなかったとしても見て様々なことを感じることができ,ルールを知るということによって考えるという次元が増えるということではないかと思います。
こうしたことは様々なスポーツであるわけです。中学生のころ興味本位で審判講習会に行ってからは,サッカーの試合においてオフサイドについてよく見るようになりました。しかし,別にオフサイドというのを考えなかったとしても見ていて面白いわけです。そうした形でなくても,例えばオリンピックで色々な競技を見ているうちに最初とは少し違った見方にをするようになるということはあると思います。その場合もそもそも何か面白いから最初に見ているのであって,別にそれはルールの知識とはあまり関係ないことです。
ここまではスポーツを観戦するという視点でルールとの関係で私が感じてきたことを書いてきましたが,スポーツ自体についても,ルールというものの性質は同じなのではないかと思います。スポーツというのは別にルールが先にあって成り立っているのではなく,何か軸となるものがあって,それに合わせてルールが作られていくように思います。もともとラグビー自体ももととなるフットボールでのルール違反により生まれた競技とされていますが,そうだとすると元の競技としてはルールが存在したわけであり,ラグビーというのはそれがまとめられたルール体系よりもむしろ別の競技性の基礎が根底にあるわけです。そのうえで,ルールというものがラグビーに限らずスポーツを実際の形に作り上げているわけで,ルールがあることによって具体的な戦術を考えることができるようになっているといえるのではないかと思います。私みたいにルールをある程度知ったとはいえまだまだ十分に分かっていないものが言うことではないのかもしれませんが,ラグビーとは何か見つけていきたいです。
あまりルールについて書きすぎると,麻雀のルールを覚えるように多方面から言われてしまいそうなので,このくらいにしておきたいと思います。次は2年の辻金大さんにバトンを渡します。金大さんは膝のけがのためしばらく練習からは休んでいますが,そんな中でも食事などできることをしていらっしゃるようです。
アーカイブ
- 2025年12月(11)
- 2025年11月(12)
- 2025年10月(13)
- 2025年9月(11)
- 2025年8月(11)
- 2025年7月(11)
- 2025年6月(10)
- 2025年5月(8)
- 2025年4月(9)
- 2025年3月(9)
- 2025年2月(15)
- 2025年1月(2)
- 2024年12月(18)
- 2024年11月(12)
- 2024年10月(12)
- 2024年9月(13)
- 2024年8月(11)
- 2024年7月(12)
- 2024年6月(8)
- 2024年5月(9)
- 2024年4月(8)
- 2024年3月(8)
- 2024年2月(19)
- 2024年1月(7)
- 2023年12月(9)
- 2023年11月(12)
- 2023年10月(11)
- 2023年9月(12)
- 2023年8月(11)
- 2023年7月(11)
- 2023年6月(8)
- 2023年5月(7)
- 2023年4月(8)
- 2023年3月(7)
- 2023年2月(15)
- 2023年1月(7)
- 2022年12月(23)
- 2022年11月(14)
- 2022年10月(13)
- 2022年9月(14)
- 2022年8月(14)
- 2022年7月(16)
- 2022年6月(10)
- 2022年5月(11)
- 2022年4月(12)
- 2022年3月(10)
- 2022年2月(15)
- 2022年1月(4)
- 2021年12月(12)
- 2021年11月(12)
- 2021年10月(14)
- 2021年9月(12)
- 2021年8月(12)
- 2021年7月(12)
- 2021年6月(11)
- 2021年5月(12)
- 2021年4月(11)
- 2021年3月(13)
- 2021年2月(10)
- 2021年1月(21)
- 2020年12月(11)
- 2020年11月(12)
- 2020年10月(13)
- 2020年9月(12)
- 2020年8月(14)
- 2020年7月(12)
- 2020年6月(12)
- 2020年5月(13)
- 2020年4月(12)
- 2020年3月(13)
- 2020年2月(12)
- 2020年1月(4)
- 2019年12月(10)
- 2019年11月(15)
- 2019年10月(11)
- 2019年9月(13)
- 2019年8月(13)
- 2019年7月(10)
- 2019年6月(8)
- 2019年5月(13)
- 2019年4月(7)
- 2019年3月(7)
- 2019年2月(5)
- 2019年1月(7)
- 2018年12月(15)
- 2018年11月(12)
- 2018年10月(15)
- 2018年9月(10)
- 2018年8月(7)
- 2018年7月(6)
- 2018年6月(10)
- 2018年5月(12)
- 2018年4月(11)
- 2018年3月(5)
- 2017年12月(11)
- 2017年11月(13)
- 2017年10月(12)
- 2017年9月(11)
- 2017年8月(12)
- 2017年7月(10)
- 2017年6月(10)
- 2017年5月(17)
- 2017年4月(10)
- 2017年3月(13)
- 2017年2月(4)
- 2016年12月(15)
- 2016年11月(12)
- 2016年10月(14)
- 2016年9月(12)
- 2016年8月(12)
- 2016年7月(15)
- 2016年6月(9)
- 2016年5月(9)
- 2016年4月(11)
- 2016年3月(10)
- 2016年2月(7)
- 2015年12月(8)
- 2015年11月(11)
- 2015年10月(10)
- 2015年9月(10)
- 2015年8月(5)
- 2015年7月(7)
- 2015年6月(11)
- 2015年5月(13)
- 2015年4月(8)
- 2015年3月(9)
- 2015年2月(12)
- 2015年1月(11)
- 2014年12月(12)
- 2014年11月(10)
- 2014年10月(12)
- 2014年9月(12)
- 2014年8月(12)
- 2014年7月(6)
- 2014年6月(5)
- 2014年5月(13)
- 2014年4月(11)
- 2014年3月(14)
- 2014年2月(7)
- 2013年12月(23)
- 2013年11月(29)
- 2013年10月(32)
- 2013年9月(30)
- 2013年8月(14)
- 2013年7月(15)
- 2013年6月(23)
- 2013年5月(33)
- 2013年4月(27)
- 2013年3月(20)
- 2013年2月(10)
- 2013年1月(1)
- 2012年12月(13)
- 2012年11月(11)
- 2012年10月(24)
- 2012年9月(13)
- 2012年8月(9)
- 2012年7月(5)
- 2012年6月(8)
- 2012年5月(11)
- 2012年4月(9)
- 2012年3月(10)
- 2012年2月(8)
- 2011年12月(6)
- 2011年11月(6)
- 2011年10月(7)
- 2011年9月(9)
- 2011年8月(10)
- 2011年7月(5)
- 2011年6月(5)
- 2011年5月(9)
- 2011年4月(7)
- 2011年3月(8)
- 2011年2月(4)
ブログ最新記事
- 挑戦 (12/27 22:41)
- 愉快な4年間 (12/26 22:13)
- 大航海 (12/26 00:00)
- 巨人の肩の上 (12/24 21:29)
- セカンドの7番 (12/23 22:50)
- ラグビーに感謝 (12/22 22:21)
- 勇気 (12/19 23:55)
- ボール・イン! (12/17 19:00)
- 駒場のフィン・ラッセル (12/16 19:22)
- タックルも人間も腰は低い方がカッコいい (12/15 19:00)
- パワーグリップの詩 (12/01 21:08)
- Marry Me Chicken (11/28 10:31)
- 愉快で最高な仲間たち (11/26 18:43)
- 男磨きはボディビルへ (11/25 16:43)
- fall season (11/22 22:18)
- 類まれな才能 (11/20 09:32)
- しんらい (11/19 23:02)
- あの坂田が!?!?泣いたアニメ (11/19 18:27)
- 埼玉旅行記 (11/16 18:05)
- 渋谷のサグラダ・ファミリア (11/15 20:40)





.jpg)