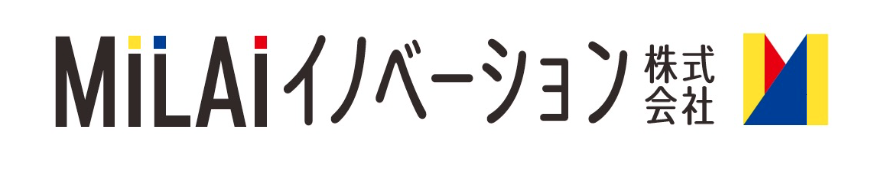ブログ 佐々木 凜さんが書いた記事
| 次へ>> |
出会い[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2024/12/15(日) 03:25
昴からバトンを受け取りました、佐々木です。昴はラグビーをするために東大を志望したという変わったやつで、彼のおかげでうちの同期は多くの仲間が集まり、1年生の頃から彼のラグビー愛がこの学年を引っ張ってきたように思います。私と昴は同じ新歓委員で、メディカルのメンターでもあり、この4年間で同期選手の中では一番長い時間を一緒に過ごしてきた気がします。今年もよくご飯に行って真面目な話もくだらない話もしましたが、昴は何も考えていないように見えて自分の信念と強い軸を持っている人なので、私が弱気になった時に背中を押してくれたこともありました。今までぶりっ子やら赤ちゃんやらといじってしまいましたが、今年は4年としての責任がにじみ頼もしく、赤ちゃんキャラもすっかり卒業のようです。後輩の前で私の顔真似をしてばかにしていたことは全然気にしていないので、安心して今後も仲良くしてください。
ついに自分もラストリレー日記を書く時期が来てしまいました。これまで自分の趣味や思想を語らせてもらってきましたが、ラグビーや部活についてはあまり書いてこなかったので、最後ということで自分のラグビーとの出会いから東大で過ごした4年間について書き残しておきたいと思います。最近同期にも後輩にも私は何を考えているのか分からない、とよく言われるので、自分の考えてきたことを率直に書いたつもりです。身勝手だと思われるかもしれないし、見苦しい部分もあるかと思いますが、どうぞお許しください。
私が初めてラグビーに出会ったのは小学校3年生くらいだったと思う。父がコーチをしていたタグラグビークラブに弟が行っていたので、私も一緒に参加するようになった。ここでのタグとの出会いが私の人生に大きな影響を与えることになる。私が小学校5年生までは週に1回の練習でタグラグビーを楽しむためにやっている感じだったが、小学校6年生になってから県内の強いスクールのチームと一緒に練習して触発されたことで、少人数での平日毎日の朝練がスタートした。それから次第に朝練に参加する人数が増えていって、チームは次第に勝利という目的達成のために一切の妥協を許さない超スパルタ集団へと変容していった。コーチは信じられないほど厳しく(今のコンプライアンス的には絶対にアウト)耐えられずにやめていく人もいたが、ラグビーのスキルや指導は的確で、チームはあっという間に強くなった。私がキャプテンだった年は東北大会に行くことができなかったが、卒業した後も毎日朝練に参加し、弟たちの練習相手になった。私が卒業した2年後に弟たちは全国で3位になり、数年後には後輩たちが全国優勝を成し遂げた。ここでの経験を通して私はただ楽しいだけではなく、本気で努力して上達することの楽しさを知り、スポーツや部活は和気藹々と楽しむ場所ではなく、勝つためにどんな時も真剣に集中した状態でやるものだという価値観が根付いた。同時に自分が表舞台に立てなくともそれをサポートすることに喜びを感じ、これがのちに私がマネージャー業に打ち込むことになる布石の一つだったのかもしれないと思う。
入学した高校のラグビー部の顧問が父の大学の部活の後輩だった、ということもあり、私はもはや必然的に高校のラグビー部のマネージャーとして入部した。しかし、私の高校は人数が少なく、毎年15人揃うかぎりぎりで、当然練習もまともにできないのでタッチフットやハンドリング練習などコンタクトのない練習は私も選手と一緒にやっていた。福島はラグビーの強豪校がないので、人数さえ集まればどのチームにも花園に行くチャンスがあると言えるが、なんせ人を集めるという行為が一番難しい。必死に勧誘して人を集めても、元々モチベーションが高い部員が集まっているわけではないので続けさせるのも至難の業だ。練習で徹底的に追い込まれ、ついていけないやつは切り捨てられていたタグの文化とのギャップは凄まじく、周りの部員との温度差があることは感じていた。それでも私は部員に愛着を感じていたし、なんとかしてこのチームを勝たせたいと思っていたが、3年の春にはコロナが直撃して1ヶ月は学校にも行けなくなり、同期の中には受験を理由に途中で退部を考えている人もいて、15人を集めるのがやっとという状況だった。みんなと一緒に練習するのは楽しかったし、結局同期全員で最後の花園予選までやり切れたことは本当に意味があったと思うが、私ばかりがやる気を出しても周りはついてこず、1人で空回りしている感は否めなかった3年間だったと思う。
大学に入学した当初、両親の影響で運動会の部活に入ることは決めていたが、ラグビー部のスタッフを続けるか、他の運動部に入って自分がプレーヤーとして活動するかは決めかねていた。でも、何回か新歓に行くうちに私はラグビー部の雰囲気が気に入り、気がついたら結局他の新歓もろくに行かずに早々にラグビー部への入部を決めてしまった。高校時代の不完全燃焼感を払拭したい、という気持ちもどこかにあったのかもしれない。
ラグビー部に入部して、高校までとは規模の違う大学の部活の環境や、専門的なスタッフ業務に感銘を受けたのはもちろんだが、今振り返ると私が一番幸運だったことはこの同期たちに出会ったことだと思う。半数近くが大学からラグビーというしんどい競技を始めることを選んだにも関わらず、藤井さんたちジュニアコーチの熱心な指導のおかげもあり、同期のみんなは瞬く間に大きくなり、成長し、彼らのモチベーションの高さやまっすぐさに驚いた。自分が働きかけたことに対して、それ以上の反応が返ってくることが多く、これは高校では一度もなかった経験で感激した。そして彼らとなら本気で頑張る意味がある、絶対にみんなと結果を出したいと強く思うようになった。初めての大学ラグビーの春シーズン、夏シーズン、対抗戦を迎え、自分自身も1年生の途中からレフリーを始めるなど、すべてが新鮮に感じられる中であっという間に一年が過ぎていった。
2年生になって、私はレフリー以外にもメディカルや広報の仕事も本格的に担当するようになり、スタッフとして自分ができることが増えていった。この年の4年生はスタッフも選手も人数が多く、期待がかなり高まっていた中で、成蹊戦は本当に勝てるんじゃないかと思える試合だった。しかし、対抗戦は結局4勝3敗で入替戦に進むことはできず、改めてこのチームが掲げている目標と現実との距離を実感した。元々1年生の頃から学年で立てた対抗戦Aで勝つという目標があまりに高すぎて現実味がないことに違和感を感じ続けていたので、この年スイカを着てすでに試合に出場していた同期と直接話もした。実際に試合に出て戦っている同期が自分たちの目標をどう感じているのか知りたかった。結局学年で話し合って自分たちの目標は毎年更新されていくわけだが、私の心の中には自分たちの代で歴史を変えるためにはどうすればいいのか、ということが常にあり、それが部活を頑張る最大のモチベーションだった。
3年生になって、スタッフは最高学年となり、選手も4年生が少ない中で、本格的に自分たちの代が中心とならなければいけない年になった。2年の京大戦の後にデイビスとあと2年間チャレンジできる環境に感謝して来年はこの代が中心になれるように頑張ろうと話したことを覚えている。しかし実際にシーズンが始まると想像以上に課題が多かった。春はスタッフの人数が半分以下になった中で今までの仕事量をどうまかなうか、新歓がうまくいかなかったらインカレ化も免れない、というくらいには追い込まれていたから、スタッフ新歓は2月から始動し死ぬ気でやれることをやった。幸運にも今の2年生がたくさん入部してくれたおかげでスタッフの人手不足は解消されたが、たくさんの新入生に仕事を教えながら少数の上級生で試合を回していたのでかなりカツカツだった。しかも、私自身はレフリーで外部の試合に行ってチームに帯同できないことも多く、なかなか試合運営に協力できず申し訳なさともどかしさを感じていた。1年間を通して、首脳陣とのコミュニケーションや、スタッフ内部の問題、チームとしても思うような結果が出せず、辞めそうな同期は引き止めなくてはいけない、など問題が次々と起こっていく中で、チームの雰囲気を変えるため、自分たちの代で結果を出すためにはどうしたらいいのかをずっと考え、たくさんの人と話し合った。私はこの一年のおそらく9割くらい、四六時中部活のことを考えては悩み、ほとんど全てのキャパを部活に割いていた気がするし、正直人生でもあまり経験したことがないくらいしんどい期間もあった。だからこそ、たくさん迷惑も心配もかけたけれど自分たちの決断を受け入れてくれた先輩後輩、周りのサポートしてくれている人たち、当時ぎりぎりまですり減っていた私を支えてくれた家族のためにも、何がなんでも来年結果を出さないといけない、という責任を感じるとともに強い覚悟を固めた一年だった。
そしてついにラストシーズンを迎えた。今までレフリーのために外部にも出してもらい、チームを離れることもあった自分がまさかスタッフの責任者になるなんて想像もしていなかったが、この一年でこの立場になったことで自分の中での「スタッフ」としての部活への向き合い方が大きく変化したように思う。今までは、自分が関与していない仕事でミスが起きてもそれは本人たちの責任だと心のどこかで思っていた節があったが、スタッフ長になって首脳陣や他の選手ともコミュニケーションをとっていくうちに、自分の役割は単に自分の仕事に対して責任を負うのではなく、スタッフ組織全員の仕事に対しての責任をとる、ということだと気づいた。それから、スタッフ内で起きるミスや問題は全て自分事として捉えて、ミスを防ぐために自分の働きかけに何が足りていなかったのかを考えるようになった。スタッフ組織全体を成長させるため、毎月の目標設定と上級生との面談、ミスを減らすための呼びかけや話し合い、本質ではないが手段としての罰則やルールづくり、できるだけ全員の意見を聞き、取り入れながらみんなで最適な体制を模索しようと試みた。選手とスタッフの垣根を越えて互いが要求し合えるような関係を作ることも目標の一つで、選手からの要望にはできるだけ向き合い、こちらからも選手に変えてほしいことは伝えてきたつもりだった。春シーズン、夏合宿としんどい練習を選手とスタッフみんなで乗り越え、確かな手応えと周りからの期待を背負った対抗戦が始まった。しかし、結果は4勝3敗で東大は対抗戦B4位となり、この代はまたも東大の歴史を変えることができなかった。できることはやり尽くしてきたつもりだったが、それでも入替戦という目標には届かなかった。この4年間、この同期たちと歴史を変えるということだけを目標にしてやってきたからこそ、明学戦後、武蔵戦後の悔しさと喪失感は言葉にできず、気持ちを切り替えることは非常に難しかった。正直今でも心の底から悔しいという気持ちを拭い去ることはできないし、これはもうこの結果が変わらない以上どうしようもないものだと思う。このままでは悔しくて終われない、もう一回、もう一年チャンスがあれば、と思わないこともないが、学生スポーツというのは4年間限りのもので、この限られたチャンスで挑戦することに意味があるとも思う。以前自分のリレー日記でも触れたが、毎年4年生のラストリレー日記を読むたびに自分は「目標は叶わなかったけれどなんだかんだ頑張ったので良かった」的なことは絶対に書きたくないと思っていたのに、結局同じような立場になってしまったことが本当に悔しい。
東大に入学してからの4年間を振り返ると、私も昴と同じく(というかこの部にはたくさんいると思うが)、東大まで来て勉強もせず、大学生らしい遊びをするわけでもなく、ほぼ部活しかしていなかった、変なやつだ。今思うと、東大ラグビー部も私の高校時代のラグビー部と規模が違うだけで本質は結局同じだった。普通入学する時に東大に入って部活に全てを捧げよう、なんて思っている奴はほとんどいない。そもそも最初からラグビーをやろうと思っている奴なんてほぼゼロに等しいし、それでもどうにか騙し騙しで入部させるが、そこから死ぬほどしんどい練習を乗り越えさせる、モチベーションを維持させるのは非常に難しい。どうしても途中で辞めてしまう人も出てくる。これはスポーツ推薦などなく、たとえ入りたくても受験でラグビー経験者がどんどんふるい落とされる東大では致し方ないことだろう。だから結局まずはとにかくこの部に入る母数を増やすこと、そしてしんどくて辞めそうなやつも必死に繋ぎ止めて残らせる、ということをやらないといけない。毎年必死に新歓して、辞めそうな同期や後輩を引き止めて、結局東大にきても高校の時と同じことをしていたなあ、と思う。私はあの頃の自分と比べて、何か変わったのだろうか。
この4年間の意味は今すぐには分からないだろうし、とにかく頑張ったからそれでよかった、というような薄っぺらい言葉では片付けたくない。でも今後の人生でこの経験や選択を正解にするのは自分自身だし、私はここを選んで正解だった、ということは自信をもって言える。引退間近の老害の戯言ながらに、今の、そして未来の後輩に伝えたいことは、とにかく人を、一緒に戦う仲間を集めろ、ということと、このラグビーという素晴らしいスポーツに出会い、東大ラグビー部に入る、という選択をしたあなたは絶対に間違っていないということだ。
最後に私を4年間この部活に夢中にさせてくれた最高の同期たちに。みんなに出会って一緒に同じ目標を追うことができたことがこの4年間の一番の財産です。おっとりしていてゆるふわで、でもラグビーに対しては真面目で大学生とは思えないくらい純粋で素直なみんなとだったからこそ、私もここまで頑張ることができました。本当にこの代でよかったと心から思います。引退してもずっと大事な仲間でいましょう。
次は見事面白さランキングNo.1の座に輝いた清和にバトンを渡します。清和は普段は人の話を100倍は盛ってみんなに広めるし、いつも本気なのかネタなのか分からないトーンで絶妙に失礼なことを言ってくるふざけたやつですが、彼の部活に対する熱意や意識の高さは紛れもない本物で、練習中と練習外のオンオフがきっちりしているところはとても尊敬しています。今シーズンも清和のパワフルなプレーに何度も会場が沸いていたし、肩が万全ではない中、チームを引っ張ってくれてありがとう。私は清和独特の笑いのセンスが好きで、私生活でいくらだらしなくても清和節で誤魔化されるとなぜか許してしまう部分があるのが悔しいです。そういえば今思い出しましたが、何年も前に貸したエアビ代もまだ返ってきていないような気がします。来年は私と同じく彼も留年暇組なのでみんなで旅行でも行きましょう、北朝鮮とルワンダはさすがになしです。
ついに自分もラストリレー日記を書く時期が来てしまいました。これまで自分の趣味や思想を語らせてもらってきましたが、ラグビーや部活についてはあまり書いてこなかったので、最後ということで自分のラグビーとの出会いから東大で過ごした4年間について書き残しておきたいと思います。最近同期にも後輩にも私は何を考えているのか分からない、とよく言われるので、自分の考えてきたことを率直に書いたつもりです。身勝手だと思われるかもしれないし、見苦しい部分もあるかと思いますが、どうぞお許しください。
私が初めてラグビーに出会ったのは小学校3年生くらいだったと思う。父がコーチをしていたタグラグビークラブに弟が行っていたので、私も一緒に参加するようになった。ここでのタグとの出会いが私の人生に大きな影響を与えることになる。私が小学校5年生までは週に1回の練習でタグラグビーを楽しむためにやっている感じだったが、小学校6年生になってから県内の強いスクールのチームと一緒に練習して触発されたことで、少人数での平日毎日の朝練がスタートした。それから次第に朝練に参加する人数が増えていって、チームは次第に勝利という目的達成のために一切の妥協を許さない超スパルタ集団へと変容していった。コーチは信じられないほど厳しく(今のコンプライアンス的には絶対にアウト)耐えられずにやめていく人もいたが、ラグビーのスキルや指導は的確で、チームはあっという間に強くなった。私がキャプテンだった年は東北大会に行くことができなかったが、卒業した後も毎日朝練に参加し、弟たちの練習相手になった。私が卒業した2年後に弟たちは全国で3位になり、数年後には後輩たちが全国優勝を成し遂げた。ここでの経験を通して私はただ楽しいだけではなく、本気で努力して上達することの楽しさを知り、スポーツや部活は和気藹々と楽しむ場所ではなく、勝つためにどんな時も真剣に集中した状態でやるものだという価値観が根付いた。同時に自分が表舞台に立てなくともそれをサポートすることに喜びを感じ、これがのちに私がマネージャー業に打ち込むことになる布石の一つだったのかもしれないと思う。
入学した高校のラグビー部の顧問が父の大学の部活の後輩だった、ということもあり、私はもはや必然的に高校のラグビー部のマネージャーとして入部した。しかし、私の高校は人数が少なく、毎年15人揃うかぎりぎりで、当然練習もまともにできないのでタッチフットやハンドリング練習などコンタクトのない練習は私も選手と一緒にやっていた。福島はラグビーの強豪校がないので、人数さえ集まればどのチームにも花園に行くチャンスがあると言えるが、なんせ人を集めるという行為が一番難しい。必死に勧誘して人を集めても、元々モチベーションが高い部員が集まっているわけではないので続けさせるのも至難の業だ。練習で徹底的に追い込まれ、ついていけないやつは切り捨てられていたタグの文化とのギャップは凄まじく、周りの部員との温度差があることは感じていた。それでも私は部員に愛着を感じていたし、なんとかしてこのチームを勝たせたいと思っていたが、3年の春にはコロナが直撃して1ヶ月は学校にも行けなくなり、同期の中には受験を理由に途中で退部を考えている人もいて、15人を集めるのがやっとという状況だった。みんなと一緒に練習するのは楽しかったし、結局同期全員で最後の花園予選までやり切れたことは本当に意味があったと思うが、私ばかりがやる気を出しても周りはついてこず、1人で空回りしている感は否めなかった3年間だったと思う。
大学に入学した当初、両親の影響で運動会の部活に入ることは決めていたが、ラグビー部のスタッフを続けるか、他の運動部に入って自分がプレーヤーとして活動するかは決めかねていた。でも、何回か新歓に行くうちに私はラグビー部の雰囲気が気に入り、気がついたら結局他の新歓もろくに行かずに早々にラグビー部への入部を決めてしまった。高校時代の不完全燃焼感を払拭したい、という気持ちもどこかにあったのかもしれない。
ラグビー部に入部して、高校までとは規模の違う大学の部活の環境や、専門的なスタッフ業務に感銘を受けたのはもちろんだが、今振り返ると私が一番幸運だったことはこの同期たちに出会ったことだと思う。半数近くが大学からラグビーというしんどい競技を始めることを選んだにも関わらず、藤井さんたちジュニアコーチの熱心な指導のおかげもあり、同期のみんなは瞬く間に大きくなり、成長し、彼らのモチベーションの高さやまっすぐさに驚いた。自分が働きかけたことに対して、それ以上の反応が返ってくることが多く、これは高校では一度もなかった経験で感激した。そして彼らとなら本気で頑張る意味がある、絶対にみんなと結果を出したいと強く思うようになった。初めての大学ラグビーの春シーズン、夏シーズン、対抗戦を迎え、自分自身も1年生の途中からレフリーを始めるなど、すべてが新鮮に感じられる中であっという間に一年が過ぎていった。
2年生になって、私はレフリー以外にもメディカルや広報の仕事も本格的に担当するようになり、スタッフとして自分ができることが増えていった。この年の4年生はスタッフも選手も人数が多く、期待がかなり高まっていた中で、成蹊戦は本当に勝てるんじゃないかと思える試合だった。しかし、対抗戦は結局4勝3敗で入替戦に進むことはできず、改めてこのチームが掲げている目標と現実との距離を実感した。元々1年生の頃から学年で立てた対抗戦Aで勝つという目標があまりに高すぎて現実味がないことに違和感を感じ続けていたので、この年スイカを着てすでに試合に出場していた同期と直接話もした。実際に試合に出て戦っている同期が自分たちの目標をどう感じているのか知りたかった。結局学年で話し合って自分たちの目標は毎年更新されていくわけだが、私の心の中には自分たちの代で歴史を変えるためにはどうすればいいのか、ということが常にあり、それが部活を頑張る最大のモチベーションだった。
3年生になって、スタッフは最高学年となり、選手も4年生が少ない中で、本格的に自分たちの代が中心とならなければいけない年になった。2年の京大戦の後にデイビスとあと2年間チャレンジできる環境に感謝して来年はこの代が中心になれるように頑張ろうと話したことを覚えている。しかし実際にシーズンが始まると想像以上に課題が多かった。春はスタッフの人数が半分以下になった中で今までの仕事量をどうまかなうか、新歓がうまくいかなかったらインカレ化も免れない、というくらいには追い込まれていたから、スタッフ新歓は2月から始動し死ぬ気でやれることをやった。幸運にも今の2年生がたくさん入部してくれたおかげでスタッフの人手不足は解消されたが、たくさんの新入生に仕事を教えながら少数の上級生で試合を回していたのでかなりカツカツだった。しかも、私自身はレフリーで外部の試合に行ってチームに帯同できないことも多く、なかなか試合運営に協力できず申し訳なさともどかしさを感じていた。1年間を通して、首脳陣とのコミュニケーションや、スタッフ内部の問題、チームとしても思うような結果が出せず、辞めそうな同期は引き止めなくてはいけない、など問題が次々と起こっていく中で、チームの雰囲気を変えるため、自分たちの代で結果を出すためにはどうしたらいいのかをずっと考え、たくさんの人と話し合った。私はこの一年のおそらく9割くらい、四六時中部活のことを考えては悩み、ほとんど全てのキャパを部活に割いていた気がするし、正直人生でもあまり経験したことがないくらいしんどい期間もあった。だからこそ、たくさん迷惑も心配もかけたけれど自分たちの決断を受け入れてくれた先輩後輩、周りのサポートしてくれている人たち、当時ぎりぎりまですり減っていた私を支えてくれた家族のためにも、何がなんでも来年結果を出さないといけない、という責任を感じるとともに強い覚悟を固めた一年だった。
そしてついにラストシーズンを迎えた。今までレフリーのために外部にも出してもらい、チームを離れることもあった自分がまさかスタッフの責任者になるなんて想像もしていなかったが、この一年でこの立場になったことで自分の中での「スタッフ」としての部活への向き合い方が大きく変化したように思う。今までは、自分が関与していない仕事でミスが起きてもそれは本人たちの責任だと心のどこかで思っていた節があったが、スタッフ長になって首脳陣や他の選手ともコミュニケーションをとっていくうちに、自分の役割は単に自分の仕事に対して責任を負うのではなく、スタッフ組織全員の仕事に対しての責任をとる、ということだと気づいた。それから、スタッフ内で起きるミスや問題は全て自分事として捉えて、ミスを防ぐために自分の働きかけに何が足りていなかったのかを考えるようになった。スタッフ組織全体を成長させるため、毎月の目標設定と上級生との面談、ミスを減らすための呼びかけや話し合い、本質ではないが手段としての罰則やルールづくり、できるだけ全員の意見を聞き、取り入れながらみんなで最適な体制を模索しようと試みた。選手とスタッフの垣根を越えて互いが要求し合えるような関係を作ることも目標の一つで、選手からの要望にはできるだけ向き合い、こちらからも選手に変えてほしいことは伝えてきたつもりだった。春シーズン、夏合宿としんどい練習を選手とスタッフみんなで乗り越え、確かな手応えと周りからの期待を背負った対抗戦が始まった。しかし、結果は4勝3敗で東大は対抗戦B4位となり、この代はまたも東大の歴史を変えることができなかった。できることはやり尽くしてきたつもりだったが、それでも入替戦という目標には届かなかった。この4年間、この同期たちと歴史を変えるということだけを目標にしてやってきたからこそ、明学戦後、武蔵戦後の悔しさと喪失感は言葉にできず、気持ちを切り替えることは非常に難しかった。正直今でも心の底から悔しいという気持ちを拭い去ることはできないし、これはもうこの結果が変わらない以上どうしようもないものだと思う。このままでは悔しくて終われない、もう一回、もう一年チャンスがあれば、と思わないこともないが、学生スポーツというのは4年間限りのもので、この限られたチャンスで挑戦することに意味があるとも思う。以前自分のリレー日記でも触れたが、毎年4年生のラストリレー日記を読むたびに自分は「目標は叶わなかったけれどなんだかんだ頑張ったので良かった」的なことは絶対に書きたくないと思っていたのに、結局同じような立場になってしまったことが本当に悔しい。
東大に入学してからの4年間を振り返ると、私も昴と同じく(というかこの部にはたくさんいると思うが)、東大まで来て勉強もせず、大学生らしい遊びをするわけでもなく、ほぼ部活しかしていなかった、変なやつだ。今思うと、東大ラグビー部も私の高校時代のラグビー部と規模が違うだけで本質は結局同じだった。普通入学する時に東大に入って部活に全てを捧げよう、なんて思っている奴はほとんどいない。そもそも最初からラグビーをやろうと思っている奴なんてほぼゼロに等しいし、それでもどうにか騙し騙しで入部させるが、そこから死ぬほどしんどい練習を乗り越えさせる、モチベーションを維持させるのは非常に難しい。どうしても途中で辞めてしまう人も出てくる。これはスポーツ推薦などなく、たとえ入りたくても受験でラグビー経験者がどんどんふるい落とされる東大では致し方ないことだろう。だから結局まずはとにかくこの部に入る母数を増やすこと、そしてしんどくて辞めそうなやつも必死に繋ぎ止めて残らせる、ということをやらないといけない。毎年必死に新歓して、辞めそうな同期や後輩を引き止めて、結局東大にきても高校の時と同じことをしていたなあ、と思う。私はあの頃の自分と比べて、何か変わったのだろうか。
この4年間の意味は今すぐには分からないだろうし、とにかく頑張ったからそれでよかった、というような薄っぺらい言葉では片付けたくない。でも今後の人生でこの経験や選択を正解にするのは自分自身だし、私はここを選んで正解だった、ということは自信をもって言える。引退間近の老害の戯言ながらに、今の、そして未来の後輩に伝えたいことは、とにかく人を、一緒に戦う仲間を集めろ、ということと、このラグビーという素晴らしいスポーツに出会い、東大ラグビー部に入る、という選択をしたあなたは絶対に間違っていないということだ。
最後に私を4年間この部活に夢中にさせてくれた最高の同期たちに。みんなに出会って一緒に同じ目標を追うことができたことがこの4年間の一番の財産です。おっとりしていてゆるふわで、でもラグビーに対しては真面目で大学生とは思えないくらい純粋で素直なみんなとだったからこそ、私もここまで頑張ることができました。本当にこの代でよかったと心から思います。引退してもずっと大事な仲間でいましょう。
次は見事面白さランキングNo.1の座に輝いた清和にバトンを渡します。清和は普段は人の話を100倍は盛ってみんなに広めるし、いつも本気なのかネタなのか分からないトーンで絶妙に失礼なことを言ってくるふざけたやつですが、彼の部活に対する熱意や意識の高さは紛れもない本物で、練習中と練習外のオンオフがきっちりしているところはとても尊敬しています。今シーズンも清和のパワフルなプレーに何度も会場が沸いていたし、肩が万全ではない中、チームを引っ張ってくれてありがとう。私は清和独特の笑いのセンスが好きで、私生活でいくらだらしなくても清和節で誤魔化されるとなぜか許してしまう部分があるのが悔しいです。そういえば今思い出しましたが、何年も前に貸したエアビ代もまだ返ってきていないような気がします。来年は私と同じく彼も留年暇組なのでみんなで旅行でも行きましょう、北朝鮮とルワンダはさすがになしです。
先生[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2024/09/16(月) 15:59
同期の塩谷からバトンを受け取りました、4年スタッフの佐々木です。夏合宿では、慶應との合同練習後の午後オフに自主的にフィッツで追い込むなど塩谷のプレーや態度から4年としての自覚や責任、気迫を感じ、非常に頼もしく思っていました。早く怪我を治して対抗戦の舞台で暴れてくれるのを待っています。4年間で私の新しい面を知ったそうですが、まだまだ氷山の一角にすぎないので今後とも仲良くしましょう。
ついに9月に突入し、対抗戦も2戦が終わりました。このシーズンで結果を出すために過ごしてきた4年間を証明できるように責任と覚悟を持って、自分にできることを出し切りたいと思います。
突然ですが、高校時代大好きだった生物の先生の話をしたいと思います。若いイケメンの先生のリアコだったとかではなく、45歳くらいの小太りのおじさんです。私は文系だったのでその先生と実際に関わったのは1年間だけでしたが、たった一年でその先生は私の人生にとても大きなインパクトを残してきました。
その先生は、教科書も参考書も一切使わず、事前に公開している自分の授業の録画映像と手作りのレジュメ的なものをみてわからないことを授業中に質問しろ、というとても特殊な授業スタイルをとっていました。どの質問に対しても、先生はただ知識を回答するのではなく、なんでそうなると思う?と生徒に考えさせて、生物基礎にしては深すぎる本質的な話をしました。また、授業時間の半分くらいは大体先生の雑談で、自分の人生の挫折や教訓、自分が今までに教えてきた生徒たちの面白い話を無限にしていました。丸々1時間、先生の雑談だけで授業が終わった時も何回かありました。先生の話が上手だったこともありますが、先生が見てきた生徒一人一人の人間ドラマがめちゃくちゃ面白く、私は毎回ずっと雑談してくれないかなあと思っていました。あまりに受験対策向けではないので、当然中には反発し、勝手に自習している生徒もいましたが、私には先生の常識にとらわれない自由な感じが刺さりました。授業時間に間に合わないのが日常茶飯事で、帰るのがめんどくさいからと理科室にベッドを持ち込み、そこで寝泊まりしながら毎日カップ麺を食べて生活するなど、ぶっ飛んでいてめちゃくちゃ適当な感じなのに、生物の知識は誰よりも深く、過去に文部科学大臣優秀教員の表彰も受けるほど能力は高いというのも、カリスマ性が高くてかっこよかったです。私は生物の授業で先生と話したいがために、席替えでわざわざ教卓の正面の席を希望し、授業中は毎回先生の真ん前で、終始先生を凝視して話を聞いている、自他ともに認めるガチファンでした。
1年の最後の生物の授業の時に、先生は東日本大震災のドキュメンタリーを教室で流してみんなで鑑賞した後に、自分が当時経験したことを話しました。先生が勤めていた学校は避難所になり、避難者が増えすぎて食料や衣類などの物品が不足したため、隣の地域から物品を分けてもらおうとしたらそこは行政の管轄が違うから、と断られたこと。消息不明の家族を探して訪れた人に、それは個人情報だからと言って避難者の名簿を見せることが禁じられたこと。避難してきた原子力発電所の職員に「まだ世の中には報道されていないが近いうちに1号機以外の原発も爆発すると言われているから、先生たちだけでも私たちを置いて逃げてくれ。ここまで私たちのために避難所を運営してくれてありがとう。」と告げられたこと。先生はそれまで受験に特化し難関大学合格者を多数輩出することを目標に努力してきたのが、この震災をきっかけに、ルールに縛られ緊急時に柔軟な対応ができない行政や政府の無力さを痛感し、受験のための知識なんていざという時には何の役にも立たないと気づいたそうです。それ以降、先生は指導方針を大きく変え、本当に困った時に自分でそれを乗り越えて強く生きていくことができる能力を生徒につけさせることを目標にするようになり、最終的に今のスタイルに辿り着いたという話を初めて私たちにしました。自分は、震災当時小学校2年生で、県内で起きていた現実をあまり明確に認識できていなかったので、先生の話はとてもショックで涙が止まりませんでした。そして、これは私が将来行政で働いて、行政をもっと良くしたいと思う一つの理由にもなりました。
先生は、ただの生物教員ではなく、福島をもっと良くするために、生徒と地域や企業、大学との連携や、県内進学校同士の連携、さまざまなプロジェクトやセミナーなどの企画を立ち上げ実行していて、ある記事にはその型破りな行動力から「暴走特急」と呼ばれていると書いてありました。先生が、こうやって自分がやりたいことを勝手にやっていたら絶対に批判したり、文句を言ってくるやつもいるけど、そいつらを黙らせるにはまずは結果を出すしかない、と言っていたのも非常に印象に残っています。最初は文句を言ってきた人たちも、先生が生物の指導で、多数の合格実績を上げて結果を出し続けていたら次第に何も言ってこなくなったそうです。この年になっても自分の夢を持ち続けて、そのために行動して結果も出して周りに認めさせている、というのがかっこよくて痺れました。
先生が好きすぎて、バレンタインには手作りのお菓子を渡したし、先生が他の学校に異動になった時は、手紙も書きました。この話をしたら某後輩にパパ活などと言われましたが、私が貢いでる側なのでどちらかというと推し活です。先生の生き方はぶっ飛びすぎてなかなか真似できるものではないですが、いつか先生と一緒に福島のために仕事をすることを目標にして、それまでに私もかっこいい魅力的な大人になれるように頑張りたいと思います。
次は、1年生スタッフの琴音ちゃんにバトンを渡します。新歓でも何回かご飯に行かせてもらいましたが、同期女子スタッフがいない中で、ラグビー部を選んでくれてありがとう。愛嬌溢れるかわいらしい見た目に反して1年生とは思えないほど度胸があり肝が据わっている逸材です。期待の新星琴音ちゃんがどんなリレー日記を書くのか、楽しみでなりません。
ついに9月に突入し、対抗戦も2戦が終わりました。このシーズンで結果を出すために過ごしてきた4年間を証明できるように責任と覚悟を持って、自分にできることを出し切りたいと思います。
突然ですが、高校時代大好きだった生物の先生の話をしたいと思います。若いイケメンの先生のリアコだったとかではなく、45歳くらいの小太りのおじさんです。私は文系だったのでその先生と実際に関わったのは1年間だけでしたが、たった一年でその先生は私の人生にとても大きなインパクトを残してきました。
その先生は、教科書も参考書も一切使わず、事前に公開している自分の授業の録画映像と手作りのレジュメ的なものをみてわからないことを授業中に質問しろ、というとても特殊な授業スタイルをとっていました。どの質問に対しても、先生はただ知識を回答するのではなく、なんでそうなると思う?と生徒に考えさせて、生物基礎にしては深すぎる本質的な話をしました。また、授業時間の半分くらいは大体先生の雑談で、自分の人生の挫折や教訓、自分が今までに教えてきた生徒たちの面白い話を無限にしていました。丸々1時間、先生の雑談だけで授業が終わった時も何回かありました。先生の話が上手だったこともありますが、先生が見てきた生徒一人一人の人間ドラマがめちゃくちゃ面白く、私は毎回ずっと雑談してくれないかなあと思っていました。あまりに受験対策向けではないので、当然中には反発し、勝手に自習している生徒もいましたが、私には先生の常識にとらわれない自由な感じが刺さりました。授業時間に間に合わないのが日常茶飯事で、帰るのがめんどくさいからと理科室にベッドを持ち込み、そこで寝泊まりしながら毎日カップ麺を食べて生活するなど、ぶっ飛んでいてめちゃくちゃ適当な感じなのに、生物の知識は誰よりも深く、過去に文部科学大臣優秀教員の表彰も受けるほど能力は高いというのも、カリスマ性が高くてかっこよかったです。私は生物の授業で先生と話したいがために、席替えでわざわざ教卓の正面の席を希望し、授業中は毎回先生の真ん前で、終始先生を凝視して話を聞いている、自他ともに認めるガチファンでした。
1年の最後の生物の授業の時に、先生は東日本大震災のドキュメンタリーを教室で流してみんなで鑑賞した後に、自分が当時経験したことを話しました。先生が勤めていた学校は避難所になり、避難者が増えすぎて食料や衣類などの物品が不足したため、隣の地域から物品を分けてもらおうとしたらそこは行政の管轄が違うから、と断られたこと。消息不明の家族を探して訪れた人に、それは個人情報だからと言って避難者の名簿を見せることが禁じられたこと。避難してきた原子力発電所の職員に「まだ世の中には報道されていないが近いうちに1号機以外の原発も爆発すると言われているから、先生たちだけでも私たちを置いて逃げてくれ。ここまで私たちのために避難所を運営してくれてありがとう。」と告げられたこと。先生はそれまで受験に特化し難関大学合格者を多数輩出することを目標に努力してきたのが、この震災をきっかけに、ルールに縛られ緊急時に柔軟な対応ができない行政や政府の無力さを痛感し、受験のための知識なんていざという時には何の役にも立たないと気づいたそうです。それ以降、先生は指導方針を大きく変え、本当に困った時に自分でそれを乗り越えて強く生きていくことができる能力を生徒につけさせることを目標にするようになり、最終的に今のスタイルに辿り着いたという話を初めて私たちにしました。自分は、震災当時小学校2年生で、県内で起きていた現実をあまり明確に認識できていなかったので、先生の話はとてもショックで涙が止まりませんでした。そして、これは私が将来行政で働いて、行政をもっと良くしたいと思う一つの理由にもなりました。
先生は、ただの生物教員ではなく、福島をもっと良くするために、生徒と地域や企業、大学との連携や、県内進学校同士の連携、さまざまなプロジェクトやセミナーなどの企画を立ち上げ実行していて、ある記事にはその型破りな行動力から「暴走特急」と呼ばれていると書いてありました。先生が、こうやって自分がやりたいことを勝手にやっていたら絶対に批判したり、文句を言ってくるやつもいるけど、そいつらを黙らせるにはまずは結果を出すしかない、と言っていたのも非常に印象に残っています。最初は文句を言ってきた人たちも、先生が生物の指導で、多数の合格実績を上げて結果を出し続けていたら次第に何も言ってこなくなったそうです。この年になっても自分の夢を持ち続けて、そのために行動して結果も出して周りに認めさせている、というのがかっこよくて痺れました。
先生が好きすぎて、バレンタインには手作りのお菓子を渡したし、先生が他の学校に異動になった時は、手紙も書きました。この話をしたら某後輩にパパ活などと言われましたが、私が貢いでる側なのでどちらかというと推し活です。先生の生き方はぶっ飛びすぎてなかなか真似できるものではないですが、いつか先生と一緒に福島のために仕事をすることを目標にして、それまでに私もかっこいい魅力的な大人になれるように頑張りたいと思います。
次は、1年生スタッフの琴音ちゃんにバトンを渡します。新歓でも何回かご飯に行かせてもらいましたが、同期女子スタッフがいない中で、ラグビー部を選んでくれてありがとう。愛嬌溢れるかわいらしい見た目に反して1年生とは思えないほど度胸があり肝が据わっている逸材です。期待の新星琴音ちゃんがどんなリレー日記を書くのか、楽しみでなりません。
クソガキ[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2024/02/28(水) 13:03
同期の小野からバトンを受け取りました、新4年スタッフの佐々木です。小野とは同じ法学部ですが、授業で顔を合わせたことは数えるほどしかなく、時々課題だけラインで聞いてくるのはどうにかしてほしいです。1年生の頃から怪我が多く心配していましたが、最近はウエイトや食事にも非常に熱心なようでその不屈の精神が報われることを信じています。4年が先頭になって一緒に引っ張っていきましょう。
ついに自分が4年生になってしまいました。リレー日記を書くのもこれを含めてあと3回しかありません。毎年思ってきたことですが、自分が引退間近に書くラストリレー日記で「目標は叶わなかったけれどなんだかんだ頑張ったので良かった」的なことは絶対に書きたくないので、ラスト一年やれるだけのことをやり切って結果に繋げていきたいと思います。
小学校、中学校、高校、大学の中で、あなたが一番楽しかったのはいつですか?と聞かれたら、あなたはどれを選ぶだろうか。私は、小さい頃に母にこの質問をして、「大学が一番自由で楽しかった。」と聞いて以来、大学はどれだけ面白いところなんだろうとずっと楽しみにしていたし、実際に高校生、大学生になると、生活の変化と共に、世界も大きく広がった。しかし、今ここで振り返ってみると、一番印象に残っているのは意外と小学校の時の記憶である気がする。私が大好きだったドラマ「ブラッシュアップライフ」のように人生をやり直すとしたら、ぜひ今のままの自分で小学生に戻ってみたい。学校自体も楽しかったけれど、放課後や土日に家の周りで遊んでいた記憶が今でもとても印象深いので、当時何がそんなに面白かったのかを思い出してみた。
学校や習い事以外の時間は、基本的に弟と徒歩10秒くらいのところに住んでいた近所のお友達S君と3人で外で遊ぶことが多かった。家の近くには幼稚園や、父の実家の寺と山の上の墓地、遊歩道、神社などがあり遊び場には事欠かなかった。
うちの裏庭、というか幼稚園の裏庭(うちと幼稚園はほぼ隣接していた)には昔からそこそこ大きな池があり、そこにはメダカや金魚、アメンボ、ゲンゴロウ、タガメ、ミズカマキリなどの多種多様な生き物が生息し、春には毎年ヒキガエルが産卵のためにやってきていた。池の周りにしゃがみ込んで生き物を観察したり、網で捕まえて水槽で飼育したり、夜寝るときにはカエルの大合唱が聞こえてきたり、とたくさんの思い出がある。冬になると水面が凍るため、ここ歩けるんだよーと呼んだら、慣れない友達が氷の薄いところを踏んで池に落ちたのも懐かしい記憶だ。ただ、震災後は除染のために池は埋め立てられてしまい、翌春カエルたちがただの土になってしまった跡地に産卵のために戻ってきてしまった時はとても悲しい気持ちになった。
夏になるとそこら中にある蝉の抜け殻を探して一箇所に隠し集める、という謎の遊びをしていた。おそらく数百個は集まっていたと思う。何に使うわけでもなく、ただただ集めるだけだったが、なぜか強烈に印象に残っている。また夏休み恒例の自由研究では、毎回生き物をテーマにしていたので、カマキリを飼育して餌の虫をとりに行ったり、カブトムシやクワガタ、アリ、カタツムリ、アリジゴク、などたくさんの生き物を探しに行っては捕まえて飼育した。アリジゴクは実際に見たことがある人はあまり多くないかもしれないが、近所の神社やお寺の境内下で意外と簡単に見つけられた感動は今でも覚えている。
家の裏には山の上に作られた大きな墓地があったので暇さえあればお墓探検に繰り出していた。高低差が激しく、竹藪や木が茂っているお墓の中で鬼ごっこやかくれんぼをしたり、今思えば不謹慎すぎるが、形の気に入ったお墓を自分たちの溜まり場にしたりしていた。一から自分たちで大きな秘密基地を作るという壮大な夢もあったが、震災後にはあまりお墓にも入れなくなり結局実現しなかった、非常に残念。春にはお墓の中にある大きな桜の木を眺めたり、つくしやふきのとうを集めたり、竹藪から生えてきた筍を掘って収穫したりしたこともあった。たくさん採りすぎてしばらくは延々と筍のメニューが食卓に並んでいた気がする。
幼稚園生がいない土日には、家の裏にある幼稚園の園庭を自分の家の庭のように使っていた。野球やドッジボール、ドッジビー、サッカーなどなんでもできた。明らかに自分たちの体のサイズに合っていないブランコやグルグルを高速回転させたり、弟は砂場に落とし穴を作って友達を落としたりもしていた。
冬には、屋根から伸びているたくさんのつららに雪玉を当てて落とすのが面白かった。お墓の階段を雪で固めてそり滑りとかもやった気がする。一番印象的なのは、小学校中学年くらいの頃に数十年ぶりの大雪が降って学校が休校になった日。近所の子供達と一緒に大きな雪の城のようなものを作った。雪で階段や防御壁を作って潜伏し、道を通るお父さんとかおじさんとか大人に雪を投げたりしたのは最高だった。
家の周りを移動するときには基本自転車を使っており、3人連なってものすごいスピードで駆け抜けていたので近所の人にはチャリンコ暴走族と言われていたらしい。あまり記憶にないが母によると、正面のお家の庭の地面に刺さっているガーデンライトを勝手に引き抜いて回ってその主人のおじさんに怒られたりもしていたらしい。当時は全く罪の意識もなかったのが不思議だ。
今思うとただのクソガキな気がするけれど、当時は本当に面白かった。あの頃にしかできない贅沢な時間の無駄遣いをしていたと思う。一般的に幼稚園、小学生の時期は人格形成の基盤になると言われている通り、いわばあの時期が今の私を作ったとも言える私のルーツだ。私はあの時期を地元で過ごせて本当に良かったと思っているし、あまりに面白かったので、自分の子供も同じように田舎で育てたいと強く思っている。東大生には都会育ちや、小さい頃から塾に通っていたエリートがおそらく多いだろうし、あまり共感されないかもしれないけれど、個人的には子育てには田舎が最高だ、という説を唱えたい。
次は新2年期待のフロントロー大野にバトンを繋ぎます。大野は度々光るプレーを見せてくれますが、あとはお母様に負けないパワーと気持ちの強さが発揮されるのを心待ちにしています。先日私の弟と一緒に遊びに行くという謎イベントがあったようですが、今度は私も参戦させてください。
ついに自分が4年生になってしまいました。リレー日記を書くのもこれを含めてあと3回しかありません。毎年思ってきたことですが、自分が引退間近に書くラストリレー日記で「目標は叶わなかったけれどなんだかんだ頑張ったので良かった」的なことは絶対に書きたくないので、ラスト一年やれるだけのことをやり切って結果に繋げていきたいと思います。
小学校、中学校、高校、大学の中で、あなたが一番楽しかったのはいつですか?と聞かれたら、あなたはどれを選ぶだろうか。私は、小さい頃に母にこの質問をして、「大学が一番自由で楽しかった。」と聞いて以来、大学はどれだけ面白いところなんだろうとずっと楽しみにしていたし、実際に高校生、大学生になると、生活の変化と共に、世界も大きく広がった。しかし、今ここで振り返ってみると、一番印象に残っているのは意外と小学校の時の記憶である気がする。私が大好きだったドラマ「ブラッシュアップライフ」のように人生をやり直すとしたら、ぜひ今のままの自分で小学生に戻ってみたい。学校自体も楽しかったけれど、放課後や土日に家の周りで遊んでいた記憶が今でもとても印象深いので、当時何がそんなに面白かったのかを思い出してみた。
学校や習い事以外の時間は、基本的に弟と徒歩10秒くらいのところに住んでいた近所のお友達S君と3人で外で遊ぶことが多かった。家の近くには幼稚園や、父の実家の寺と山の上の墓地、遊歩道、神社などがあり遊び場には事欠かなかった。
うちの裏庭、というか幼稚園の裏庭(うちと幼稚園はほぼ隣接していた)には昔からそこそこ大きな池があり、そこにはメダカや金魚、アメンボ、ゲンゴロウ、タガメ、ミズカマキリなどの多種多様な生き物が生息し、春には毎年ヒキガエルが産卵のためにやってきていた。池の周りにしゃがみ込んで生き物を観察したり、網で捕まえて水槽で飼育したり、夜寝るときにはカエルの大合唱が聞こえてきたり、とたくさんの思い出がある。冬になると水面が凍るため、ここ歩けるんだよーと呼んだら、慣れない友達が氷の薄いところを踏んで池に落ちたのも懐かしい記憶だ。ただ、震災後は除染のために池は埋め立てられてしまい、翌春カエルたちがただの土になってしまった跡地に産卵のために戻ってきてしまった時はとても悲しい気持ちになった。
夏になるとそこら中にある蝉の抜け殻を探して一箇所に隠し集める、という謎の遊びをしていた。おそらく数百個は集まっていたと思う。何に使うわけでもなく、ただただ集めるだけだったが、なぜか強烈に印象に残っている。また夏休み恒例の自由研究では、毎回生き物をテーマにしていたので、カマキリを飼育して餌の虫をとりに行ったり、カブトムシやクワガタ、アリ、カタツムリ、アリジゴク、などたくさんの生き物を探しに行っては捕まえて飼育した。アリジゴクは実際に見たことがある人はあまり多くないかもしれないが、近所の神社やお寺の境内下で意外と簡単に見つけられた感動は今でも覚えている。
家の裏には山の上に作られた大きな墓地があったので暇さえあればお墓探検に繰り出していた。高低差が激しく、竹藪や木が茂っているお墓の中で鬼ごっこやかくれんぼをしたり、今思えば不謹慎すぎるが、形の気に入ったお墓を自分たちの溜まり場にしたりしていた。一から自分たちで大きな秘密基地を作るという壮大な夢もあったが、震災後にはあまりお墓にも入れなくなり結局実現しなかった、非常に残念。春にはお墓の中にある大きな桜の木を眺めたり、つくしやふきのとうを集めたり、竹藪から生えてきた筍を掘って収穫したりしたこともあった。たくさん採りすぎてしばらくは延々と筍のメニューが食卓に並んでいた気がする。
幼稚園生がいない土日には、家の裏にある幼稚園の園庭を自分の家の庭のように使っていた。野球やドッジボール、ドッジビー、サッカーなどなんでもできた。明らかに自分たちの体のサイズに合っていないブランコやグルグルを高速回転させたり、弟は砂場に落とし穴を作って友達を落としたりもしていた。
冬には、屋根から伸びているたくさんのつららに雪玉を当てて落とすのが面白かった。お墓の階段を雪で固めてそり滑りとかもやった気がする。一番印象的なのは、小学校中学年くらいの頃に数十年ぶりの大雪が降って学校が休校になった日。近所の子供達と一緒に大きな雪の城のようなものを作った。雪で階段や防御壁を作って潜伏し、道を通るお父さんとかおじさんとか大人に雪を投げたりしたのは最高だった。
家の周りを移動するときには基本自転車を使っており、3人連なってものすごいスピードで駆け抜けていたので近所の人にはチャリンコ暴走族と言われていたらしい。あまり記憶にないが母によると、正面のお家の庭の地面に刺さっているガーデンライトを勝手に引き抜いて回ってその主人のおじさんに怒られたりもしていたらしい。当時は全く罪の意識もなかったのが不思議だ。
今思うとただのクソガキな気がするけれど、当時は本当に面白かった。あの頃にしかできない贅沢な時間の無駄遣いをしていたと思う。一般的に幼稚園、小学生の時期は人格形成の基盤になると言われている通り、いわばあの時期が今の私を作ったとも言える私のルーツだ。私はあの時期を地元で過ごせて本当に良かったと思っているし、あまりに面白かったので、自分の子供も同じように田舎で育てたいと強く思っている。東大生には都会育ちや、小さい頃から塾に通っていたエリートがおそらく多いだろうし、あまり共感されないかもしれないけれど、個人的には子育てには田舎が最高だ、という説を唱えたい。
次は新2年期待のフロントロー大野にバトンを繋ぎます。大野は度々光るプレーを見せてくれますが、あとはお母様に負けないパワーと気持ちの強さが発揮されるのを心待ちにしています。先日私の弟と一緒に遊びに行くという謎イベントがあったようですが、今度は私も参戦させてください。
指針[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2023/09/05(火) 09:42
2年生のはるとからバトンを受け取りました、3年スタッフの佐々木です。はるとは私の下クラで、去年の春には新歓飯に行きすぎて話すことがなくなったと言われるくらい猛アタックをかけさせていただきました。陸上出身の非凡な身体能力やセンスはさすがですが、その代わりに社会生活に必要な能力は少々飛んでいってしまったのかもしれませんね。手料理の約束をした記憶は全くありませんが、対抗戦全試合トライくらいしてくれたら考えてもいいかなと思います。
先日同期と話していた際に、りんはワンオクのビジュアルが好きなの?音楽が好きなの?という非常に屈辱的な質問をされたので、今回は私の好きなONE OK ROCKというバンドについて書きたいと思います。
最初は、私が中学生の頃に、弟にワンオクの曲をいくつか薦められて聴いてみたのがきっかけでした。彼らが海外のバンドなのか日本のバンドなのかさえ知らない状態で曲を聴いて、かっこいいと思ってYouTubeで彼らのライブの映像を見ました。そのライブでの圧倒的な歌唱力とパフォーマンスに「生演奏でこんなうまい人たちいるんだ。」と衝撃を受けて、それ以来このバンドに興味を持つようになりました。
彼らの作った曲を聴き込み、彼らの配信やラジオなどの情報を見聞きし、ライブ映像を見たり、実際にライブ会場に足を運んでみたりするうちに、私は彼らの音楽、ライブパフォーマンスだけではなく、ONE OK ROCKというバンドの生き方自体が最高にかっこよくて好きだな、と思うようになりました。
私は1年生の頃からHPのプロフィールの「尊敬する人」という欄にTakaの名前を書いています。このバンドを率いる彼の人間性や魅力はここでは語り尽くせませんが、私が彼の最も尊敬している部分は、どれだけ有名になってもブレない芯の強さ、常に変化を恐れず挑戦する行動力です。
ONE OK ROCKというバンドはこういうTakaの生き方を反映していて、ライブ会場でのファンとの直接の交流を一番大事にしているから、とどれだけ売れてもテレビには出演せず、世界的にロックミュージックを復活させる、という目標のために、毎年世界中の小さなライブハウスをバスに宿泊しながら連日回るというタフなツアーを敢行しています。日本にいれば簡単に何万人規模のドームツアーを埋められるのに、あえてしんどい道を選ぶ、30代になっても決して夢をあきらめない青さが、見ていて清々しいし、世の中に迎合していなくてロックだなあと思います。
彼らが19歳の時に作ったデビューアルバムの中の「努努-ゆめゆめ-」という曲には、「ついて来い、世界に行こうぜ」という歌詞があります。今、同年代の私から見ても恥ずかしくなるような青くて痛い歌詞が並んでいますが、なんの実績もない当時からこんな大きなことを言えるのもすごいし、いまだに同じ夢を追って、しかも確実にそこに近づいている、というのがマジでかっこいいです。いくら自分たちの地位が上がっても、自分の中のブレない軸があるからこそ、こういう生き方ができるんだろうな、と思います。すごく元気をもらえる曲なので興味があったら一度聞いてみてください。
Takaの人脈の広さと行動力も影響し、Taka個人、そしてワンオクはたくさんのアーティストとコラボしています。国内のみならずエド・シーランやアヴリル・ラヴィーンのような大物海外アーティストとも交流が深く、コロナ禍ではTakaが清水翔太と共に絢香、KENTA(WANIMA)、Nissy(西島隆弘)ら当初はほとんど交流がなかったアーティストにも声をかけて共同で曲を制作し、それをきっかけに各々のアーティスト同士の新たなコラボレーションが多数生まれました。また、昨年TakaがOfficial髭男dismの藤原聡とラジオで共演し、その半年後にはワンオクの新アルバムの曲に藤原が参加、という記事が出たのをみて、いつもながらその行動力とスピード感はさすがだなあと思いました。人との出会いを大切にしていて、迷わず自分から相手に一歩踏み込む行動力があるからこそ、人間性、そしてワンオクのバンドとしての幅が広がっていくのだと思います。
ワンオクは音楽自体の面でも非常に挑戦的で、常に変化し続けています。昔の曲を聴いたことがある人なら分かると思いますが、アルバムを出すたびに音や曲調のテイストが大きく変わります。中には昔の曲の方が好きだった、ワンオクはロックを捨ててしまった、という声もありましたが、これは彼ら曰く、あくまでロックの復活という最終ゴールに向かう途中に、その時その時で作るべき必要な音楽を模索し続けている結果なのだそうです。
きっと彼らも変化をする怖さを感じていないわけではないと思います。やはり批判の声は嫌でも耳に入ってくるし、気にならないわけではない、とTaka本人も言っていました。それでもワンオクのメンバーがドキュメンタリー映像か何かで言っていた「ONE OK ROCKにとって現状維持は衰退と同じなんです。」という言葉が私には深く刺さりました。現状維持は停滞ではなく、衰退、つまり変化を恐れて何も新しいことをしなければ前に進むどころかどんどん弱って力を失っていく、ということなのだと思います。
熱量有り余りオタク感満載の文章を書いてしまいましたが、私にとってワンオクというバンドの生き方は人生の指針であり、日頃の生活にもたくさんの影響を受けています。3年生になり、自分のことだけでなくチームのことを考える時間が格段に増えました。このチームには何が必要で自分には何ができるのか、何を残し、何を変えるべきなのか。簡単に答えを出せることではありませんが、やらぬ後悔よりやる後悔だと思っているので、保身に走らず常に最善を求めて模索し続ける、ワンオクのように芯をブラさず変化を恐れず進んでいきたいと思います。
次は態度も体も大型新人の筑波にバトンを繋ぎます。未経験者でありながら、体の強さや当たりの強さを他の選手が褒めているのを聞くので、早く実戦で活躍する姿を見たいです。しかし、新歓時に感じた真面目さはどこへやら、メンタルの強さはあっぱれですが、反省顔の技術ではなく早起きの習慣を身につけて欲しいので、私からは目覚まし時計を100個くらいプレゼントしようかなと思っています。
先日同期と話していた際に、りんはワンオクのビジュアルが好きなの?音楽が好きなの?という非常に屈辱的な質問をされたので、今回は私の好きなONE OK ROCKというバンドについて書きたいと思います。
最初は、私が中学生の頃に、弟にワンオクの曲をいくつか薦められて聴いてみたのがきっかけでした。彼らが海外のバンドなのか日本のバンドなのかさえ知らない状態で曲を聴いて、かっこいいと思ってYouTubeで彼らのライブの映像を見ました。そのライブでの圧倒的な歌唱力とパフォーマンスに「生演奏でこんなうまい人たちいるんだ。」と衝撃を受けて、それ以来このバンドに興味を持つようになりました。
彼らの作った曲を聴き込み、彼らの配信やラジオなどの情報を見聞きし、ライブ映像を見たり、実際にライブ会場に足を運んでみたりするうちに、私は彼らの音楽、ライブパフォーマンスだけではなく、ONE OK ROCKというバンドの生き方自体が最高にかっこよくて好きだな、と思うようになりました。
私は1年生の頃からHPのプロフィールの「尊敬する人」という欄にTakaの名前を書いています。このバンドを率いる彼の人間性や魅力はここでは語り尽くせませんが、私が彼の最も尊敬している部分は、どれだけ有名になってもブレない芯の強さ、常に変化を恐れず挑戦する行動力です。
ONE OK ROCKというバンドはこういうTakaの生き方を反映していて、ライブ会場でのファンとの直接の交流を一番大事にしているから、とどれだけ売れてもテレビには出演せず、世界的にロックミュージックを復活させる、という目標のために、毎年世界中の小さなライブハウスをバスに宿泊しながら連日回るというタフなツアーを敢行しています。日本にいれば簡単に何万人規模のドームツアーを埋められるのに、あえてしんどい道を選ぶ、30代になっても決して夢をあきらめない青さが、見ていて清々しいし、世の中に迎合していなくてロックだなあと思います。
彼らが19歳の時に作ったデビューアルバムの中の「努努-ゆめゆめ-」という曲には、「ついて来い、世界に行こうぜ」という歌詞があります。今、同年代の私から見ても恥ずかしくなるような青くて痛い歌詞が並んでいますが、なんの実績もない当時からこんな大きなことを言えるのもすごいし、いまだに同じ夢を追って、しかも確実にそこに近づいている、というのがマジでかっこいいです。いくら自分たちの地位が上がっても、自分の中のブレない軸があるからこそ、こういう生き方ができるんだろうな、と思います。すごく元気をもらえる曲なので興味があったら一度聞いてみてください。
Takaの人脈の広さと行動力も影響し、Taka個人、そしてワンオクはたくさんのアーティストとコラボしています。国内のみならずエド・シーランやアヴリル・ラヴィーンのような大物海外アーティストとも交流が深く、コロナ禍ではTakaが清水翔太と共に絢香、KENTA(WANIMA)、Nissy(西島隆弘)ら当初はほとんど交流がなかったアーティストにも声をかけて共同で曲を制作し、それをきっかけに各々のアーティスト同士の新たなコラボレーションが多数生まれました。また、昨年TakaがOfficial髭男dismの藤原聡とラジオで共演し、その半年後にはワンオクの新アルバムの曲に藤原が参加、という記事が出たのをみて、いつもながらその行動力とスピード感はさすがだなあと思いました。人との出会いを大切にしていて、迷わず自分から相手に一歩踏み込む行動力があるからこそ、人間性、そしてワンオクのバンドとしての幅が広がっていくのだと思います。
ワンオクは音楽自体の面でも非常に挑戦的で、常に変化し続けています。昔の曲を聴いたことがある人なら分かると思いますが、アルバムを出すたびに音や曲調のテイストが大きく変わります。中には昔の曲の方が好きだった、ワンオクはロックを捨ててしまった、という声もありましたが、これは彼ら曰く、あくまでロックの復活という最終ゴールに向かう途中に、その時その時で作るべき必要な音楽を模索し続けている結果なのだそうです。
きっと彼らも変化をする怖さを感じていないわけではないと思います。やはり批判の声は嫌でも耳に入ってくるし、気にならないわけではない、とTaka本人も言っていました。それでもワンオクのメンバーがドキュメンタリー映像か何かで言っていた「ONE OK ROCKにとって現状維持は衰退と同じなんです。」という言葉が私には深く刺さりました。現状維持は停滞ではなく、衰退、つまり変化を恐れて何も新しいことをしなければ前に進むどころかどんどん弱って力を失っていく、ということなのだと思います。
熱量有り余りオタク感満載の文章を書いてしまいましたが、私にとってワンオクというバンドの生き方は人生の指針であり、日頃の生活にもたくさんの影響を受けています。3年生になり、自分のことだけでなくチームのことを考える時間が格段に増えました。このチームには何が必要で自分には何ができるのか、何を残し、何を変えるべきなのか。簡単に答えを出せることではありませんが、やらぬ後悔よりやる後悔だと思っているので、保身に走らず常に最善を求めて模索し続ける、ワンオクのように芯をブラさず変化を恐れず進んでいきたいと思います。
次は態度も体も大型新人の筑波にバトンを繋ぎます。未経験者でありながら、体の強さや当たりの強さを他の選手が褒めているのを聞くので、早く実戦で活躍する姿を見たいです。しかし、新歓時に感じた真面目さはどこへやら、メンタルの強さはあっぱれですが、反省顔の技術ではなく早起きの習慣を身につけて欲しいので、私からは目覚まし時計を100個くらいプレゼントしようかなと思っています。
母親[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2023/06/09(金) 10:50
2年生の福元からバトンを受け取りました、3年スタッフの佐々木です。福元はスタッフともよく話すコミュ力の高い男ですが、部内きっての大スピーカーなのでうっかり余計なことを話しすぎないように気をつけなければなりません。以下の通り最近の私は家事と授業に忙殺されて余暇など楽しむ余裕もないのですが、たまには息抜きでお菓子作りや野球観戦とかしたいなあと夢見ています。
個人的な話ですが、4月から弟が上京してきたので、現在二人暮らしをしています。新しい家は以前より圧倒的に広く、開放感があるので気に入っています。何より二年間一人暮らしだったので、家に誰かがいるというのが新鮮ですが、どうでもいい話をする相手がいるのは楽しいです。
家事は私がご飯、弟が洗濯や食器洗いを担当しているので、4月から毎日の食事を考えて準備しなければいけなくなりました。去年までは私一人の食事なんて大した量でもないので適当に済ませることができましたが、弟は大学でラグビーをしているため、量や栄養バランスを考えた食事を作らなければならず、当然負担も去年より倍増しました。料理は嫌いではないので特別苦ではないのですが、常に次の食事を何にするかが頭から離れず、いかに効率的に合間の時間で料理を終えるかを考えていると、もはや学生というより主婦になったような気持ちになります。どの品物がどこのスーパーだとどれくらい安いかもほぼ頭に入っているし、趣味は新しいスーパーを開拓することと、クックパッド、クラシル、Nadia、キッコーマン等あらゆるレシピサイトを見漁ることです。実際ご飯を作っていて授業に間に合わないという事態も発生しており、もはやどちらが本職か分からなくなってきました。
手間を省くために大量生産していると、何回か同じ食事が続いてだんだん飽きてきます。そこで私がやってみて美味しかったおすすめのリメイクレシピをご紹介しようと思います。一人暮らしの人は大量消費に飽きたらやってみてください。
①余った餃子の皮→ラザニア
餃子の皮と、ミートソース、クリームソース、玉ねぎとジャガイモを重ねて焼くだけ。ソースは市販のものを使えば簡単です。
②余った棒棒鶏→冷やし中華
棒棒鶏を見ていたらこれほぼ冷やし中華じゃね、と発想。卵を焼いて、中華麺だけ用意すればちょっと豪華な冷やし中華になります。棒棒鶏用のゴマだれをかけると美味しい。
③余った小松菜のお浸し→肉そば
小松菜と油揚げのお浸し(汁多め)が残っていたので、豚バラ肉と麺つゆを足したら簡単に肉そばの汁に。出汁も出ていてお蕎麦やうどんと相性抜群です。
④余ったラタトゥイユ→冷製パスタ
レシピでもなんでもないですが、パスタを茹でて氷でしめ、冷やしたラタトゥイユをかければ完成。味が薄まるので塩胡椒をするといいかもしれません。
改めて家族全員分の料理、洗濯、掃除全てを一人でこなしている母親の凄さを実感しています。普通に化け物だと思います。弟はこの程度の家事で「頭がいっぱいで疲れるから実家に帰りたい。」などどほざいているのでぶん殴りたくなりますが、協力して頑張ります。
次は3 年生になって以前よりいくらかバブみが薄れてきた桑田昴にバトンを渡します。ほんとは賢いくせにあほで可愛いキャラを獲得しているあざとさがちょっと気に食わないですが、昴の素直さにはいつも救われています。昴は農学部なので私がつまらない民法の話を聞いている裏で、森林に出かけて植物を植えたり虫を観察したり、楽しそうで心底羨ましいです。長いリハビリが終わりようやく本領発揮だと思うので、3年生、そしてチームを引っ張る活躍を期待しています。
個人的な話ですが、4月から弟が上京してきたので、現在二人暮らしをしています。新しい家は以前より圧倒的に広く、開放感があるので気に入っています。何より二年間一人暮らしだったので、家に誰かがいるというのが新鮮ですが、どうでもいい話をする相手がいるのは楽しいです。
家事は私がご飯、弟が洗濯や食器洗いを担当しているので、4月から毎日の食事を考えて準備しなければいけなくなりました。去年までは私一人の食事なんて大した量でもないので適当に済ませることができましたが、弟は大学でラグビーをしているため、量や栄養バランスを考えた食事を作らなければならず、当然負担も去年より倍増しました。料理は嫌いではないので特別苦ではないのですが、常に次の食事を何にするかが頭から離れず、いかに効率的に合間の時間で料理を終えるかを考えていると、もはや学生というより主婦になったような気持ちになります。どの品物がどこのスーパーだとどれくらい安いかもほぼ頭に入っているし、趣味は新しいスーパーを開拓することと、クックパッド、クラシル、Nadia、キッコーマン等あらゆるレシピサイトを見漁ることです。実際ご飯を作っていて授業に間に合わないという事態も発生しており、もはやどちらが本職か分からなくなってきました。
手間を省くために大量生産していると、何回か同じ食事が続いてだんだん飽きてきます。そこで私がやってみて美味しかったおすすめのリメイクレシピをご紹介しようと思います。一人暮らしの人は大量消費に飽きたらやってみてください。
①余った餃子の皮→ラザニア
餃子の皮と、ミートソース、クリームソース、玉ねぎとジャガイモを重ねて焼くだけ。ソースは市販のものを使えば簡単です。
②余った棒棒鶏→冷やし中華
棒棒鶏を見ていたらこれほぼ冷やし中華じゃね、と発想。卵を焼いて、中華麺だけ用意すればちょっと豪華な冷やし中華になります。棒棒鶏用のゴマだれをかけると美味しい。
③余った小松菜のお浸し→肉そば
小松菜と油揚げのお浸し(汁多め)が残っていたので、豚バラ肉と麺つゆを足したら簡単に肉そばの汁に。出汁も出ていてお蕎麦やうどんと相性抜群です。
④余ったラタトゥイユ→冷製パスタ
レシピでもなんでもないですが、パスタを茹でて氷でしめ、冷やしたラタトゥイユをかければ完成。味が薄まるので塩胡椒をするといいかもしれません。
改めて家族全員分の料理、洗濯、掃除全てを一人でこなしている母親の凄さを実感しています。普通に化け物だと思います。弟はこの程度の家事で「頭がいっぱいで疲れるから実家に帰りたい。」などどほざいているのでぶん殴りたくなりますが、協力して頑張ります。
次は3 年生になって以前よりいくらかバブみが薄れてきた桑田昴にバトンを渡します。ほんとは賢いくせにあほで可愛いキャラを獲得しているあざとさがちょっと気に食わないですが、昴の素直さにはいつも救われています。昴は農学部なので私がつまらない民法の話を聞いている裏で、森林に出かけて植物を植えたり虫を観察したり、楽しそうで心底羨ましいです。長いリハビリが終わりようやく本領発揮だと思うので、3年生、そしてチームを引っ張る活躍を期待しています。
| 次へ>> |
2025年11月
| <<前月 | 翌月>> |
| |
| |
| |
| |
| |
アーカイブ
- 2025年11月(5)
- 2025年10月(13)
- 2025年9月(11)
- 2025年8月(11)
- 2025年7月(11)
- 2025年6月(10)
- 2025年5月(8)
- 2025年4月(9)
- 2025年3月(9)
- 2025年2月(15)
- 2025年1月(2)
- 2024年12月(18)
- 2024年11月(12)
- 2024年10月(12)
- 2024年9月(13)
- 2024年8月(11)
- 2024年7月(12)
- 2024年6月(8)
- 2024年5月(9)
- 2024年4月(8)
- 2024年3月(8)
- 2024年2月(19)
- 2024年1月(7)
- 2023年12月(9)
- 2023年11月(12)
- 2023年10月(11)
- 2023年9月(12)
- 2023年8月(11)
- 2023年7月(11)
- 2023年6月(8)
- 2023年5月(7)
- 2023年4月(8)
- 2023年3月(7)
- 2023年2月(15)
- 2023年1月(7)
- 2022年12月(23)
- 2022年11月(14)
- 2022年10月(13)
- 2022年9月(14)
- 2022年8月(14)
- 2022年7月(16)
- 2022年6月(10)
- 2022年5月(11)
- 2022年4月(12)
- 2022年3月(10)
- 2022年2月(15)
- 2022年1月(4)
- 2021年12月(12)
- 2021年11月(12)
- 2021年10月(14)
- 2021年9月(12)
- 2021年8月(12)
- 2021年7月(12)
- 2021年6月(11)
- 2021年5月(12)
- 2021年4月(11)
- 2021年3月(13)
- 2021年2月(10)
- 2021年1月(21)
- 2020年12月(11)
- 2020年11月(12)
- 2020年10月(13)
- 2020年9月(12)
- 2020年8月(14)
- 2020年7月(12)
- 2020年6月(12)
- 2020年5月(13)
- 2020年4月(12)
- 2020年3月(13)
- 2020年2月(12)
- 2020年1月(4)
- 2019年12月(10)
- 2019年11月(15)
- 2019年10月(11)
- 2019年9月(13)
- 2019年8月(13)
- 2019年7月(10)
- 2019年6月(8)
- 2019年5月(13)
- 2019年4月(7)
- 2019年3月(7)
- 2019年2月(5)
- 2019年1月(7)
- 2018年12月(15)
- 2018年11月(12)
- 2018年10月(15)
- 2018年9月(10)
- 2018年8月(7)
- 2018年7月(6)
- 2018年6月(10)
- 2018年5月(12)
- 2018年4月(11)
- 2018年3月(5)
- 2017年12月(11)
- 2017年11月(13)
- 2017年10月(12)
- 2017年9月(11)
- 2017年8月(12)
- 2017年7月(10)
- 2017年6月(10)
- 2017年5月(17)
- 2017年4月(10)
- 2017年3月(13)
- 2017年2月(4)
- 2016年12月(15)
- 2016年11月(12)
- 2016年10月(14)
- 2016年9月(12)
- 2016年8月(12)
- 2016年7月(15)
- 2016年6月(9)
- 2016年5月(9)
- 2016年4月(11)
- 2016年3月(10)
- 2016年2月(7)
- 2015年12月(8)
- 2015年11月(11)
- 2015年10月(10)
- 2015年9月(10)
- 2015年8月(5)
- 2015年7月(7)
- 2015年6月(11)
- 2015年5月(13)
- 2015年4月(8)
- 2015年3月(9)
- 2015年2月(12)
- 2015年1月(11)
- 2014年12月(12)
- 2014年11月(10)
- 2014年10月(12)
- 2014年9月(12)
- 2014年8月(12)
- 2014年7月(6)
- 2014年6月(5)
- 2014年5月(13)
- 2014年4月(11)
- 2014年3月(14)
- 2014年2月(7)
- 2013年12月(23)
- 2013年11月(29)
- 2013年10月(32)
- 2013年9月(30)
- 2013年8月(14)
- 2013年7月(15)
- 2013年6月(23)
- 2013年5月(33)
- 2013年4月(27)
- 2013年3月(20)
- 2013年2月(10)
- 2013年1月(1)
- 2012年12月(13)
- 2012年11月(11)
- 2012年10月(24)
- 2012年9月(13)
- 2012年8月(9)
- 2012年7月(5)
- 2012年6月(8)
- 2012年5月(11)
- 2012年4月(9)
- 2012年3月(10)
- 2012年2月(8)
- 2011年12月(6)
- 2011年11月(6)
- 2011年10月(7)
- 2011年9月(9)
- 2011年8月(10)
- 2011年7月(5)
- 2011年6月(5)
- 2011年5月(9)
- 2011年4月(7)
- 2011年3月(8)
- 2011年2月(4)
ブログ最新記事
- 埼玉旅行記 (11/16 18:05)
- 渋谷のサグラダ・ファミリア (11/15 20:40)
- 逆ナンなん? (11/13 16:34)
- バイト (11/12 10:31)
- モチーフで見る部員の部屋 (11/07 00:32)
- 自己開示 (10/31 13:42)
- ポスト考古学実習 (10/28 21:23)
- 白球に魅せられて (10/25 18:37)
- LoveType16 (10/25 11:46)
- 休みたい (10/25 07:09)
- No pain, no gain. (10/24 12:29)
- 銀杏 (10/18 07:50)
- ラグビーマン決戦・徳島頂上バトル (10/17 19:33)
- 名古屋に行きました。 (10/17 00:13)
- 勇気のいらない親切 (10/13 16:15)
- 懐かしのDAYS (10/10 16:14)
- アレルギー (10/04 23:56)
- 炎 (10/02 23:50)
- タックル怖くね? (09/29 22:08)
- surprise! mf (09/26 22:52)





.jpg)