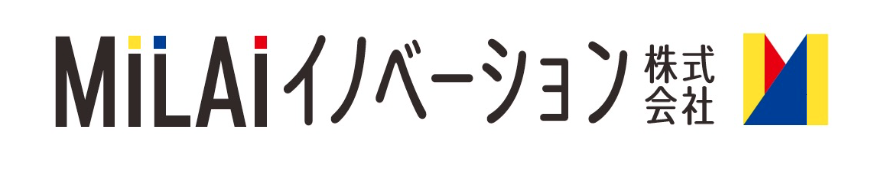ブログ
| <<前へ | 次へ>> |
I'll be back[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2018/11/09(金) 23:43
今シーズンは自分にとってかなり大きな出来事があった。それは前十字靭帯損傷からの復帰を目前とした8月に前十字靭帯の再断裂したことだ。そのことについて少し書きたいと思う。
僕は大学1年の冬に前十字靭帯損傷という怪我をした。競技復帰に手術を受けて、8ヶ月のリハビリをしていた。もとをたどれば、数年間まともにラグビーができていない。高校2年の秋の左肩脱臼にはじまり、高3の夏の左肩の再脱臼、そして大学1年の冬の前十字靭帯損傷、怪我とその手術を3度繰り返してきた。ラグビーができない歯がゆさやフラストレーションはつもりにつもっていた。
そしてついに怪我からの復帰、8月をむえた。ラグビーがやっとできるようになると期待に胸を膨らませていた。しかしその期待は一瞬でついえた。キック後の着地で右脚をついた瞬間に膝がグキッとなった。前十字靭帯の再断裂だった。ラグビーはまたも自分の手から離れていった。診断結果を突きつけられたときは今まで積み上げてきたものが無に帰したような感じがした。そして、何故またなのかと悔しくて、不甲斐なくて、そして悲しくてしかたなかった。
今回の怪我はいろんなことを考えた。特に自分はこれからどうしたらいいのかはかなり考えた。自分がプレイヤーとして続けたときのことを考えても全くいい未来は想像できないかった。こんなにもラグビーができていないの復帰しても、ラグビーをできる気がしないし、出遅れてた2年分だけ置いていかれてみんなについていけるかも不安しかない。 プレーを続けずラグビーに携わる方が自分にとっていいのではないかとも考えた。
そんなこと考えているときにチームメイトがかけてくれた何気ない言葉が自分をプレイヤーへ気持を引き戻してくれた。「復帰してくるまで待ってるよ」と「復帰向けてに一緒に頑張ろうな」などと声をかけてくれた。自分はこの言葉は本当に嬉しかった。自分の復帰を待ってくれたり、望んでくれる仲間がいるそれだけで自分もまた復帰に向けて頑張るしかないなと思えた。
次にリレー日記を書くときは怪我を乗り越えてという題で書けることを切に願い次の人にバトンを渡します。次は自分と同じ「監獄」に住んでいる1年の斎藤です。
ブレディスローカップ[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2018/11/06(火) 13:55
鍛え抜かれた四頭筋が代名詞の2年の藤井さんからバトンを受け取りました、1年の松本です。
先輩方、同期共に熱い日記を書いていますが、僕は先日会報に寄稿したので今回はゆるめに先日観戦したブレディスローカップについて書きたいと思います。
ブレディスローカップとは1931年から始まったニュージーランド対オーストラリアのテストマッチです。ニュージーランドが15年連続でカップを保持しており、今年もニュージーランドが勝利しました。今回、実家の近くの日産スタジアムで開催されると言うことで、父に入学祝いとしてお願いしチケットを買ってもらいました。
これまで日本代表やサンウルブズの試合は生で観戦したことがありましたが他国同士の試合は初めてでした。両国にとってホームでも完全なアウェイでもない日本で行われる試合はどのような感じになるのだろうと楽しみにしていましたが、実際には雰囲気的には完全にオールブラックスのホームでした。
入場するとBIG TRYと書かれた紙が配られるのですが、その裏にはI LOVE ALL BLACKS と書かれており、逆にワラビーズを応援するグッズは一切配られておりませんでした。会場内も案の定オールブラックスを応援する人ばかりでワラビーズのユニフォームを着ている人はオーストラリアからの応援団くらいでした。
本題の試合はというと、前半は互角の戦いが繰り広げられ、1トライ差で折り返しました。
後半はオールブラックスが圧倒し勝利しました。僕の好きな選手、ボーデンバレットのトライを間近で見ることができたのは本当に嬉しかったです。まさに世界レベルの試合を生で観戦できたのは貴重な経験でした。
自分も少しでも彼らに近づきたいとラグビーのモチベーションが高まった最高の1日になったとおもいます。
本当に稚拙な文章となりましたがお読みいただきありがとうございました。
次は「膝パート」の2年川端さんにバトンを回します。
こだわり[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2018/11/04(日) 20:18
東大に入ってはや2年が過ぎようとしていて、最近思っていることは、自分に強い信念のようなものがないということだ。東大生は様々なことに対して自分の意見を持ち合わせていることが多いように感じる。たとえば授業で扱われた社会問題に対してもみんなの前で発表できるような意見を持っている人が多い。それに対して自分は人の意見を聞いて「なるほど」と思っても他の人の意見を聞くと「あ、それもいいな」と思い自分の意見を持っていない。
同時に思いつく似たこととして、自分は物事にこだわりを持っていない。受験期の参考書もなんでもいいと思っていたし、コンビニで買うお茶もなんでもいい。今まではそれを悪いことだと思っていなかった。むしろ、ある1つのものに執着していないわけだから、融通がきくし、なにより気持ちが楽である。
ただ最近思うことは、ラグビーに関しては「こだわり」が足りないのではないかということだ。オールブラックスの有名選手や日本代表、大学ラグビーのトップ選手など、色々思い浮かべてみても、なにかしらの能力に突出している。タックルやヒット、パス、キック、ステップ、スピードなど、これなら勝負できるという長所がある。よく言われることだが、あらゆるスキルをまんべんなく平凡にできる人より、他がそこまでよくなくても何か1つの能力に秀でている選手はラグビーにおいて重宝される。自分はどうだろうかと考えた時、自信を持って、これにこだわったと言えるものはない。
幸い、まだ自分には大学ラグビーをする時間が2年以上残されている。自分の得意なものにこだわり続け、これなら絶対誰にも負けないと言えるようなことを身に付けたい。
稚拙な文章を読んでいただきありがとうございます。次は、未経験ながらセンターとして圧倒的成長を遂げている一年生の松本に回したいと思います。
リレー日記[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2018/11/01(木) 12:07
シルエットも性格も野村に近いものを持ち合わせているように思える1年の吉田からバトンを受け取りました、3年の高橋です。
対抗戦も5試合を終え、3勝2敗。東大ラグビー部としては順調といえる対抗戦シーズンになっているだろう。一方で、自分は今危機的状況に陥っている。それはリレー日記に書くことが全く思いつかないということだ。というのも、書き始めるまでに何時間もかかり、書き始めてからも書いては消しを繰り返し、ここまで1時間くらい経っているのだ。冒頭と末尾の紹介文は5分とかからずに書き終えたのにまさかこんなに時間がかかるとは、というのが今の気持ちである。
さて、なぜリレー日記を書けないことが危機的状況かというとまずはもちろん期限があるからだ。自分のリレー日記の期限は昨日までであった。(申し訳ないです。)この時点で大きな問題であり、どうしようもなくなった結果、「書くことを思いつかない」という諦めの手段で書き始めてしまった。
ただ、自分個人にとってはこの理由以上に問題となることがある。それはリレー日記を書けない原因がおそらく自分の今の感情や思考が明確に言語化、文章化できるほど整理できていないせいだということだ。対抗戦も5試合を終えたが、試合が終わればまたすぐ次の試合がやってきて、流れるようにシーズンは深まっていく。そうして、あっという間にシーズンは終わり、4年生になるだろう。そんな中で、現状のことや今年の残りのシーズンのこと、そして最高学年となる来年のことなど多くのことに考えを巡らせるうちに、1つ1つの考えがまとまらなくなってしまっていたのだと思う。リレー日記はこうした現状に気づかせてくれたのだ。書き終えた後に、じっくり時間をとって、もう一度自分の考えを整理したいと思う。
拙い文章になってしまいましたが、ご容赦ください。
次はラグビー部の中でもごく少ない、ラグビー、勉強、私生活の全ての充実を持ち合わせる2年の藤井にバトンを回したいと思います。
夢[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2018/10/27(土) 11:28
僕は、このリレー日記を二年半前、高3の4月から読んでいる。特に浪人時代には、勉強の合間にこの日記を読み心の支えとしていた。ついにこの日記を書くこととなり、個人的には非常に感慨深く思われる。
僕は高3の10月で高校のラグビー部を引退した。その時すでに志望校調査書には東京大学と書いて提出していたが、ラグビー部を引退するまでは進路のことなど全く気にしていなかった。引退すると、本当に自分なんかが東大に受かるのかという不安があった。また、ラグビー部の監督から他のある大学でラグビーをすることを強く勧められ、その道に行く選択肢もチャレンジングでとても魅力的に感じていた。
しかし、そんな将来に対する決断ができていない時期に読んだのが、今の3年(当時1年)野村先輩の書いたリレー日記である。
(http://www.turfc.com/blog_detail/blog_id=21&id=1093?SmartPhonePCView=2)
この文章を読み終えた時、僕の決意は固まっていた。
野村先輩(以下ノムさん)は僕が高1の時の高3の高校ラグビー部の先輩であり、僕とノムさんで花園予選は両ロックを組んでいた。
高校ラグビーでは夢破れたノムさんが東大ラグビー部でまた新たな夢を追っているという事実、「対抗戦A昇格」という言葉の響きの良さに武者震いがした。
「俺もノムさんの夢を一緒に追いたい。」
そう思って必死に勉強し、一年間余分に時間はかかってしまったが東大ラグビー部に入部することができた。
ただ、入部して改めて、「対抗戦A昇格」の実現は簡単ではないことを実感した。これまでの東大の先輩方が誰も成し遂げられていない夢である。この夢を実現するには、高校以前から実績のあるプレーヤーをリクルーティングし、入部時点からラグビーに対するモチベーションの高いメンバーが集まったチームを負かさなければならない。口で言う何倍も難しい夢であることは自覚している。
先月から今月にかけて、合計三週間膝の手術で入院していた時、一人でいる時間が長かった。その間、チームの練習ビデオや高校時代の試合などを見ていたのだが、その時これまでやこれからの自らのラグビー人生について考えていた。
まず、大学入学からこれまでの時間でどれだけ「夢」に近づけたのだろうか、と考えた。考えた末、「本当に近づけたのだろうか?」という思考に至った。恥ずかしながら、夢に近づくための最善の選択肢を選んで来られた自信はない。ウェイトトレーニングでも、何か言い訳を作ってサボる時もあった。なぜ受験期にあれだけ燃えた夢を追える環境に居られているのに、サボってしまった自分がいるのか。すごく情けない気持ちになった。
また、もう一つふと考えたことがあった。同期のほかの14人は、どのような目標を持って東大ラグビー部に所属しているのだろうか。三年後のこの時期にどんな自分たちの姿を想像しているのだろうか。自分たちの目標は共有されているだろうか。もちろん、今年の「対抗戦4勝」というチーム全体としての目標は共有されている。しかし、我々が4年生になった時の目標はまだ存在していない。僕は上で述べたように「対抗戦A昇格」を漠然と考えていた。他のものはもしかしたら、「入れ替え戦出場」または「楽しくラグビーをする」だったかもしれない。どんな目標が良い悪いということではない。自分たちの三年後の姿をこの半年間で語り合い、自分たちの将来像を共有することができなかったことが自分にとって大きな反省であると思った。それは、恥ずかしさや自分だけが空回りしてしまうのではないかという不安もあったからである。これも自分が情けなく感じた。
先日、武蔵大に東大が勝利を収めた。僕はその試合を外から眺めることしかしていないが、勝利を告げるホイッスルが鳴り響いたとき、自然と涙が溢れた。僕の何倍も辛いことをしてきて何倍もの責任を背負っていた先輩方に申し訳ないので必死で涙を堪えようとしたが無理だった。夢の実現の希望が見えたことに体の芯から熱くなるのを感じたからであった。決して不可能な夢ではない。そのように思わせてくれるような試合だった。
僕らの代の目標はまだない。しかし、「対抗戦A昇格」という目標を掲げても良いのではないかと思う。4年生になってから掲げる目標としては高いかもしれないが、あと3年あれば十分手に届く目標であると思う。そのポテンシャルが同期の15人にはあると自信を持って断言する。
なぜ自分は東大のラグビー部を目指して必死に勉強したのか、その初心を忘れないように、目標を実現するための最善の選択肢を常に選んでいきたい。3年後、僕らが4年生となり、東大ラグビー部が100周年を迎える年を見据えて1日1日を100%で過ごしていくことが重要であると思う。
頭で整理する前に思い浮かんだ順に書き連ねてしまったため、纏まりがなく読みにくい文章になってしまって申し訳ありませんでした。普段も頭で言うことを整理することが苦手なので、僕の思いの丈を書き留めておきました。特に同期には読んでもらいたいです。
次は、元フランカーだったと聞いて衝撃を受けた、とても大きな巨体を持つ勇河さんにバトンを回します。
| <<前へ | 次へ>> |
2025年11月
| <<前月 | 翌月>> |
| |
| |
| |
| |
| |
アーカイブ
- 2025年11月(5)
- 2025年10月(13)
- 2025年9月(11)
- 2025年8月(11)
- 2025年7月(11)
- 2025年6月(10)
- 2025年5月(8)
- 2025年4月(9)
- 2025年3月(9)
- 2025年2月(15)
- 2025年1月(2)
- 2024年12月(18)
- 2024年11月(12)
- 2024年10月(12)
- 2024年9月(13)
- 2024年8月(11)
- 2024年7月(12)
- 2024年6月(8)
- 2024年5月(9)
- 2024年4月(8)
- 2024年3月(8)
- 2024年2月(19)
- 2024年1月(7)
- 2023年12月(9)
- 2023年11月(12)
- 2023年10月(11)
- 2023年9月(12)
- 2023年8月(11)
- 2023年7月(11)
- 2023年6月(8)
- 2023年5月(7)
- 2023年4月(8)
- 2023年3月(7)
- 2023年2月(15)
- 2023年1月(7)
- 2022年12月(23)
- 2022年11月(14)
- 2022年10月(13)
- 2022年9月(14)
- 2022年8月(14)
- 2022年7月(16)
- 2022年6月(10)
- 2022年5月(11)
- 2022年4月(12)
- 2022年3月(10)
- 2022年2月(15)
- 2022年1月(4)
- 2021年12月(12)
- 2021年11月(12)
- 2021年10月(14)
- 2021年9月(12)
- 2021年8月(12)
- 2021年7月(12)
- 2021年6月(11)
- 2021年5月(12)
- 2021年4月(11)
- 2021年3月(13)
- 2021年2月(10)
- 2021年1月(21)
- 2020年12月(11)
- 2020年11月(12)
- 2020年10月(13)
- 2020年9月(12)
- 2020年8月(14)
- 2020年7月(12)
- 2020年6月(12)
- 2020年5月(13)
- 2020年4月(12)
- 2020年3月(13)
- 2020年2月(12)
- 2020年1月(4)
- 2019年12月(10)
- 2019年11月(15)
- 2019年10月(11)
- 2019年9月(13)
- 2019年8月(13)
- 2019年7月(10)
- 2019年6月(8)
- 2019年5月(13)
- 2019年4月(7)
- 2019年3月(7)
- 2019年2月(5)
- 2019年1月(7)
- 2018年12月(15)
- 2018年11月(12)
- 2018年10月(15)
- 2018年9月(10)
- 2018年8月(7)
- 2018年7月(6)
- 2018年6月(10)
- 2018年5月(12)
- 2018年4月(11)
- 2018年3月(5)
- 2017年12月(11)
- 2017年11月(13)
- 2017年10月(12)
- 2017年9月(11)
- 2017年8月(12)
- 2017年7月(10)
- 2017年6月(10)
- 2017年5月(17)
- 2017年4月(10)
- 2017年3月(13)
- 2017年2月(4)
- 2016年12月(15)
- 2016年11月(12)
- 2016年10月(14)
- 2016年9月(12)
- 2016年8月(12)
- 2016年7月(15)
- 2016年6月(9)
- 2016年5月(9)
- 2016年4月(11)
- 2016年3月(10)
- 2016年2月(7)
- 2015年12月(8)
- 2015年11月(11)
- 2015年10月(10)
- 2015年9月(10)
- 2015年8月(5)
- 2015年7月(7)
- 2015年6月(11)
- 2015年5月(13)
- 2015年4月(8)
- 2015年3月(9)
- 2015年2月(12)
- 2015年1月(11)
- 2014年12月(12)
- 2014年11月(10)
- 2014年10月(12)
- 2014年9月(12)
- 2014年8月(12)
- 2014年7月(6)
- 2014年6月(5)
- 2014年5月(13)
- 2014年4月(11)
- 2014年3月(14)
- 2014年2月(7)
- 2013年12月(23)
- 2013年11月(29)
- 2013年10月(32)
- 2013年9月(30)
- 2013年8月(14)
- 2013年7月(15)
- 2013年6月(23)
- 2013年5月(33)
- 2013年4月(27)
- 2013年3月(20)
- 2013年2月(10)
- 2013年1月(1)
- 2012年12月(13)
- 2012年11月(11)
- 2012年10月(24)
- 2012年9月(13)
- 2012年8月(9)
- 2012年7月(5)
- 2012年6月(8)
- 2012年5月(11)
- 2012年4月(9)
- 2012年3月(10)
- 2012年2月(8)
- 2011年12月(6)
- 2011年11月(6)
- 2011年10月(7)
- 2011年9月(9)
- 2011年8月(10)
- 2011年7月(5)
- 2011年6月(5)
- 2011年5月(9)
- 2011年4月(7)
- 2011年3月(8)
- 2011年2月(4)
ブログ最新記事
- 埼玉旅行記 (11/16 18:05)
- 渋谷のサグラダ・ファミリア (11/15 20:40)
- 逆ナンなん? (11/13 16:34)
- バイト (11/12 10:31)
- モチーフで見る部員の部屋 (11/07 00:32)
- 自己開示 (10/31 13:42)
- ポスト考古学実習 (10/28 21:23)
- 白球に魅せられて (10/25 18:37)
- LoveType16 (10/25 11:46)
- 休みたい (10/25 07:09)
- No pain, no gain. (10/24 12:29)
- 銀杏 (10/18 07:50)
- ラグビーマン決戦・徳島頂上バトル (10/17 19:33)
- 名古屋に行きました。 (10/17 00:13)
- 勇気のいらない親切 (10/13 16:15)
- 懐かしのDAYS (10/10 16:14)
- アレルギー (10/04 23:56)
- 炎 (10/02 23:50)
- タックル怖くね? (09/29 22:08)
- surprise! mf (09/26 22:52)





.jpg)