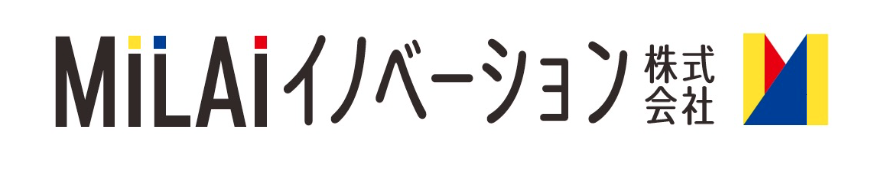ブログ 倉橋 直希さんが書いた記事
| 次へ>> |
同期紹介[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2024/12/11(水) 18:44
デイビスからバトンを受け取りました、倉橋です。彼は選手としても人としても素晴らしい人間です。今年の春に一緒にハーフ団を組んでいたときは慣れないポジションでプレーする僕のことを引っ張ってくれました。そのおかげでハーフとしてプレーする時にいつも緊張ばかりしていたのがとても楽しめるようになったので本当に感謝しています。彼との一番の思い出はデルとゆうしと一緒にシックスネーションズの試合を見たことです。来年は豚の足こそ無いかもですが、ウェールズが勝てるように僕も一緒に応援します!
さて、時は戻って4年前。東大に入学した僕はやったことのない何かを始めたいと思っていた。そんなわけでラグビー部は僕の選択肢にはなかったのだが、そこに桑田が現れた。現れたといっても物理的に現れたわけではなく、食の科学という授業の参加者一覧に彼の名前があった(当時はすべてオンライン授業)。まさかと思ったが、実際に彼からラインが来て、さらに偶然7号館の下で再会したのだ。ここまで彼のことを以前から知っているかのように書いたが、彼はなんと小学校3年から4年間クラスが一緒だった。しかも出席番号も隣。よくつるんでいた。そんなわけで久しぶりに会ったついでにラグビー部の新歓に行った。しかし「俺もいるから」と言われたから行ったのに彼は授業を抜けられないと理由で来なかった。
その初めての新歓練習で覚えていることはあまりないが、本多の存在だけは覚えている。旧友にドタキャンされた先にいた同クラは心強い。彼はその時から既に100kgあったが、いざウエイトをしてみると荷重の筋トレをしたことない僕には信じられないくらい強かった。そして今もみんなとの差を保ったままさらに強くなっている。某うどんチェーンの特盛うどんを二口で食べるし試験もちょっと勉強しただけでいい成績をとるし、僕にないものをすべて持っているあたり、ずっと尊敬していた。
新歓練習の後には新歓飯に行った。コロナ禍ということもあって部からお金を出してもらって一年生だけで飯に行った。なんとも奇妙な時代である。そこの席には同時に辻とりんと授業終わりの桑田がいた。
辻の第一印象は声が大きい、笑い声はもっと大きい、変わったやつ、というものだった。これは別に今も変わらない。強いて言うならこれらが強調されたくらいだ。言わずと知れた目立ちたがり屋だが良い方に目立てるようにせいぜい頑張ってほしいものだ。
りんの第一印象は特にない。多分僕の注意は全部辻に持って行かれたのだろう。りんは筋力が強いし、気も強いし、何を考えているのかもよくわからないことも多いが、天然で面白いという話も聞いたことがある。去年笑いの哲学という授業を履修したときに漫才のネタを書いたことは知っているのでそれは本当に見せてほしいです。そして、そんな面白いに決まっているネタをあきおに実演してもらうことは僕の夢の一つだ。
塩谷とはまだお互いに入部する前に二人で飯に行った。新歓飯という体だったが、なぜかまだ入ってない二人で食べたこの時の記憶が鮮明にある。なんなら話した内容まで細かく覚えている。デカくなりたいと言っていたがすぐにデカくなった。そしてスタッフになることも考えていたが、今となってはその世界線は考えられないほどだ。某強豪校との練習試合で105分出たときは特にすごかった。
清和は一年生が本格的に部活を始めて少し経った後の6月にいきなり現れて、初回でCC(コーディネーションサーキット)を一緒にやった強者だった。いきなりこんなにきついことをやって入部してくれるのかなと思ったが杞憂だった。清和はそんなレベルの人間ではなかった。清和はどんな人間かというと核心を突いたことをストレートに言う人間だ。際どいことでも言い方が上手だからこれがまたとても面白い。
1年や2年の時に多く時間を共にした人に雪竹を挙げたい。これは自分もそうなのだがとにかく食べるのに時間がかかった。練習後には永遠と感じられるような長い時間をかけてご飯を食べていた。最近はバイトや金欠とやらですぐ家に帰って食べているそうだがもっと雪竹の素晴らしい人生の話を聞きたいものである。雪竹とバイトといえば1年生の時に朝練の前に某牛丼屋で深夜シフトに入っていたのを太田さんに怒られていたのが印象的だ。
一木はラグビーという激しいスポーツをやっているが、ラグビー以外では驚くほど温厚なインドア派だ。ギャップ萌えでも狙ってるのか。2年生はこの4年間で最も練習がハードだった一年だった記憶があるが、そんななか息抜きで彼とさしで寿司食べたりサッカー見に行ったりできたのは今でもうれしい思い出である。まわりにサッカー見る人が少ないので卒部した後も家から出たくなくてもたまには一緒に行きましょう。
最初の2年ほどは小野がどんなラグビー選手なのか、はたまたどんな人間かさえもよくわからなかった。怪我や手術を繰り返していたので仕方なしといったところか。彼が復帰した時のラグビー中のプレーや雰囲気はアイランダーぽかった。そんな小野は合宿の隙間時間でずとラグビー見たり、筋トレするために最終試験を切ったり、少しでもパフォーマンスが上がるようにアメリカからいろんなサプリ(本人いわく安全らしい)を取り寄せたりするほど学年一ラグビーが好きなやつだ。またラグビーの深い話を一緒にしたいと思わせてくれる。
小野とは対照的に幸いにも僕は4年間大きな怪我に見舞われなかった。しっかり体に気を遣っているからなのか体質なのか単に運が良かっただけなのかはわからないが、これは自分の最大の武器となった。出場機会が少なくてもいつ自分の出番が来てもいいように準備することの大切さも心得たので、最後の3週間もこれまでのように頑張りたい。
そんなわけでメンターのよーこにお世話になることは少なかった。よーこは今年主務をやっていたはずなのにそんなに忙しそうにしている姿は見なかった。今日も部室でこの日記を書いていたが、隣でぐっすり眠っていた。ここによーこのすごさがある。要領がとても良いのである。しかも後輩と仲良くご飯に行くところもよく見かける。この二つの才能を持ち合わせれば怖いことは何もないんじゃないかと思えて羨ましい。
2年生の終わりに僕は留年して人生に絶望していた(大袈裟かもしれないが精神的にきつかったのは事実だった)が、その時に救ってくれたのは礒崎だった。些細なことだったし本人にその自覚はないだろうが、彼のおかげで僕は気が晴れて前を向けた。何があったかはちょっと僕が恥ずかしくなってしまうので書かないが、そこに関してはめちゃくちゃに感謝しています。またつらいことあったら頼らせていただきます。
もう一人僕に前を向かせてくれた人がいたとすればもりぞーだ。似たような経験をした彼女からかけられた言葉は助けになったし、実際最近少しずつそのことを感じ始めている。中高時代を合わせたら相当な年月を同じ空間で過ごしているが、ようやくもりぞーがどんな人間か分かってきた気がする。最も僕はというと単純な人間なのでとっくにすべて見透かされているだろうが。日常的に会えなくなるのは寂しいけど、忙しい中でもたまに会ってください。
3年の後半から4年にかけて東大ラグビー部には多くの留学生が来て一緒にプレーをした。これに間違いなく貢献していたのはデルだった。コミュ力があって五カ国語できてラグビーも上手い。試合中は何かに取り憑かれてるのではないかと思うほどの狂気が垣間見えることもあるが普段は優しさに溢れているやつだ。最近は会えていなくて寂しいが、京大戦の時に来てくれるとのことなので、特別なビールを用意して待ってます。
奥山は口数があまり多くないが、背中で多くを語るやつだった。去年は毎試合動けなくなるまで闘っていた姿は見ているだけでもアツさが伝わってきた。今年は試合の最後まで闘い続けているのを見ると彼の弛まぬ努力が分かる。背中で多く語ると言ったが、奥山は表情からも感情がよく伝わってくる。顔で喋るといえば礒崎だが、奥山も負けてはいない。顔全体で表現しているというよりも感情が抑え切れてない感じがまた良い。
あきおはやよい軒でお米を11杯食べるような大食漢である。いつかわんこそばに行って何杯食べられるか横で観察してみたい。寝起きと腹が減っている時は機嫌が悪くて要注意だが、基本的にみんなを笑顔にしてくれる、ほぼパンダだ。実際僕のラインではあきおの名前は「X-Factorパンダ」だ。これはあきおがパンダ界に入った場合にスクラムの強さや動ける度合いも含めてX-Factor並みのすごさを持っているだろうという敬意を込めている。これは本当にいじってません。
話は戻しまして、初めて行った新歓の数日後、また桑田に誘われて新歓練習のために駒場に行った。と思ったらそれは新歓練習ではなく一年生は一人もいなかった。桑田がシニアの練習に参加してみたかっただけのようだ。なんてひどいやつだ。しかし、ここで僕は初めて寿太郎に会った。アメフト部とラグビー部の両方に入って迷っていたが、話を聞いてみたら彼はラグビー部に入ると思った。結局ラグビー部に入ったわけだが、そこからは共に過ごす時間が多くなった。そしてそこで寿太郎のラグビーにかける情熱やその面白いトークに惹かれていった。この4年間チームメイトとして、そして今年はキャプテンとして一緒にラグビーができて本当によかった。
最後に、この場を借りて4年間支えてくださった人たちに感謝の意を述べたいと思います。まず両親へ、入部当初から数多くの心配をかけたかもしれませんが、一番近くで一番たくさん応援してくれてありがとうございました。倶楽部、監督、コーチの皆様へ、僕たちのことを信じてともに戦っていただきありがとうございました。先輩、後輩へ、みんなとラグビーができて光栄でした、これからも応援しています。同期へ、卒部した後もずっと仲良くやっていきましょう。
最後まで楽しく、かつ真剣にラグビーに取り組み、人間としても成長できたのはみなさんのおかげでした。本当にありがとうございました。これからの2試合もノーサイドのホイッスルが鳴るまで成長していきます。
次は小学校の時からはちょっとでかくなっただけで中身も外見も何も変わっていない桑田にバトンを渡します。彼のおかげでラグビー部に入れたと言うとなんだか負けた気がして嫌ですが、ラグビー部に入るきっかけをくれたことには感謝しています。これからもお世話するのでよろしく。
さて、時は戻って4年前。東大に入学した僕はやったことのない何かを始めたいと思っていた。そんなわけでラグビー部は僕の選択肢にはなかったのだが、そこに桑田が現れた。現れたといっても物理的に現れたわけではなく、食の科学という授業の参加者一覧に彼の名前があった(当時はすべてオンライン授業)。まさかと思ったが、実際に彼からラインが来て、さらに偶然7号館の下で再会したのだ。ここまで彼のことを以前から知っているかのように書いたが、彼はなんと小学校3年から4年間クラスが一緒だった。しかも出席番号も隣。よくつるんでいた。そんなわけで久しぶりに会ったついでにラグビー部の新歓に行った。しかし「俺もいるから」と言われたから行ったのに彼は授業を抜けられないと理由で来なかった。
その初めての新歓練習で覚えていることはあまりないが、本多の存在だけは覚えている。旧友にドタキャンされた先にいた同クラは心強い。彼はその時から既に100kgあったが、いざウエイトをしてみると荷重の筋トレをしたことない僕には信じられないくらい強かった。そして今もみんなとの差を保ったままさらに強くなっている。某うどんチェーンの特盛うどんを二口で食べるし試験もちょっと勉強しただけでいい成績をとるし、僕にないものをすべて持っているあたり、ずっと尊敬していた。
新歓練習の後には新歓飯に行った。コロナ禍ということもあって部からお金を出してもらって一年生だけで飯に行った。なんとも奇妙な時代である。そこの席には同時に辻とりんと授業終わりの桑田がいた。
辻の第一印象は声が大きい、笑い声はもっと大きい、変わったやつ、というものだった。これは別に今も変わらない。強いて言うならこれらが強調されたくらいだ。言わずと知れた目立ちたがり屋だが良い方に目立てるようにせいぜい頑張ってほしいものだ。
りんの第一印象は特にない。多分僕の注意は全部辻に持って行かれたのだろう。りんは筋力が強いし、気も強いし、何を考えているのかもよくわからないことも多いが、天然で面白いという話も聞いたことがある。去年笑いの哲学という授業を履修したときに漫才のネタを書いたことは知っているのでそれは本当に見せてほしいです。そして、そんな面白いに決まっているネタをあきおに実演してもらうことは僕の夢の一つだ。
塩谷とはまだお互いに入部する前に二人で飯に行った。新歓飯という体だったが、なぜかまだ入ってない二人で食べたこの時の記憶が鮮明にある。なんなら話した内容まで細かく覚えている。デカくなりたいと言っていたがすぐにデカくなった。そしてスタッフになることも考えていたが、今となってはその世界線は考えられないほどだ。某強豪校との練習試合で105分出たときは特にすごかった。
清和は一年生が本格的に部活を始めて少し経った後の6月にいきなり現れて、初回でCC(コーディネーションサーキット)を一緒にやった強者だった。いきなりこんなにきついことをやって入部してくれるのかなと思ったが杞憂だった。清和はそんなレベルの人間ではなかった。清和はどんな人間かというと核心を突いたことをストレートに言う人間だ。際どいことでも言い方が上手だからこれがまたとても面白い。
1年や2年の時に多く時間を共にした人に雪竹を挙げたい。これは自分もそうなのだがとにかく食べるのに時間がかかった。練習後には永遠と感じられるような長い時間をかけてご飯を食べていた。最近はバイトや金欠とやらですぐ家に帰って食べているそうだがもっと雪竹の素晴らしい人生の話を聞きたいものである。雪竹とバイトといえば1年生の時に朝練の前に某牛丼屋で深夜シフトに入っていたのを太田さんに怒られていたのが印象的だ。
一木はラグビーという激しいスポーツをやっているが、ラグビー以外では驚くほど温厚なインドア派だ。ギャップ萌えでも狙ってるのか。2年生はこの4年間で最も練習がハードだった一年だった記憶があるが、そんななか息抜きで彼とさしで寿司食べたりサッカー見に行ったりできたのは今でもうれしい思い出である。まわりにサッカー見る人が少ないので卒部した後も家から出たくなくてもたまには一緒に行きましょう。
最初の2年ほどは小野がどんなラグビー選手なのか、はたまたどんな人間かさえもよくわからなかった。怪我や手術を繰り返していたので仕方なしといったところか。彼が復帰した時のラグビー中のプレーや雰囲気はアイランダーぽかった。そんな小野は合宿の隙間時間でずとラグビー見たり、筋トレするために最終試験を切ったり、少しでもパフォーマンスが上がるようにアメリカからいろんなサプリ(本人いわく安全らしい)を取り寄せたりするほど学年一ラグビーが好きなやつだ。またラグビーの深い話を一緒にしたいと思わせてくれる。
小野とは対照的に幸いにも僕は4年間大きな怪我に見舞われなかった。しっかり体に気を遣っているからなのか体質なのか単に運が良かっただけなのかはわからないが、これは自分の最大の武器となった。出場機会が少なくてもいつ自分の出番が来てもいいように準備することの大切さも心得たので、最後の3週間もこれまでのように頑張りたい。
そんなわけでメンターのよーこにお世話になることは少なかった。よーこは今年主務をやっていたはずなのにそんなに忙しそうにしている姿は見なかった。今日も部室でこの日記を書いていたが、隣でぐっすり眠っていた。ここによーこのすごさがある。要領がとても良いのである。しかも後輩と仲良くご飯に行くところもよく見かける。この二つの才能を持ち合わせれば怖いことは何もないんじゃないかと思えて羨ましい。
2年生の終わりに僕は留年して人生に絶望していた(大袈裟かもしれないが精神的にきつかったのは事実だった)が、その時に救ってくれたのは礒崎だった。些細なことだったし本人にその自覚はないだろうが、彼のおかげで僕は気が晴れて前を向けた。何があったかはちょっと僕が恥ずかしくなってしまうので書かないが、そこに関してはめちゃくちゃに感謝しています。またつらいことあったら頼らせていただきます。
もう一人僕に前を向かせてくれた人がいたとすればもりぞーだ。似たような経験をした彼女からかけられた言葉は助けになったし、実際最近少しずつそのことを感じ始めている。中高時代を合わせたら相当な年月を同じ空間で過ごしているが、ようやくもりぞーがどんな人間か分かってきた気がする。最も僕はというと単純な人間なのでとっくにすべて見透かされているだろうが。日常的に会えなくなるのは寂しいけど、忙しい中でもたまに会ってください。
3年の後半から4年にかけて東大ラグビー部には多くの留学生が来て一緒にプレーをした。これに間違いなく貢献していたのはデルだった。コミュ力があって五カ国語できてラグビーも上手い。試合中は何かに取り憑かれてるのではないかと思うほどの狂気が垣間見えることもあるが普段は優しさに溢れているやつだ。最近は会えていなくて寂しいが、京大戦の時に来てくれるとのことなので、特別なビールを用意して待ってます。
奥山は口数があまり多くないが、背中で多くを語るやつだった。去年は毎試合動けなくなるまで闘っていた姿は見ているだけでもアツさが伝わってきた。今年は試合の最後まで闘い続けているのを見ると彼の弛まぬ努力が分かる。背中で多く語ると言ったが、奥山は表情からも感情がよく伝わってくる。顔で喋るといえば礒崎だが、奥山も負けてはいない。顔全体で表現しているというよりも感情が抑え切れてない感じがまた良い。
あきおはやよい軒でお米を11杯食べるような大食漢である。いつかわんこそばに行って何杯食べられるか横で観察してみたい。寝起きと腹が減っている時は機嫌が悪くて要注意だが、基本的にみんなを笑顔にしてくれる、ほぼパンダだ。実際僕のラインではあきおの名前は「X-Factorパンダ」だ。これはあきおがパンダ界に入った場合にスクラムの強さや動ける度合いも含めてX-Factor並みのすごさを持っているだろうという敬意を込めている。これは本当にいじってません。
話は戻しまして、初めて行った新歓の数日後、また桑田に誘われて新歓練習のために駒場に行った。と思ったらそれは新歓練習ではなく一年生は一人もいなかった。桑田がシニアの練習に参加してみたかっただけのようだ。なんてひどいやつだ。しかし、ここで僕は初めて寿太郎に会った。アメフト部とラグビー部の両方に入って迷っていたが、話を聞いてみたら彼はラグビー部に入ると思った。結局ラグビー部に入ったわけだが、そこからは共に過ごす時間が多くなった。そしてそこで寿太郎のラグビーにかける情熱やその面白いトークに惹かれていった。この4年間チームメイトとして、そして今年はキャプテンとして一緒にラグビーができて本当によかった。
最後に、この場を借りて4年間支えてくださった人たちに感謝の意を述べたいと思います。まず両親へ、入部当初から数多くの心配をかけたかもしれませんが、一番近くで一番たくさん応援してくれてありがとうございました。倶楽部、監督、コーチの皆様へ、僕たちのことを信じてともに戦っていただきありがとうございました。先輩、後輩へ、みんなとラグビーができて光栄でした、これからも応援しています。同期へ、卒部した後もずっと仲良くやっていきましょう。
最後まで楽しく、かつ真剣にラグビーに取り組み、人間としても成長できたのはみなさんのおかげでした。本当にありがとうございました。これからの2試合もノーサイドのホイッスルが鳴るまで成長していきます。
次は小学校の時からはちょっとでかくなっただけで中身も外見も何も変わっていない桑田にバトンを渡します。彼のおかげでラグビー部に入れたと言うとなんだか負けた気がして嫌ですが、ラグビー部に入るきっかけをくれたことには感謝しています。これからもお世話するのでよろしく。
農学部![ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2024/08/23(金) 08:25
3年の細谷からバトンを受け取りました、4年の倉橋です。一昨日の試合では悔しい思いをしたのでB戦でももちろん、今度はA戦で一緒に活躍できるようにお互いに頑張りましょう。
今回は農学部の良さについて書きます。なぜこのようなことをしなければならないかというと、世の中に農学部について間違ったイメージや偏見が蔓延っているからです。畑を耕してそう、バカが多そう、などなど。控えめに言ってこの状況は許しがたいものなので、この文章読んでいる人にだけでも農学部が素晴らしいところであるということを知ってもらいたいです。偶然にも今が進振りの時期だそうなので、まだ迷っている人は安冨さんのリレー日記と合わせて読むと良いでしょう。
まず、農学部は畑を耕してそうだというイメージですが、実際に畑を耕している人は少ないです。本多のように化学系や生物系の研究している人も多く、畑を耕すこととはあまり関係がないことをする人も多くいます。そして、そうでない人も桑田が所属する森林系や水産系の専修もあります。さらに、農学部と聞くと理系のイメージが強いかもしれませんが、実は農学部の学生で文系から理転して来る学生も多いのです。そんなこともあって理系でなければついていけないというような内容はかなり少ないです。生物系の授業も高校生物の範囲から学んでいくことがほとんどです。つまり、農学部はすべての人に開かれた学部であり、幅広く学ぶことができるところです。
しかも学ぶといっても試験前に詰め込んで試験が終わった瞬間に忘れるというような勉強ではなく、しっかり実験や実習に基づいた知識を身につけることができます。なぜかというと、農学部は世界のあらゆる問題を解決する鍵を握っているからです。食糧問題はもちろん、環境問題や地球温暖化に対処するための研究も数多く行われています。詳しくは農学部のホームページの農学部のミッションというのに掲載されているのでぜひ読んでみてください。
そして一番大事なのはなんといっても楽しいということです。僕にとっての楽しいポイントはもちろんの毎回の授業の内容もそうですが、特に実習に行くことができるということです。教室で座っているだけでも研究室でずっと研究しているだけでもフィールドで実際に何が起きているかはわかりません。農学部では多くの専修で実習を行っており、全国にある東大の施設などに出向いて実習を行います。そして、田無キャンパスで実習を行う時は様々な絶品野菜や果物が手に入ります。この間は専修の同期と収穫した野菜をナポリタンにして食べたところ、今までに食べたことのないくらい美味しかったです。
そんなこともあり、僕は最近とても勉強の意欲が湧いています。桑田も前期課程では全然勉強をしていなかったのに、農学部に入ってからは意欲的に「俺図書館で勉強してくるわ」とか「俺今論文読んでるから」というようなことをよく言っています。その成果か一緒に森へ行くと木の種類とその葉が食べられるか食べられないかを実演とともに目を輝かせながら説明してくれます。
さて、今私たちは菅平合宿中ですが、ここはレタスやとうもろこし畑が多いだけでなく、それらの収穫が行われていたり、町中でトラクターが行き交っているのを見ていると農学部の血が騒ぎます。ラグビーと野菜に囲まれて生活するなんてなんという幸せなことなのだろうかと想像しながら生活しています。
次は1年のジェッドにバトンを渡します。彼はこの部活で3人目のウェールズ人となっていますが、もう二人に負けないほどのセンスをこの間の一年生試合で見せつけていました。今は怪我中ということですが、僕が卒部してしまう前に早く一緒にプレーしたいです。
今回は農学部の良さについて書きます。なぜこのようなことをしなければならないかというと、世の中に農学部について間違ったイメージや偏見が蔓延っているからです。畑を耕してそう、バカが多そう、などなど。控えめに言ってこの状況は許しがたいものなので、この文章読んでいる人にだけでも農学部が素晴らしいところであるということを知ってもらいたいです。偶然にも今が進振りの時期だそうなので、まだ迷っている人は安冨さんのリレー日記と合わせて読むと良いでしょう。
まず、農学部は畑を耕してそうだというイメージですが、実際に畑を耕している人は少ないです。本多のように化学系や生物系の研究している人も多く、畑を耕すこととはあまり関係がないことをする人も多くいます。そして、そうでない人も桑田が所属する森林系や水産系の専修もあります。さらに、農学部と聞くと理系のイメージが強いかもしれませんが、実は農学部の学生で文系から理転して来る学生も多いのです。そんなこともあって理系でなければついていけないというような内容はかなり少ないです。生物系の授業も高校生物の範囲から学んでいくことがほとんどです。つまり、農学部はすべての人に開かれた学部であり、幅広く学ぶことができるところです。
しかも学ぶといっても試験前に詰め込んで試験が終わった瞬間に忘れるというような勉強ではなく、しっかり実験や実習に基づいた知識を身につけることができます。なぜかというと、農学部は世界のあらゆる問題を解決する鍵を握っているからです。食糧問題はもちろん、環境問題や地球温暖化に対処するための研究も数多く行われています。詳しくは農学部のホームページの農学部のミッションというのに掲載されているのでぜひ読んでみてください。
そして一番大事なのはなんといっても楽しいということです。僕にとっての楽しいポイントはもちろんの毎回の授業の内容もそうですが、特に実習に行くことができるということです。教室で座っているだけでも研究室でずっと研究しているだけでもフィールドで実際に何が起きているかはわかりません。農学部では多くの専修で実習を行っており、全国にある東大の施設などに出向いて実習を行います。そして、田無キャンパスで実習を行う時は様々な絶品野菜や果物が手に入ります。この間は専修の同期と収穫した野菜をナポリタンにして食べたところ、今までに食べたことのないくらい美味しかったです。
そんなこともあり、僕は最近とても勉強の意欲が湧いています。桑田も前期課程では全然勉強をしていなかったのに、農学部に入ってからは意欲的に「俺図書館で勉強してくるわ」とか「俺今論文読んでるから」というようなことをよく言っています。その成果か一緒に森へ行くと木の種類とその葉が食べられるか食べられないかを実演とともに目を輝かせながら説明してくれます。
さて、今私たちは菅平合宿中ですが、ここはレタスやとうもろこし畑が多いだけでなく、それらの収穫が行われていたり、町中でトラクターが行き交っているのを見ていると農学部の血が騒ぎます。ラグビーと野菜に囲まれて生活するなんてなんという幸せなことなのだろうかと想像しながら生活しています。
次は1年のジェッドにバトンを渡します。彼はこの部活で3人目のウェールズ人となっていますが、もう二人に負けないほどのセンスをこの間の一年生試合で見せつけていました。今は怪我中ということですが、僕が卒部してしまう前に早く一緒にプレーしたいです。
始まり[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2024/03/22(金) 14:19
同期の奥山からバトンを受け取りました、新4年の倉橋です。
奥山はこの間開催された学年会で行った謎解きで憲法第2条の穴埋めをヒントなしで即答したのはかっこよかったです。僕らが謎解きの本筋から大きく外れたところで悪戦苦闘しているなか、「これは大きいですね」と声をかけてくれたスタッフのことは忘れません。奥山はこんな感じで頭が良いだけでなく、試合中ともなれば力強いプレーを連発し、最後には本当に走れなくなるまで全力を尽くすような理想のラグビープレイヤーです。
モテるかどうかはともかく守田英正似と紹介された私ですが、これは自他ともに認めており、サッカー日本代表の重要な試合の前後にはラグビー部内だけではなく、同クラや高校同期、はたまた新歓で初めて会った一年生にさえも言われるほどです。競技は違えど東大の守田としてもっと活躍できるように頑張ります。
紹介文にも書かれましたが、私は同期内では早いうちから逆バリキャラを確立してしまいました。逆張りという言葉自体東大のラグビー部に入ってから初めて耳にしたので当初は困惑していましたが、今ではそんなこと言われても全く気にならなくなりました。逆張りと言われる理由の一つに僕の海外生活が長かったことが挙げられますが、今回のリレー日記ではそんな僕のラグビーとの出会いを書こうと思います。
それは中学1年の夏だった。父の転勤に伴いイギリスに引っ越し、現地の学校へ転校したのだった。これはおそらくどこに行っても一緒だが、やはり進学したり転校したりして新しい学校に身を置くとなるとどうしても不安が大きくなる。そして僕はそんなときには早めに友達を作ろうとするのだが、その不安は初日の昼休みに解消した。イギリスではもちろんラグビーは盛んだが、一番人気なスポーツはなんといってもサッカー。そんなサッカーを毎日昼休みに校庭で男子が全員やるのだ。男というのはとても単純な生き物で、一回楽しく一緒にサッカーやるだけで仲良くなってしまう。楽しいのはもちろんだが家に帰れば母に怒られる毎日だった。というのもサッカーは制服を着たまま革靴でやるので、それらが全部泥だらけになったまま家に帰るからだ。それがただの泥ならいいのだが、そこにはたまに何かしらの動物の糞がついていたりした。カモであれば匂いは全然しないのだが、雑食のキツネだった場合が最悪で... あとは詳しくは書きませんが、簡単にいうと男子中学生がやりそうなことをみんなでしてました。
汚い話は置いといて、二日目の学校の放課後ちょうど帰宅する前、ジョージといういかにもフッカーをやっていそうな友達が声をかけてくれた。(以下すべて倉橋による和訳)
「そういえばさ、明日ラグビーやらない?」
「明日?土曜日に?」
「そう、みんなやってるよ!」
「え、どこで?」
「ここで、明日9時に来て!」
「ここ?わかった、考えとく。」
ラグビーなんてやったことないどころか見たことないし、ルールは前に投げてはいけないということくらいしか知らなかった。情報はジョージがくれたものだけで半信半疑だったが両親と相談した結果とりあえず行って見学することにした。
そしてまた次の日、前の日に話をしていた場所に行ったら本当に人が集まっていた。みんな学校の体育着を着用して集まっているなか、自分一人だけ私服で行ったせいでめちゃくちゃ浮いてしまった。そして先生に目をつけられる。
「おう、君新しい生徒か?」
「あ、はい」
「誰か知っているか?」
「一応そこにいるオリーとかジョージとか…」
「その格好はなんだ?早く着替えて入りな!」
マジか。見学という概念は存在しないらしい。見学しようと思っていたものの運動着を持って行っていて助かった。そしてさらに前日に父にタックルの仕方とかされ方とかの基本を教えてもらったのも助かった。別に強豪というわけでもなく練習がきついというわけでもなかったので初心者の僕からしてみればちょうどよかった。しかも学校のチームだったからか次の週の試合でも少しばかりのプレータイムをもらえた。そんなこんなで週一の練習と試合という楽しいラグビー生活が始まった。
そんな僕がラグビーを始めた数週間後、タイミングよく2015年のワールドカップが始まった。衝撃を受けたのは開幕戦のイングランド対フィジー。そこで初めてラグビーがどんなスポーツかなんとなくわかった気がした。これまた逆張りと言われることを承知のうえで正直なことを言うと日本が南アフリカを破った試合よりも心に残っている。もちろん日本対南アフリカも感動したが、その前の弱かった時代を知らないうえに南アフリカの強さも知らない僕からしてみれば隣で父が泣き叫んでいる理由もわからないし行く先々で日本人である僕に対して「よくやった!」と褒めてくる人たちがよくわからなかった。
ワールドカップほど試合数が多く、ラグビーの楽しさを知るための教科書は存在しないわけで、ラグビーを始めてから一ヶ月ほどですっかり学校でのラグビーの話についていけるようになり、チームでもスタメンをとれるようになった。それから勝っても負けても楽しめるようになり、いいプレーをするとみんなから忍者だとか侍だとか呼ばれたことはいい思い出だ。
稚拙な文章でしたが、僕がラグビーを始めた流れはまさにこんな感じでした。これですっかりラグビー好きになったわけですが、再びラグビーをやる機会が訪れたのは大学に入った後でした。それについては残る2回のリレー日記のどちらかで書くと思います。
次は僕の同期の桑田でさえ弟みたいだと言った新2年の武村にバトンを渡します。彼は元気がよく純粋な人間ですが、だからこそ辻のような先輩にはくっつきすぎない方がいいと思います。
奥山はこの間開催された学年会で行った謎解きで憲法第2条の穴埋めをヒントなしで即答したのはかっこよかったです。僕らが謎解きの本筋から大きく外れたところで悪戦苦闘しているなか、「これは大きいですね」と声をかけてくれたスタッフのことは忘れません。奥山はこんな感じで頭が良いだけでなく、試合中ともなれば力強いプレーを連発し、最後には本当に走れなくなるまで全力を尽くすような理想のラグビープレイヤーです。
モテるかどうかはともかく守田英正似と紹介された私ですが、これは自他ともに認めており、サッカー日本代表の重要な試合の前後にはラグビー部内だけではなく、同クラや高校同期、はたまた新歓で初めて会った一年生にさえも言われるほどです。競技は違えど東大の守田としてもっと活躍できるように頑張ります。
紹介文にも書かれましたが、私は同期内では早いうちから逆バリキャラを確立してしまいました。逆張りという言葉自体東大のラグビー部に入ってから初めて耳にしたので当初は困惑していましたが、今ではそんなこと言われても全く気にならなくなりました。逆張りと言われる理由の一つに僕の海外生活が長かったことが挙げられますが、今回のリレー日記ではそんな僕のラグビーとの出会いを書こうと思います。
それは中学1年の夏だった。父の転勤に伴いイギリスに引っ越し、現地の学校へ転校したのだった。これはおそらくどこに行っても一緒だが、やはり進学したり転校したりして新しい学校に身を置くとなるとどうしても不安が大きくなる。そして僕はそんなときには早めに友達を作ろうとするのだが、その不安は初日の昼休みに解消した。イギリスではもちろんラグビーは盛んだが、一番人気なスポーツはなんといってもサッカー。そんなサッカーを毎日昼休みに校庭で男子が全員やるのだ。男というのはとても単純な生き物で、一回楽しく一緒にサッカーやるだけで仲良くなってしまう。楽しいのはもちろんだが家に帰れば母に怒られる毎日だった。というのもサッカーは制服を着たまま革靴でやるので、それらが全部泥だらけになったまま家に帰るからだ。それがただの泥ならいいのだが、そこにはたまに何かしらの動物の糞がついていたりした。カモであれば匂いは全然しないのだが、雑食のキツネだった場合が最悪で... あとは詳しくは書きませんが、簡単にいうと男子中学生がやりそうなことをみんなでしてました。
汚い話は置いといて、二日目の学校の放課後ちょうど帰宅する前、ジョージといういかにもフッカーをやっていそうな友達が声をかけてくれた。(以下すべて倉橋による和訳)
「そういえばさ、明日ラグビーやらない?」
「明日?土曜日に?」
「そう、みんなやってるよ!」
「え、どこで?」
「ここで、明日9時に来て!」
「ここ?わかった、考えとく。」
ラグビーなんてやったことないどころか見たことないし、ルールは前に投げてはいけないということくらいしか知らなかった。情報はジョージがくれたものだけで半信半疑だったが両親と相談した結果とりあえず行って見学することにした。
そしてまた次の日、前の日に話をしていた場所に行ったら本当に人が集まっていた。みんな学校の体育着を着用して集まっているなか、自分一人だけ私服で行ったせいでめちゃくちゃ浮いてしまった。そして先生に目をつけられる。
「おう、君新しい生徒か?」
「あ、はい」
「誰か知っているか?」
「一応そこにいるオリーとかジョージとか…」
「その格好はなんだ?早く着替えて入りな!」
マジか。見学という概念は存在しないらしい。見学しようと思っていたものの運動着を持って行っていて助かった。そしてさらに前日に父にタックルの仕方とかされ方とかの基本を教えてもらったのも助かった。別に強豪というわけでもなく練習がきついというわけでもなかったので初心者の僕からしてみればちょうどよかった。しかも学校のチームだったからか次の週の試合でも少しばかりのプレータイムをもらえた。そんなこんなで週一の練習と試合という楽しいラグビー生活が始まった。
そんな僕がラグビーを始めた数週間後、タイミングよく2015年のワールドカップが始まった。衝撃を受けたのは開幕戦のイングランド対フィジー。そこで初めてラグビーがどんなスポーツかなんとなくわかった気がした。これまた逆張りと言われることを承知のうえで正直なことを言うと日本が南アフリカを破った試合よりも心に残っている。もちろん日本対南アフリカも感動したが、その前の弱かった時代を知らないうえに南アフリカの強さも知らない僕からしてみれば隣で父が泣き叫んでいる理由もわからないし行く先々で日本人である僕に対して「よくやった!」と褒めてくる人たちがよくわからなかった。
ワールドカップほど試合数が多く、ラグビーの楽しさを知るための教科書は存在しないわけで、ラグビーを始めてから一ヶ月ほどですっかり学校でのラグビーの話についていけるようになり、チームでもスタメンをとれるようになった。それから勝っても負けても楽しめるようになり、いいプレーをするとみんなから忍者だとか侍だとか呼ばれたことはいい思い出だ。
稚拙な文章でしたが、僕がラグビーを始めた流れはまさにこんな感じでした。これですっかりラグビー好きになったわけですが、再びラグビーをやる機会が訪れたのは大学に入った後でした。それについては残る2回のリレー日記のどちらかで書くと思います。
次は僕の同期の桑田でさえ弟みたいだと言った新2年の武村にバトンを渡します。彼は元気がよく純粋な人間ですが、だからこそ辻のような先輩にはくっつきすぎない方がいいと思います。
ポルトガル[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2023/11/14(火) 17:47
いつも仕事が速いみくちゃんからバトンを受け取りました3年の倉橋です。どれだけ速いかというと、写真のアップロードが「史上最速か!!」と思うほど(僕の体感)速いです。しかし彼女は仕事が速いだけでなく話しかけてみるとなんとなく面白いので、まだ仲良くなりきれていないプレイヤーのみなさんは是非話してみるといいです。
優しい素敵な先輩という紹介を頂きましたが、このような紹介はこれで2回連続なので僕はおそらく本当に優しく素敵な先輩なのでしょう。このようなことを書いてくれるような仲間たちに囲まれているなんて僕は幸せです。
さて、いきなりですが僕は今年の春から新たな趣味ができました。ポルトガル語です。僕がポルトガル語を勉強しているというと「それ意味あるの?」とか「ああそれやめた方がいい」とかいろいろと心ない言葉をかけられてしまうことがありますが、そういう人に限って英語すらできない人が多いのでそういう人たちにはポルトガル語のことを悪く言う前に英語を勉強してほしいです。今回はそんな人もそうでない人にもポルトガル語とその母国であるポルトガルの魅力についてたっぷりとお届けします。
まず、ポルトガル語はどんな言語なのか。ポルトガル語は言語学的にはロマンス諸語に分類されます。要はラテン語から派生しているわけですが、ローマ人が来る前のイベリア半島にはケルト人はいて、その後もイスラム勢力に支配された時期もあったので、それらの影響も強く受けてます。同じ背景を持つスペイン語とはだいぶ似ているのでスペイン語に触れたことがある人にはポルトガル語は理解しやすいでしょう。
その後ポルトガル語はポルトガルの大航海時代の反映によって世界中に普及しています。現代では英語が国際的な共通語の役割を果たしていますが、この時代ではポルトガル語が異国間の交流で使われていました。結局は現在がそうであるように英語が世界的に普及しますが、ポルトガルの植民地では引き続きポルトガル語は使われ続け、現在に至ります。ポルトガルが旧宗主国というような国ではブラジルが一番有名ですが、実はブラジル以外にもアフリカやアジアなど世界中でちらほら使われています。そんな国に行くことがあったら僕を通訳として連れて行くことをおすすめします(自分や自分に近い人がギニアビサウや東ティモールに行く未来は見えませんが)。
ポルトガル語と一口に言っても実はポルトガルとブラジルでは大きく違うようです。それもイギリス英語とアメリカ英語やスペインのスペイン語とラテンアメリカのスペイン語が違うのとはわけが違うくらい違います。発音や言葉遣いが異なるのはもちろん、文の構造までもが違ったりするようです(詳しくはまだわかりませんが)。また、ポルトガルではそんなことないのですが、ブラジルでは書き言葉と話し言葉が違いすぎて大学入試では書き言葉をちゃんと読むことができるかを見る試験があるほど。ブラジルのサッカー選手などで文字が読めない人がいる話を聞いたことありますが、こんなに複雑だったら文字を読めない人がいても不思議ではありません。
最近勉強していて少しおもしろいと感じたのはポルトガル語では1週間の曜日を数詞を使って表すことです。なんとヨーロッパでこんなことをしているのはポルトガル語だけなんです。他はみんな天体にちなんで月火水木金土日なのにポルトガル語だけ日曜日、23456日目、土曜日というふうに表します。こっちの方が自然な気もしますが。日曜から金曜まではキリスト教における天地創造の日にちから来ていて土曜日だけヘブライ語の安息日から来ています。もともと月火水木金というのは古代ローマで使われていた呼称なのですが、キリスト教世界になったときにキリスト教風に数字で表したのがなぜかポルトガル語だけで残ったようです。
ポルトガルでスポーツといえばサッカーですが、ポルトガルのサッカーの魅力は僕が説明するまでもないので、今回はラグビーについて紹介します。もしポルトガルのサッカーがクリスティアーノロナウドだけだと思っている人がいたら後で個人的に僕に聞いてください。
ラグビーの代表の愛称は’Os Lobos’、「狼」。今年は2007年以来のワールドカップ出場ということで脚光を浴びました。さらに最終節でフィジー相手にワールドカップ初勝利をあげたことが話題になりました。しかしフィジー戦までにもウェールズやオーストラリアに善戦をし、ジョージアとは最後のプレーまで激闘を繰り広げていたので、フィジー戦の勝利はおかしなことではないと感じました。それもボールを展開し、どんどん前に出て行く観客を魅了するようなラグビーをするので、見ていて楽しかったです。
驚きなのは彼らの多くはアマチュアやセミプロでやっていることです。キャプテンがリスボンの歯科医であるだけでなく、他の選手でもパン屋や肉屋など副業をしながらラグビーをやっている選手が多いです。そのようなチームが世界的な選手たちが揃うチーム相手と対等に戦えているのを見ると勇気をたくさんもらえます。
数年前までは欧州ラグビーチャンピオンシップ(シックスネーションズの一つ下のカテゴリー)の下のカテゴリーにいたのに急激に力をつけてきたのは感心しました。この躍進の裏には若手の存在が挙げられます。2007年にポルトガルが初めてワールドカップに出場したときの代表チームを子供の頃に見た世代が影響を受けてラグビーをやってきたのです。そして彼らの多くはまだ20代前半なのでこれからの躍進にも期待していきたいです。
こんなにポルトガルの話をしていたらポルトガルに行きたくなってしまいました。そのうちラグビー部を卒部して暇な時に同期を何人か連れて行ってみたいです。全員で、と言いたいところですが、静岡に行った時でさえみんなバラバラに行動をしてしまったので、ポルトガルに行ったらバラバラになるだけでなくそもそも日本に帰って来れなくなっちゃう人が続出しそうで怖いです。それまでは神泉や代々木八幡にあるポルトガル料理を玉代勢さんと楽しみたいと思います。予習も兼ねて。
次は同期の塩谷にバトンを渡します。
彼は背中が大きいです。そして、強いです。3年前にお互い新歓をされている時に新歓飯を(なぜか)二人で食べに行ったのですが、スタッフになることに興味があると言っていました。プレーヤーになってくれてよかったです。
優しい素敵な先輩という紹介を頂きましたが、このような紹介はこれで2回連続なので僕はおそらく本当に優しく素敵な先輩なのでしょう。このようなことを書いてくれるような仲間たちに囲まれているなんて僕は幸せです。
さて、いきなりですが僕は今年の春から新たな趣味ができました。ポルトガル語です。僕がポルトガル語を勉強しているというと「それ意味あるの?」とか「ああそれやめた方がいい」とかいろいろと心ない言葉をかけられてしまうことがありますが、そういう人に限って英語すらできない人が多いのでそういう人たちにはポルトガル語のことを悪く言う前に英語を勉強してほしいです。今回はそんな人もそうでない人にもポルトガル語とその母国であるポルトガルの魅力についてたっぷりとお届けします。
まず、ポルトガル語はどんな言語なのか。ポルトガル語は言語学的にはロマンス諸語に分類されます。要はラテン語から派生しているわけですが、ローマ人が来る前のイベリア半島にはケルト人はいて、その後もイスラム勢力に支配された時期もあったので、それらの影響も強く受けてます。同じ背景を持つスペイン語とはだいぶ似ているのでスペイン語に触れたことがある人にはポルトガル語は理解しやすいでしょう。
その後ポルトガル語はポルトガルの大航海時代の反映によって世界中に普及しています。現代では英語が国際的な共通語の役割を果たしていますが、この時代ではポルトガル語が異国間の交流で使われていました。結局は現在がそうであるように英語が世界的に普及しますが、ポルトガルの植民地では引き続きポルトガル語は使われ続け、現在に至ります。ポルトガルが旧宗主国というような国ではブラジルが一番有名ですが、実はブラジル以外にもアフリカやアジアなど世界中でちらほら使われています。そんな国に行くことがあったら僕を通訳として連れて行くことをおすすめします(自分や自分に近い人がギニアビサウや東ティモールに行く未来は見えませんが)。
ポルトガル語と一口に言っても実はポルトガルとブラジルでは大きく違うようです。それもイギリス英語とアメリカ英語やスペインのスペイン語とラテンアメリカのスペイン語が違うのとはわけが違うくらい違います。発音や言葉遣いが異なるのはもちろん、文の構造までもが違ったりするようです(詳しくはまだわかりませんが)。また、ポルトガルではそんなことないのですが、ブラジルでは書き言葉と話し言葉が違いすぎて大学入試では書き言葉をちゃんと読むことができるかを見る試験があるほど。ブラジルのサッカー選手などで文字が読めない人がいる話を聞いたことありますが、こんなに複雑だったら文字を読めない人がいても不思議ではありません。
最近勉強していて少しおもしろいと感じたのはポルトガル語では1週間の曜日を数詞を使って表すことです。なんとヨーロッパでこんなことをしているのはポルトガル語だけなんです。他はみんな天体にちなんで月火水木金土日なのにポルトガル語だけ日曜日、23456日目、土曜日というふうに表します。こっちの方が自然な気もしますが。日曜から金曜まではキリスト教における天地創造の日にちから来ていて土曜日だけヘブライ語の安息日から来ています。もともと月火水木金というのは古代ローマで使われていた呼称なのですが、キリスト教世界になったときにキリスト教風に数字で表したのがなぜかポルトガル語だけで残ったようです。
ポルトガルでスポーツといえばサッカーですが、ポルトガルのサッカーの魅力は僕が説明するまでもないので、今回はラグビーについて紹介します。もしポルトガルのサッカーがクリスティアーノロナウドだけだと思っている人がいたら後で個人的に僕に聞いてください。
ラグビーの代表の愛称は’Os Lobos’、「狼」。今年は2007年以来のワールドカップ出場ということで脚光を浴びました。さらに最終節でフィジー相手にワールドカップ初勝利をあげたことが話題になりました。しかしフィジー戦までにもウェールズやオーストラリアに善戦をし、ジョージアとは最後のプレーまで激闘を繰り広げていたので、フィジー戦の勝利はおかしなことではないと感じました。それもボールを展開し、どんどん前に出て行く観客を魅了するようなラグビーをするので、見ていて楽しかったです。
驚きなのは彼らの多くはアマチュアやセミプロでやっていることです。キャプテンがリスボンの歯科医であるだけでなく、他の選手でもパン屋や肉屋など副業をしながらラグビーをやっている選手が多いです。そのようなチームが世界的な選手たちが揃うチーム相手と対等に戦えているのを見ると勇気をたくさんもらえます。
数年前までは欧州ラグビーチャンピオンシップ(シックスネーションズの一つ下のカテゴリー)の下のカテゴリーにいたのに急激に力をつけてきたのは感心しました。この躍進の裏には若手の存在が挙げられます。2007年にポルトガルが初めてワールドカップに出場したときの代表チームを子供の頃に見た世代が影響を受けてラグビーをやってきたのです。そして彼らの多くはまだ20代前半なのでこれからの躍進にも期待していきたいです。
こんなにポルトガルの話をしていたらポルトガルに行きたくなってしまいました。そのうちラグビー部を卒部して暇な時に同期を何人か連れて行ってみたいです。全員で、と言いたいところですが、静岡に行った時でさえみんなバラバラに行動をしてしまったので、ポルトガルに行ったらバラバラになるだけでなくそもそも日本に帰って来れなくなっちゃう人が続出しそうで怖いです。それまでは神泉や代々木八幡にあるポルトガル料理を玉代勢さんと楽しみたいと思います。予習も兼ねて。
次は同期の塩谷にバトンを渡します。
彼は背中が大きいです。そして、強いです。3年前にお互い新歓をされている時に新歓飯を(なぜか)二人で食べに行ったのですが、スタッフになることに興味があると言っていました。プレーヤーになってくれてよかったです。
訪秋[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2023/05/08(月) 17:33
いつもそのチャーミングな笑顔で人々を魅了するゆいちゃんからバトンを受け取りました、3年の倉橋です。そんなゆいちゃんのことを好きになってしまう人がいても不思議ではありません。ゆいちゃんは僕のことを大人っぽいだの男っぽいだの書いていましたが、僕の頭の中はそんなことないのでもっとお互いのことを知るためにももっと話したいです。
いきなりですが、僕は旅に出ることが好きです。今回のゴールデンウィークは合宿のためにどこかに行けるわけではありませんが、何日か連続のオフがあるときは毎回旅行を画策しています。これまでのオフでは京都、八丈島、淡路島、札幌、福岡、熊本と、全国各地に行きました。そのうちラグビー部を引退したら南米一周とかしてみたいものです。それまでにスペイン語とポルトガル語をマスターしなければ、、、オフがない時はない時で地図や写真を見ながら想像を膨らませています。バーチャル旅行といったところでしょうか。実際に行くのと比べたら屁でもないですけど意外と楽しいものです。
そんなこんなで今回のリレー日記は3月のオフを利用して行った秋田について書こうと思います。秋田といえば同期の礒崎が幼少期を過ごした地として有名ですが、それ以外秋田についての知識が乏しかったので、行ってみました。
初日、夜行バスで秋田駅に着いたら朝だった。朝7時前だからか駅のまわりは全然人がいない。駅のなかも全然人がいなかったうえに飲食店も空いてなかったので、市民市場に行って朝ごはんを食べた。朝ごはんの焼き魚定食を食べ終わったら駅の観光案内所に行けばレンタサイクルが無料で借りられることを調べてあったので、駅に向かった。しかし、なんとレンタサイクルは4月にならないと始まらないという。出鼻を挫かれた。そんなわけでこの日は歩きまくった。とりあえずこの日一番の目的地である秋田城跡に向かった。途中久保田城跡や秋田市民俗芸能伝承館、秋田市役所、八橋運動公園をよりながら。秋田市民芸能伝承館では小さい竿燈を持つ体験がおすすめ。一番大きい竿燈の重さは50キロにも及ぶらしい。どこもそこそこの距離があるのにいちいちバスを乗るほどの距離じゃないというのとそもそもどこに行ってもバスが一時間に一本くらいしかないから結局何時間も歩いてしまった。
ついに秋田城跡にたどり着いた。なぜここに行きたかったというと古代の水洗トイレがあるからだ。実は秋田城は奈良時代に日本の北の玄関口として政治的にとても重要な役割を担っていたらしく、当時の最先端の技術があらゆるものに使われていた。トイレからは当時外国人しか食べなかった豚肉などに特有の寄生虫の化石が発見されており、国際交流が盛んだったことがうかがえる。だがしかし、ここの水洗トイレも4月にならないと公開されないという。仕方なしに資料館だけまわって知識を深めた。
少し歩いたらポートタワーセリオンに着いた。おそらく秋田で一番高い建物。ここの名物だといううどんの自動販売機でうどんを食べようかと考えていた。なんと自動であつあつのうどんを作ってくれるらしい。でもなぜかどこにも見つからない。まさか、と思ったがそのまさかだった。ここ50年間休みなしにうどんを販売し続けた自販機がその2週間だけ修理に出されていたのだ。仕方なく駅の近くまで戻ってご飯を食べることにした。そこで調べておいた居酒屋に向かったらなんと月に2日しかない休みの日がその日だった。もうやってらんない。そんなわけ別の居酒屋で食べて飲んでいい気分。
ちなみにこの時点で泊まる宿がとれていなかった。というのも2日前に予約しようとしたらどのホテル予約サイトでもこの日に泊まれる部屋がなかったのだ。ホテルとか旅館の数は結構あるのに。しかも秋田で観光客らしき人が全然見当たらない。なんでやねん。結局この日は人生で初めてネカフェに泊まったのだが、思った以上に快適だった。後から母にネカフェに泊まったことを言ったら「そんなところに泊まって襲われなかった?」とかなり心配されたが、別にネカフェはそんなことがよくあるわけでもないし、いくらそういう人がいたとしても立派な髭を生やしてる餃子耳の人は襲わないでしょ。
日が変わって二日目。この日はドライブ。まず男鹿半島に行った。とりあえず男鹿半島と八郎潟干拓地を一望できる展望台に行った。世界三景と書いてある。そんなわけ。たしかに景色はいいけど世界中の景色と比べて三本の指に入るか?ツッコミはこれくらいにしておいて、その後は男鹿半島一周してからナマハゲ館に行った。ナマハゲは漢の武帝が男鹿半島にわざわざ漢から連れてきたらしい。まじで意味わからん。ツッコミどころしかない。そんなことはさておきナマハゲ館ではナマハゲ体験ができる。僕はしてないけど。ナマハゲに襲われる体験ができるこのイベントこそナマハゲ館の最大の強みだという。
それを体験せずに向かった次の目的地が伊勢堂岱遺跡だった。ここは実は縄文時代の環状列石がある世界遺産だ。もはや言う必要はないかもしれないがここもまた4月下旬まで公開されない。だがここの資料館はそんなことがどうでもいいくらいよかった。特に精巧に作られたジオラマがポイント。ぜひ秋田に行くときはみなさんもここに寄ってください。
夜は秋田に戻ってきりたんぽ。人生初のきりたんぽにわくわくしていたのだが、入ったお店がきりたんぽを注文した人に紙芝居を披露するところだった。いざ紙芝居が始まったら全部秋田弁。何も理解できなかった。友達はみんな理解できたとか。「そりゃ日本語なんだからわかるよ~」悔しい。
三日目は角館と田沢湖へ。内陸の方へいくと雪が多少残っていた。そんなこともあり、武家屋敷と枝垂れ桜で有名な角館だが、桜は一輪も咲いていなかった。桜の満開は例年4月の下旬。本当に行く時期を間違えた。その後に行った田沢湖は息を呑むような美しさだった。天気がよかったのもあるが。浅いところはカリブ海のような色をしていたのでつい入りたくなってしまい足だけ入ったが、信じられないほど冷たかった。せっかくなのでここでその時の写真を一枚。

ここまでたらたらと自分の秋田旅行について書いてしまいましたが、全体的にはいいところだったので旅行先としてみなさんにおすすめします。ただ、3月よりは4月下旬のほうがいろいろと見られてよいかと思います。
次は合宿で塩谷とともに完投賞を受賞したげんとにバトンを渡します。いつもスクラムやモールで相手を圧倒し続けながらもフル出場を続ける彼らには頭が上がりません。フィールドの内外できついときに頼ってくれるように僕もこれからより一層の頑張りをしていきたいです。
いきなりですが、僕は旅に出ることが好きです。今回のゴールデンウィークは合宿のためにどこかに行けるわけではありませんが、何日か連続のオフがあるときは毎回旅行を画策しています。これまでのオフでは京都、八丈島、淡路島、札幌、福岡、熊本と、全国各地に行きました。そのうちラグビー部を引退したら南米一周とかしてみたいものです。それまでにスペイン語とポルトガル語をマスターしなければ、、、オフがない時はない時で地図や写真を見ながら想像を膨らませています。バーチャル旅行といったところでしょうか。実際に行くのと比べたら屁でもないですけど意外と楽しいものです。
そんなこんなで今回のリレー日記は3月のオフを利用して行った秋田について書こうと思います。秋田といえば同期の礒崎が幼少期を過ごした地として有名ですが、それ以外秋田についての知識が乏しかったので、行ってみました。
初日、夜行バスで秋田駅に着いたら朝だった。朝7時前だからか駅のまわりは全然人がいない。駅のなかも全然人がいなかったうえに飲食店も空いてなかったので、市民市場に行って朝ごはんを食べた。朝ごはんの焼き魚定食を食べ終わったら駅の観光案内所に行けばレンタサイクルが無料で借りられることを調べてあったので、駅に向かった。しかし、なんとレンタサイクルは4月にならないと始まらないという。出鼻を挫かれた。そんなわけでこの日は歩きまくった。とりあえずこの日一番の目的地である秋田城跡に向かった。途中久保田城跡や秋田市民俗芸能伝承館、秋田市役所、八橋運動公園をよりながら。秋田市民芸能伝承館では小さい竿燈を持つ体験がおすすめ。一番大きい竿燈の重さは50キロにも及ぶらしい。どこもそこそこの距離があるのにいちいちバスを乗るほどの距離じゃないというのとそもそもどこに行ってもバスが一時間に一本くらいしかないから結局何時間も歩いてしまった。
ついに秋田城跡にたどり着いた。なぜここに行きたかったというと古代の水洗トイレがあるからだ。実は秋田城は奈良時代に日本の北の玄関口として政治的にとても重要な役割を担っていたらしく、当時の最先端の技術があらゆるものに使われていた。トイレからは当時外国人しか食べなかった豚肉などに特有の寄生虫の化石が発見されており、国際交流が盛んだったことがうかがえる。だがしかし、ここの水洗トイレも4月にならないと公開されないという。仕方なしに資料館だけまわって知識を深めた。
少し歩いたらポートタワーセリオンに着いた。おそらく秋田で一番高い建物。ここの名物だといううどんの自動販売機でうどんを食べようかと考えていた。なんと自動であつあつのうどんを作ってくれるらしい。でもなぜかどこにも見つからない。まさか、と思ったがそのまさかだった。ここ50年間休みなしにうどんを販売し続けた自販機がその2週間だけ修理に出されていたのだ。仕方なく駅の近くまで戻ってご飯を食べることにした。そこで調べておいた居酒屋に向かったらなんと月に2日しかない休みの日がその日だった。もうやってらんない。そんなわけ別の居酒屋で食べて飲んでいい気分。
ちなみにこの時点で泊まる宿がとれていなかった。というのも2日前に予約しようとしたらどのホテル予約サイトでもこの日に泊まれる部屋がなかったのだ。ホテルとか旅館の数は結構あるのに。しかも秋田で観光客らしき人が全然見当たらない。なんでやねん。結局この日は人生で初めてネカフェに泊まったのだが、思った以上に快適だった。後から母にネカフェに泊まったことを言ったら「そんなところに泊まって襲われなかった?」とかなり心配されたが、別にネカフェはそんなことがよくあるわけでもないし、いくらそういう人がいたとしても立派な髭を生やしてる餃子耳の人は襲わないでしょ。
日が変わって二日目。この日はドライブ。まず男鹿半島に行った。とりあえず男鹿半島と八郎潟干拓地を一望できる展望台に行った。世界三景と書いてある。そんなわけ。たしかに景色はいいけど世界中の景色と比べて三本の指に入るか?ツッコミはこれくらいにしておいて、その後は男鹿半島一周してからナマハゲ館に行った。ナマハゲは漢の武帝が男鹿半島にわざわざ漢から連れてきたらしい。まじで意味わからん。ツッコミどころしかない。そんなことはさておきナマハゲ館ではナマハゲ体験ができる。僕はしてないけど。ナマハゲに襲われる体験ができるこのイベントこそナマハゲ館の最大の強みだという。
それを体験せずに向かった次の目的地が伊勢堂岱遺跡だった。ここは実は縄文時代の環状列石がある世界遺産だ。もはや言う必要はないかもしれないがここもまた4月下旬まで公開されない。だがここの資料館はそんなことがどうでもいいくらいよかった。特に精巧に作られたジオラマがポイント。ぜひ秋田に行くときはみなさんもここに寄ってください。
夜は秋田に戻ってきりたんぽ。人生初のきりたんぽにわくわくしていたのだが、入ったお店がきりたんぽを注文した人に紙芝居を披露するところだった。いざ紙芝居が始まったら全部秋田弁。何も理解できなかった。友達はみんな理解できたとか。「そりゃ日本語なんだからわかるよ~」悔しい。
三日目は角館と田沢湖へ。内陸の方へいくと雪が多少残っていた。そんなこともあり、武家屋敷と枝垂れ桜で有名な角館だが、桜は一輪も咲いていなかった。桜の満開は例年4月の下旬。本当に行く時期を間違えた。その後に行った田沢湖は息を呑むような美しさだった。天気がよかったのもあるが。浅いところはカリブ海のような色をしていたのでつい入りたくなってしまい足だけ入ったが、信じられないほど冷たかった。せっかくなのでここでその時の写真を一枚。

ここまでたらたらと自分の秋田旅行について書いてしまいましたが、全体的にはいいところだったので旅行先としてみなさんにおすすめします。ただ、3月よりは4月下旬のほうがいろいろと見られてよいかと思います。
次は合宿で塩谷とともに完投賞を受賞したげんとにバトンを渡します。いつもスクラムやモールで相手を圧倒し続けながらもフル出場を続ける彼らには頭が上がりません。フィールドの内外できついときに頼ってくれるように僕もこれからより一層の頑張りをしていきたいです。
| 次へ>> |
2025年12月
| <<前月 | 翌月>> |
| |
| |
| |
アーカイブ
- 2025年12月(2)
- 2025年11月(12)
- 2025年10月(13)
- 2025年9月(11)
- 2025年8月(11)
- 2025年7月(11)
- 2025年6月(10)
- 2025年5月(8)
- 2025年4月(9)
- 2025年3月(9)
- 2025年2月(15)
- 2025年1月(2)
- 2024年12月(18)
- 2024年11月(12)
- 2024年10月(12)
- 2024年9月(13)
- 2024年8月(11)
- 2024年7月(12)
- 2024年6月(8)
- 2024年5月(9)
- 2024年4月(8)
- 2024年3月(8)
- 2024年2月(19)
- 2024年1月(7)
- 2023年12月(9)
- 2023年11月(12)
- 2023年10月(11)
- 2023年9月(12)
- 2023年8月(11)
- 2023年7月(11)
- 2023年6月(8)
- 2023年5月(7)
- 2023年4月(8)
- 2023年3月(7)
- 2023年2月(15)
- 2023年1月(7)
- 2022年12月(23)
- 2022年11月(14)
- 2022年10月(13)
- 2022年9月(14)
- 2022年8月(14)
- 2022年7月(16)
- 2022年6月(10)
- 2022年5月(11)
- 2022年4月(12)
- 2022年3月(10)
- 2022年2月(15)
- 2022年1月(4)
- 2021年12月(12)
- 2021年11月(12)
- 2021年10月(14)
- 2021年9月(12)
- 2021年8月(12)
- 2021年7月(12)
- 2021年6月(11)
- 2021年5月(12)
- 2021年4月(11)
- 2021年3月(13)
- 2021年2月(10)
- 2021年1月(21)
- 2020年12月(11)
- 2020年11月(12)
- 2020年10月(13)
- 2020年9月(12)
- 2020年8月(14)
- 2020年7月(12)
- 2020年6月(12)
- 2020年5月(13)
- 2020年4月(12)
- 2020年3月(13)
- 2020年2月(12)
- 2020年1月(4)
- 2019年12月(10)
- 2019年11月(15)
- 2019年10月(11)
- 2019年9月(13)
- 2019年8月(13)
- 2019年7月(10)
- 2019年6月(8)
- 2019年5月(13)
- 2019年4月(7)
- 2019年3月(7)
- 2019年2月(5)
- 2019年1月(7)
- 2018年12月(15)
- 2018年11月(12)
- 2018年10月(15)
- 2018年9月(10)
- 2018年8月(7)
- 2018年7月(6)
- 2018年6月(10)
- 2018年5月(12)
- 2018年4月(11)
- 2018年3月(5)
- 2017年12月(11)
- 2017年11月(13)
- 2017年10月(12)
- 2017年9月(11)
- 2017年8月(12)
- 2017年7月(10)
- 2017年6月(10)
- 2017年5月(17)
- 2017年4月(10)
- 2017年3月(13)
- 2017年2月(4)
- 2016年12月(15)
- 2016年11月(12)
- 2016年10月(14)
- 2016年9月(12)
- 2016年8月(12)
- 2016年7月(15)
- 2016年6月(9)
- 2016年5月(9)
- 2016年4月(11)
- 2016年3月(10)
- 2016年2月(7)
- 2015年12月(8)
- 2015年11月(11)
- 2015年10月(10)
- 2015年9月(10)
- 2015年8月(5)
- 2015年7月(7)
- 2015年6月(11)
- 2015年5月(13)
- 2015年4月(8)
- 2015年3月(9)
- 2015年2月(12)
- 2015年1月(11)
- 2014年12月(12)
- 2014年11月(10)
- 2014年10月(12)
- 2014年9月(12)
- 2014年8月(12)
- 2014年7月(6)
- 2014年6月(5)
- 2014年5月(13)
- 2014年4月(11)
- 2014年3月(14)
- 2014年2月(7)
- 2013年12月(23)
- 2013年11月(29)
- 2013年10月(32)
- 2013年9月(30)
- 2013年8月(14)
- 2013年7月(15)
- 2013年6月(23)
- 2013年5月(33)
- 2013年4月(27)
- 2013年3月(20)
- 2013年2月(10)
- 2013年1月(1)
- 2012年12月(13)
- 2012年11月(11)
- 2012年10月(24)
- 2012年9月(13)
- 2012年8月(9)
- 2012年7月(5)
- 2012年6月(8)
- 2012年5月(11)
- 2012年4月(9)
- 2012年3月(10)
- 2012年2月(8)
- 2011年12月(6)
- 2011年11月(6)
- 2011年10月(7)
- 2011年9月(9)
- 2011年8月(10)
- 2011年7月(5)
- 2011年6月(5)
- 2011年5月(9)
- 2011年4月(7)
- 2011年3月(8)
- 2011年2月(4)
ブログ最新記事
- タックルも人間も腰は低い方がカッコいい (12/15 19:00)
- パワーグリップの詩 (12/01 21:08)
- Marry Me Chicken (11/28 10:31)
- 愉快で最高な仲間たち (11/26 18:43)
- 男磨きはボディビルへ (11/25 16:43)
- fall season (11/22 22:18)
- 類まれな才能 (11/20 09:32)
- しんらい (11/19 23:02)
- あの坂田が!?!?泣いたアニメ (11/19 18:27)
- 埼玉旅行記 (11/16 18:05)
- 渋谷のサグラダ・ファミリア (11/15 20:40)
- 逆ナンなん? (11/13 16:34)
- バイト (11/12 10:31)
- モチーフで見る部員の部屋 (11/07 00:32)
- 自己開示 (10/31 13:42)
- ポスト考古学実習 (10/28 21:23)
- 白球に魅せられて (10/25 18:37)
- LoveType16 (10/25 11:46)
- 休みたい (10/25 07:09)
- No pain, no gain. (10/24 12:29)





.jpg)