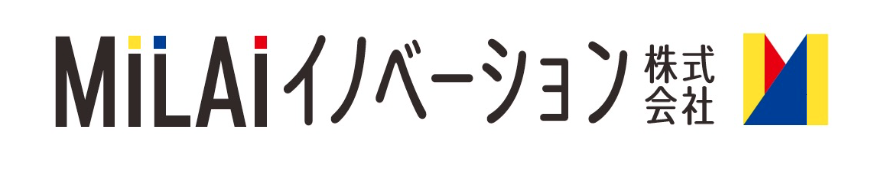ブログ 國枝 健さんが書いた記事
| <<前へ |
コミュニケーション[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2020/11/15(日) 23:56
野田君からバトンをもらいました同じく2年の國枝です。彼は新歓委員でないのにも関わらず、一昨日、新歓委員の僕に、高校生への新歓活動についてのアイデアをわざわざ話に来てくれました。彼は本気で東大ラグビー部を強くしたいと考えていて、その姿勢には見習うべきところがあると常々思っています。彼が完全復帰してくれる日を待ち望んでいます。
つい先日、アマゾンプライムビデオで、「愛していると言ってくれ」というドラマを視聴した。1995年にTBSで放送されたドラマで、最高視聴率は28.1%。主題歌の「LOVE LOVE LOVE」はダブルミリオンを記録するなど(母いわく)当時はかなりの反響があったようだ。
正直、観始める前は、「ありがちな安い恋愛ドラマだろうし、つまらなかったらすぐやめよう」くらいの心持ちだったのだが、回を重ねるごとにのめりこんでしまい、結局、最終話まで夢中になって観てしまった。
ドラマは、聴覚に障がいを持つ画家(榊晃次)と女優の卵(水野紘子)のラブストーリーを大きな軸に据えている。もちろん豊川悦二演じる榊晃次は最高にハンサムだし、常盤貴子演じる水野紘子は最高に美しいし、キュンキュンするシーンもあるし、ストーリーの展開も面白いし、単純にラブストーリーとして十分に完成されているのだが、このドラマの最大の魅力は丁寧に描かれたコミュニケーションの部分にある。(と僕は思う。)
ドラマの中で、二人は、様々な形でコミュニケーションをとる。当時はまだポケベルが全盛期の時代なので、二人は、FAXを使ったり、時には手紙を送ったりと様々な方法で連絡を取り合う。当然、うまく連絡が取れずに、もどかしい思いをしたり、意思疎通がうまくいかずに行き違いが生じたりするのだが、そういった場面に二人の感情の機微があらわれる所がこのドラマの魅力の1つでもある。
また、基本的に二人は手話を通じて会話をするのだが、僕はこのドラマを見て手話という言語に、大きな魅力を感じた。手話は、同じ動作でも手を動かすスピードや力強さ、顔の表情の変化などで、感情の程度の違いが伝わるため、表現の幅がとても広い。また、声を出すことができない場所でも会話をすることができるという手話ならではの特性もある。
そして、このドラマ最大のおすすめポイントは、言葉では表現することのできない繊細な感情やメッセージを、言語以外の媒体を通じて相手に伝えるシーンの美しさである。このドラマは、人に何かを伝える、コミュニケーションをとる、ということが、いかに難しく、そして同時に、いかに素敵な営みであるかということを教えてくれる。
ところで、チームスポーツにおいて、良いコミュニケーションをとることは、勝利への必要条件である。とりわけラグビーは競技の特性上、コミュニケーションの質が勝負を大きく左右する。
先日の練習で、ヘッドコーチの深津さんが、「声を出すことは、相手に意思を伝える行為であると同時に、自分へのコミットメントでもある」とおっしゃっていたが、これはプレー中のコミュニケーションに関する本質的な指摘であると僕は思う。
例えば、試合で、体力のキツい時間帯に、ある選手が「最後まで走り切ろう」とチームを鼓舞する声を出したとする。これはもちろん、チームの他の選手を勇気付けることになるが、それと同時に、「最後まで走り切ろうと呼びかけた自分自身が走り切らなくてはいけない」と自らを奮い立たせることにもなる。
接点付近でパスを受ける選手が「放れ」と一言、言うだけでも、言わないのとでは全く違う。それはパサーにパスを受け取る意思とタイミングを伝えるのと同時に、「自分がパスを受け、強くヒットして何が何でも前に出る」という責任を自分に課すことにもなる。
辛いから、自信がないから声を出せないのではなくて、声を出すから踏ん張れる、声を出すことで自信や責任が生まれる、という逆転の関係がそこにはあるのかもしれない。
1つ1つの局面で、強いプレーを選択し続けるためには、チーム全員が積極的にコミュニケーションをとる意識を持つ必要がある。僕自身、まだまだ、コミュニケーションの部分で改善できる余地がたくさんある。スイカを着るためにも、日々の練習の中で常にコミニュケーションを取り続けることを意識していきたいと思う。
最後までお読みいただきありがとうございます。次は一年生の手島にバトンを渡したいと思います。彼は、体重86キロという恵まれた体格を持つだけでなく、ハンドリングのセンスもあって、さらにはフィットネスでも一年生でトップの結果を残しており、僕が大きく期待を寄せている新入生の一人です。彼の初試合が観れる日を心待ちにしています。
つい先日、アマゾンプライムビデオで、「愛していると言ってくれ」というドラマを視聴した。1995年にTBSで放送されたドラマで、最高視聴率は28.1%。主題歌の「LOVE LOVE LOVE」はダブルミリオンを記録するなど(母いわく)当時はかなりの反響があったようだ。
正直、観始める前は、「ありがちな安い恋愛ドラマだろうし、つまらなかったらすぐやめよう」くらいの心持ちだったのだが、回を重ねるごとにのめりこんでしまい、結局、最終話まで夢中になって観てしまった。
ドラマは、聴覚に障がいを持つ画家(榊晃次)と女優の卵(水野紘子)のラブストーリーを大きな軸に据えている。もちろん豊川悦二演じる榊晃次は最高にハンサムだし、常盤貴子演じる水野紘子は最高に美しいし、キュンキュンするシーンもあるし、ストーリーの展開も面白いし、単純にラブストーリーとして十分に完成されているのだが、このドラマの最大の魅力は丁寧に描かれたコミュニケーションの部分にある。(と僕は思う。)
ドラマの中で、二人は、様々な形でコミュニケーションをとる。当時はまだポケベルが全盛期の時代なので、二人は、FAXを使ったり、時には手紙を送ったりと様々な方法で連絡を取り合う。当然、うまく連絡が取れずに、もどかしい思いをしたり、意思疎通がうまくいかずに行き違いが生じたりするのだが、そういった場面に二人の感情の機微があらわれる所がこのドラマの魅力の1つでもある。
また、基本的に二人は手話を通じて会話をするのだが、僕はこのドラマを見て手話という言語に、大きな魅力を感じた。手話は、同じ動作でも手を動かすスピードや力強さ、顔の表情の変化などで、感情の程度の違いが伝わるため、表現の幅がとても広い。また、声を出すことができない場所でも会話をすることができるという手話ならではの特性もある。
そして、このドラマ最大のおすすめポイントは、言葉では表現することのできない繊細な感情やメッセージを、言語以外の媒体を通じて相手に伝えるシーンの美しさである。このドラマは、人に何かを伝える、コミュニケーションをとる、ということが、いかに難しく、そして同時に、いかに素敵な営みであるかということを教えてくれる。
ところで、チームスポーツにおいて、良いコミュニケーションをとることは、勝利への必要条件である。とりわけラグビーは競技の特性上、コミュニケーションの質が勝負を大きく左右する。
先日の練習で、ヘッドコーチの深津さんが、「声を出すことは、相手に意思を伝える行為であると同時に、自分へのコミットメントでもある」とおっしゃっていたが、これはプレー中のコミュニケーションに関する本質的な指摘であると僕は思う。
例えば、試合で、体力のキツい時間帯に、ある選手が「最後まで走り切ろう」とチームを鼓舞する声を出したとする。これはもちろん、チームの他の選手を勇気付けることになるが、それと同時に、「最後まで走り切ろうと呼びかけた自分自身が走り切らなくてはいけない」と自らを奮い立たせることにもなる。
接点付近でパスを受ける選手が「放れ」と一言、言うだけでも、言わないのとでは全く違う。それはパサーにパスを受け取る意思とタイミングを伝えるのと同時に、「自分がパスを受け、強くヒットして何が何でも前に出る」という責任を自分に課すことにもなる。
辛いから、自信がないから声を出せないのではなくて、声を出すから踏ん張れる、声を出すことで自信や責任が生まれる、という逆転の関係がそこにはあるのかもしれない。
1つ1つの局面で、強いプレーを選択し続けるためには、チーム全員が積極的にコミュニケーションをとる意識を持つ必要がある。僕自身、まだまだ、コミュニケーションの部分で改善できる余地がたくさんある。スイカを着るためにも、日々の練習の中で常にコミニュケーションを取り続けることを意識していきたいと思う。
最後までお読みいただきありがとうございます。次は一年生の手島にバトンを渡したいと思います。彼は、体重86キロという恵まれた体格を持つだけでなく、ハンドリングのセンスもあって、さらにはフィットネスでも一年生でトップの結果を残しており、僕が大きく期待を寄せている新入生の一人です。彼の初試合が観れる日を心待ちにしています。
Memento Mori[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2020/08/23(日) 12:47
勉強も部活も一生懸命で、真面目で頑張り屋さんのゆきちゃんからバトンを受け取りました、2年プレイヤーの國枝です。彼女を見て背筋が伸びる思いがするのはきっと僕だけではないはずです。僕も、彼女のように、図書館が似合う大人な大学生になりたいなと密かに思っています。
人間万事塞翁が馬。
コロナウイルスの蔓延は私たち大学生のキャンパスライフを綺麗さっぱり奪い去ってしまった訳であるが、長い自粛生活の中にも新たな出会い、発見があった。
読書やラジオを楽しむ習慣が戻ったのは小学生の時以来であったし、余りある時間を使って新しいアーティストを開拓することもできた。
中でも、ロックバンド andymori との出会いは『革命』的であった。
andymori は2007年の結成から、2014年の解散までの約7年間を『すごい速さ』で駆け抜けた3人組のロックバンドである。
彼らの音楽はとにかく自由で、(僕は全く楽器が引けないが)思わずギターをかき鳴らしてしまいたくなるような衝動的で勢いのある曲もあれば、どこか郷愁を感じさせるような美しい曲まで、実に多彩な音楽を奏でる。この素晴らしいバンドを紹介してくれた同期の三方君には本当に感謝している。
ところで、このandymoriという特徴的なバンド名はどこから来ているのか。
調べてみたところ、どうやら、ポップアーティスト、そしてロックバンドのプロデューサーとしても有名なAndy Warholのandyと、作家・写真家として活躍する藤原新也の作品『メメント・モリ』(Memento Mori)のmoriを掛け合わせてandymoriという言葉を作ったようである。
Memento Moriとは、ラテン語で、「死を想え」という意味の言葉である。Memento≒Memory Mori≒Mortal であるようなので、もう少し正確にいえば、「自分がいつか必ず死ぬということを覚えておけ」といったところだろうか。
“Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure — these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose.”
高校2年生の時、英語の先生が、授業の題材として、スティーブ・ジョブズのスタンフォード大学でのスピーチを取り上げたことがあった。高校時代、学業的には非常に不真面目な生徒だった僕も、その授業のことは強く印象に残っている。
ジョブズのスピーチの死に関する部分を一言でまとめるならば、まさに、Memento Moriである。自分がいつか必ず死ぬということを忘れるな。そうすることで、下らない自尊心や恥ずかしいといった一時の感情に囚われず、本当に自分にとって大切なことを見極めることができる。というメッセージである。Memento Mori に対する前向きな捉え方とも言えるかもしれない。
僕は今、東大ラグビー部でラグビーをしている。
入部してからの約1年間、それなりに努力はしてきた。
体重は10キロ以上増えたし、ウエイトの重量も順調に伸びた。未経験者として入部した去年の4月に比べればパスやキックも少しずつではあるが上達してきている。
先輩や同期には「上手くなったね」と褒めてくれる人がいる。
でも、今の僕は、本当に大切なこと、から遠ざかっている。
僕がラグビー部に入ったのは、純粋にラグビーを楽しみたかったから。
そして、今僕がラグビー部にいるのは、対抗戦にプレイヤーとして出場して、最高の瞬間を味わいたいから。
僕は、試合前に、最高にワクワクしたいし、自分・仲間のトライに最高に興奮したいし、勝利の瞬間に最高の喜びを味わいたい。だから、明日死ぬかもしれないのに、今日、ディズニーには行かずに、練習に行くし、カラオケにはいかずにジムに行く。根本には、そういう心持ちの自分がいるべきだ。
でも、今の自分はダメだ。
今の自分は、「対抗戦に出る」自分を全く意識できていない。
なんとなく、この一回の練習を乗り切ること。周りにダメなやつだと思われないようにミスなくプレーすること。そういうことに満足を覚えてしまっている。
その場しのぎ、自己保身、そんな下らないものばかりがインセンティブになってしまっている。
だから、いつも受動的にしか動くことができない。
覚えろと言われたから、サインを覚える。でも「どういう状況でそのサインが有効なのかを分析する」というもっと大事なことは、面倒だから、苦手だから、「とりあえず、今の練習ではやっていなくてもボロが出ないから」という理由で後回しにしてしまう。
未経験者として入部した1年目は、何もわからないことが当たり前で、戦術的な理解不足でミスをしても、先輩や同期は「未経験だから仕方がない」と言ってくれたし、僕もそれに甘えていた。でも、対抗戦の舞台では、ラグビー歴なんて何の言い訳にもならないし、「未経験で始めたわりに上手い」選手と呼ばれることが僕の目標ではない。であるならば、未経験者であるからこそ誰よりも貪欲に知識や戦術を吸収していかなければならないはずだ。それなのに今の僕は、「とりあえずみんなと同じことをやっておけばいいや」「最低限のことだけやっておけばいいや」とどこか逃げ腰のスタンスでいる。
このまま4年間を終えたとしても、多分それなりに満足感、達成感はあるだろうし、「やりきった」「頑張った」とそれなりに自分を肯定することもできるだろう。でも、きっと心のどこかで肯定しきれない自分がいる。そして、そんな自分に対して、「きっと、あれが限界だったんだよ」「次のステージで頑張ればいいじゃないか」と言い聞かせる自分がいるのだろう。
人生は一度きりで、決してやり直しがきかない。ごく当たり前のことなのに、日々の生活に追われていると、いつしかそのことを忘れてしまう。そして、なんとなく、1日を、それなりに充実させることで満足してしまう。
それは自然なことで、必ずしも悪いことではない。常に気張って生きるのは疲れるし、いちいち全てのことに、「これが本当にやりたいことだろうか」なんて考えていたら、何も手につかなくなってしまう。
でも、この4年間は、ラグビー、そして、対抗戦という、理屈を超えた、最高のワクワクと興奮を追いかけることのできるこの4年間くらいは、いつも楽な方へ、自分が傷つかない方へと逃げてしまう怠惰で弱気な自分に打ち勝ってみたい。
先日の練習中の大西さんや深津さんのお話、そして、今回のリレー日記は、自分を見つめ直す良いきっかけとなった。でも、きっと今の感情、情熱は何もしなければ、一週間もしないうちに消えてしまうだろうし、またいつもの弱い自分が顔を出すだろう。いつもそうやって口先だけで、結局、何も変わらないということを繰り返してきた。
だから、今日からは、具体的に行動・態度を変えていくだけでなく、毎日、少しだけでも、Memento Mori という言葉と向き合う時間を作ろうと思う。
次は、新入生の橋野にバトンを渡したいと思います。彼はパスが上手なだけでなく、50m走、6秒台前半の俊足の持ち主で、活躍が非常に楽しみな選手です。性格もとても真面目で、精神的にもチームに良い影響を与えてくれるのではないかと大きな期待を寄せています。
人間万事塞翁が馬。
コロナウイルスの蔓延は私たち大学生のキャンパスライフを綺麗さっぱり奪い去ってしまった訳であるが、長い自粛生活の中にも新たな出会い、発見があった。
読書やラジオを楽しむ習慣が戻ったのは小学生の時以来であったし、余りある時間を使って新しいアーティストを開拓することもできた。
中でも、ロックバンド andymori との出会いは『革命』的であった。
andymori は2007年の結成から、2014年の解散までの約7年間を『すごい速さ』で駆け抜けた3人組のロックバンドである。
彼らの音楽はとにかく自由で、(僕は全く楽器が引けないが)思わずギターをかき鳴らしてしまいたくなるような衝動的で勢いのある曲もあれば、どこか郷愁を感じさせるような美しい曲まで、実に多彩な音楽を奏でる。この素晴らしいバンドを紹介してくれた同期の三方君には本当に感謝している。
ところで、このandymoriという特徴的なバンド名はどこから来ているのか。
調べてみたところ、どうやら、ポップアーティスト、そしてロックバンドのプロデューサーとしても有名なAndy Warholのandyと、作家・写真家として活躍する藤原新也の作品『メメント・モリ』(Memento Mori)のmoriを掛け合わせてandymoriという言葉を作ったようである。
Memento Moriとは、ラテン語で、「死を想え」という意味の言葉である。Memento≒Memory Mori≒Mortal であるようなので、もう少し正確にいえば、「自分がいつか必ず死ぬということを覚えておけ」といったところだろうか。
“Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure — these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose.”
高校2年生の時、英語の先生が、授業の題材として、スティーブ・ジョブズのスタンフォード大学でのスピーチを取り上げたことがあった。高校時代、学業的には非常に不真面目な生徒だった僕も、その授業のことは強く印象に残っている。
ジョブズのスピーチの死に関する部分を一言でまとめるならば、まさに、Memento Moriである。自分がいつか必ず死ぬということを忘れるな。そうすることで、下らない自尊心や恥ずかしいといった一時の感情に囚われず、本当に自分にとって大切なことを見極めることができる。というメッセージである。Memento Mori に対する前向きな捉え方とも言えるかもしれない。
僕は今、東大ラグビー部でラグビーをしている。
入部してからの約1年間、それなりに努力はしてきた。
体重は10キロ以上増えたし、ウエイトの重量も順調に伸びた。未経験者として入部した去年の4月に比べればパスやキックも少しずつではあるが上達してきている。
先輩や同期には「上手くなったね」と褒めてくれる人がいる。
でも、今の僕は、本当に大切なこと、から遠ざかっている。
僕がラグビー部に入ったのは、純粋にラグビーを楽しみたかったから。
そして、今僕がラグビー部にいるのは、対抗戦にプレイヤーとして出場して、最高の瞬間を味わいたいから。
僕は、試合前に、最高にワクワクしたいし、自分・仲間のトライに最高に興奮したいし、勝利の瞬間に最高の喜びを味わいたい。だから、明日死ぬかもしれないのに、今日、ディズニーには行かずに、練習に行くし、カラオケにはいかずにジムに行く。根本には、そういう心持ちの自分がいるべきだ。
でも、今の自分はダメだ。
今の自分は、「対抗戦に出る」自分を全く意識できていない。
なんとなく、この一回の練習を乗り切ること。周りにダメなやつだと思われないようにミスなくプレーすること。そういうことに満足を覚えてしまっている。
その場しのぎ、自己保身、そんな下らないものばかりがインセンティブになってしまっている。
だから、いつも受動的にしか動くことができない。
覚えろと言われたから、サインを覚える。でも「どういう状況でそのサインが有効なのかを分析する」というもっと大事なことは、面倒だから、苦手だから、「とりあえず、今の練習ではやっていなくてもボロが出ないから」という理由で後回しにしてしまう。
未経験者として入部した1年目は、何もわからないことが当たり前で、戦術的な理解不足でミスをしても、先輩や同期は「未経験だから仕方がない」と言ってくれたし、僕もそれに甘えていた。でも、対抗戦の舞台では、ラグビー歴なんて何の言い訳にもならないし、「未経験で始めたわりに上手い」選手と呼ばれることが僕の目標ではない。であるならば、未経験者であるからこそ誰よりも貪欲に知識や戦術を吸収していかなければならないはずだ。それなのに今の僕は、「とりあえずみんなと同じことをやっておけばいいや」「最低限のことだけやっておけばいいや」とどこか逃げ腰のスタンスでいる。
このまま4年間を終えたとしても、多分それなりに満足感、達成感はあるだろうし、「やりきった」「頑張った」とそれなりに自分を肯定することもできるだろう。でも、きっと心のどこかで肯定しきれない自分がいる。そして、そんな自分に対して、「きっと、あれが限界だったんだよ」「次のステージで頑張ればいいじゃないか」と言い聞かせる自分がいるのだろう。
人生は一度きりで、決してやり直しがきかない。ごく当たり前のことなのに、日々の生活に追われていると、いつしかそのことを忘れてしまう。そして、なんとなく、1日を、それなりに充実させることで満足してしまう。
それは自然なことで、必ずしも悪いことではない。常に気張って生きるのは疲れるし、いちいち全てのことに、「これが本当にやりたいことだろうか」なんて考えていたら、何も手につかなくなってしまう。
でも、この4年間は、ラグビー、そして、対抗戦という、理屈を超えた、最高のワクワクと興奮を追いかけることのできるこの4年間くらいは、いつも楽な方へ、自分が傷つかない方へと逃げてしまう怠惰で弱気な自分に打ち勝ってみたい。
先日の練習中の大西さんや深津さんのお話、そして、今回のリレー日記は、自分を見つめ直す良いきっかけとなった。でも、きっと今の感情、情熱は何もしなければ、一週間もしないうちに消えてしまうだろうし、またいつもの弱い自分が顔を出すだろう。いつもそうやって口先だけで、結局、何も変わらないということを繰り返してきた。
だから、今日からは、具体的に行動・態度を変えていくだけでなく、毎日、少しだけでも、Memento Mori という言葉と向き合う時間を作ろうと思う。
次は、新入生の橋野にバトンを渡したいと思います。彼はパスが上手なだけでなく、50m走、6秒台前半の俊足の持ち主で、活躍が非常に楽しみな選手です。性格もとても真面目で、精神的にもチームに良い影響を与えてくれるのではないかと大きな期待を寄せています。
「杉井智哉」[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2020/04/10(金) 19:00
ラグビー部の恋愛博士こと財木くんから紹介に預かりました、國枝です。
中高時代、彼女はおろか、女性の友達すら1人もいなかった僕にとっては、
同じ男子校出身でありながら、高校時代に複数人の女性との交際歴があった彼と、
同じ 「男子校出身」 というカテゴリーで一括りにされることに対して、いつも強い憤りを覚えています。真の男子校生としてのプライドが疼くのです。
(共感できた新入生の方は相当まずいです。くだらないプライドは早く捨てましょう。さもないと僕のように暗黒の大学生活を送ることになります。)
彼の持つ自分への自信は、僕にはないものです。僕も彼のように、ラグビーに対して強い自信が持てるように、人一倍、練習に励んでいきたいと思っています。
杉井智哉。東京大学ラグビー部2年。
県立浦和高校ラグビー部出身で、ラグビーエリートであるところの彼は、
昨年、1年生でありながら、いち早くジュニアからシニアチームに合流し、
8月の慶應戦では、スタメンに選ばれ、
途中で鎖骨を骨折しながらもプレーし続けたという逸話を持つ、ワイルドな奴である。
しかし、普段の杉井智哉はラガーマンのイメージとはかけ離れたような言動をとる。
彼はいつも「ラグビーなんか早く辞めたいよ」とボヤくのだ。
確かに、
彼はきっちりと筋トレのノルマをこなしてはいるが、
「こんな時間があったら、家で寝転がりながらyoutube見てたいのに」
とラガーマンの風上にも置けないような愚痴をこぼしたり、
学食では大盛りのご飯に苦戦しながら、
「ラグビーやってなかったらこんなにご飯食べなくていいし、人前で屁もしねぇのにな」
と言いながら平然と屁をこきまくっていたりする。
では、どうしてラグビー部に入ったのかと彼に尋ねると、
「ラグビー部に入っていなかったら友達ができなかったから」と答えるのだが、
大学のクラスでは、面白いと大評判で、女の子のファンができてしまうほどの人気者の彼なら、どんなサークルに行ってもきっと楽しい大学生活が待っていたはずだ。
僕は杉井智哉という人間に憧れている。
一つは、彼の「周りの目を気にしない」性格だ。
彼は人前で平気で屁をこくし、
学食をコートと半ズボンという世にも奇妙な組み合わせでぶらつくし、
いつも上着のポケットから間食用のバナナをちらつかせながら歩いている。
彼はありのまま、彼の感性のまま生きているような気がする。自分に正直なのだ。
周りの目ばかり気にしてきた僕は、彼のような生き方にとても憧れる。
人前で屁をこきたいとは思わないし、学食では無難な服を着たいし、バナナはリュックに入れて持ち運びたいとは思うが、
もっと本質的な部分で、彼のようになりたいと思う。
もう一つは、彼の練習への姿勢だ。
僕は、練習の時、よくミスを恐れ、そして周りの目を気にする。
自分がよく理解できていない新しい練習や、苦手な練習では、
順番待ちの列の後ろの方にまわってしまったり、
一番ミスをしなさそうなポジションを探してしまう。
パス練では先輩たちに遠慮したり、周りの目を気にして、一番外のポジションに必要以上に入ってしまったりする。
一方で、
彼は、ラグビーの練習の時、とても生き生きしている。
向上心があり、そして恐れを知らない。
パス練では、誰よりもボールに触る回数を多くしようと、積極的に内側に入るし、
どんな練習でも、 このポジションが鍵になる という所に進んで入ろうとする。
自分の「やりたいと思う気持ち」に素直で、「成長」に貪欲なのだ。
とてもラグビーが嫌いだとは思えない。彼はラグビーを楽しんでいる。
そして、それこそが彼の強さの秘訣なのだと思う。
B3には先輩、同期に沢山のライバルがいる上に、
今年は後輩という下からの大きなプレッシャーもかかってくる。
いつまでも遠慮してはいられない。
僕も杉井智哉のように「楽しむ」ことに、「成長する」ことに貪欲でありたいと思う。
拙い文章となってしまいましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。
次は先輩の杉浦さんにバトンを渡したいと思います。
杉浦さんも練習、そして試合中の生き生きとした表情が非常に印象的です。
ラグビーが大好きで、まさにラグビーのために生まれてきた人といっても過言ではないと思います。強くて上手いだけではなく、常に、考えてプレーし、それを言語化できるところに杉浦さんの本当のすごさがあるのではないかと常々思っています。
聞くところによると、杉浦さんは、最近、プライベートでいいことがあったみたいです。
中高時代、彼女はおろか、女性の友達すら1人もいなかった僕にとっては、
同じ男子校出身でありながら、高校時代に複数人の女性との交際歴があった彼と、
同じ 「男子校出身」 というカテゴリーで一括りにされることに対して、いつも強い憤りを覚えています。真の男子校生としてのプライドが疼くのです。
(共感できた新入生の方は相当まずいです。くだらないプライドは早く捨てましょう。さもないと僕のように暗黒の大学生活を送ることになります。)
彼の持つ自分への自信は、僕にはないものです。僕も彼のように、ラグビーに対して強い自信が持てるように、人一倍、練習に励んでいきたいと思っています。
杉井智哉。東京大学ラグビー部2年。
県立浦和高校ラグビー部出身で、ラグビーエリートであるところの彼は、
昨年、1年生でありながら、いち早くジュニアからシニアチームに合流し、
8月の慶應戦では、スタメンに選ばれ、
途中で鎖骨を骨折しながらもプレーし続けたという逸話を持つ、ワイルドな奴である。
しかし、普段の杉井智哉はラガーマンのイメージとはかけ離れたような言動をとる。
彼はいつも「ラグビーなんか早く辞めたいよ」とボヤくのだ。
確かに、
彼はきっちりと筋トレのノルマをこなしてはいるが、
「こんな時間があったら、家で寝転がりながらyoutube見てたいのに」
とラガーマンの風上にも置けないような愚痴をこぼしたり、
学食では大盛りのご飯に苦戦しながら、
「ラグビーやってなかったらこんなにご飯食べなくていいし、人前で屁もしねぇのにな」
と言いながら平然と屁をこきまくっていたりする。
では、どうしてラグビー部に入ったのかと彼に尋ねると、
「ラグビー部に入っていなかったら友達ができなかったから」と答えるのだが、
大学のクラスでは、面白いと大評判で、女の子のファンができてしまうほどの人気者の彼なら、どんなサークルに行ってもきっと楽しい大学生活が待っていたはずだ。
僕は杉井智哉という人間に憧れている。
一つは、彼の「周りの目を気にしない」性格だ。
彼は人前で平気で屁をこくし、
学食をコートと半ズボンという世にも奇妙な組み合わせでぶらつくし、
いつも上着のポケットから間食用のバナナをちらつかせながら歩いている。
彼はありのまま、彼の感性のまま生きているような気がする。自分に正直なのだ。
周りの目ばかり気にしてきた僕は、彼のような生き方にとても憧れる。
人前で屁をこきたいとは思わないし、学食では無難な服を着たいし、バナナはリュックに入れて持ち運びたいとは思うが、
もっと本質的な部分で、彼のようになりたいと思う。
もう一つは、彼の練習への姿勢だ。
僕は、練習の時、よくミスを恐れ、そして周りの目を気にする。
自分がよく理解できていない新しい練習や、苦手な練習では、
順番待ちの列の後ろの方にまわってしまったり、
一番ミスをしなさそうなポジションを探してしまう。
パス練では先輩たちに遠慮したり、周りの目を気にして、一番外のポジションに必要以上に入ってしまったりする。
一方で、
彼は、ラグビーの練習の時、とても生き生きしている。
向上心があり、そして恐れを知らない。
パス練では、誰よりもボールに触る回数を多くしようと、積極的に内側に入るし、
どんな練習でも、 このポジションが鍵になる という所に進んで入ろうとする。
自分の「やりたいと思う気持ち」に素直で、「成長」に貪欲なのだ。
とてもラグビーが嫌いだとは思えない。彼はラグビーを楽しんでいる。
そして、それこそが彼の強さの秘訣なのだと思う。
B3には先輩、同期に沢山のライバルがいる上に、
今年は後輩という下からの大きなプレッシャーもかかってくる。
いつまでも遠慮してはいられない。
僕も杉井智哉のように「楽しむ」ことに、「成長する」ことに貪欲でありたいと思う。
拙い文章となってしまいましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。
次は先輩の杉浦さんにバトンを渡したいと思います。
杉浦さんも練習、そして試合中の生き生きとした表情が非常に印象的です。
ラグビーが大好きで、まさにラグビーのために生まれてきた人といっても過言ではないと思います。強くて上手いだけではなく、常に、考えてプレーし、それを言語化できるところに杉浦さんの本当のすごさがあるのではないかと常々思っています。
聞くところによると、杉浦さんは、最近、プライベートでいいことがあったみたいです。
アイデンティティ[ラグビー部リレー日記]
投稿日時:2019/08/25(日) 22:18
運動量の多さと、体の大きさを武器に、大学からラグビーを始めた選手とは思えない活躍を見せている永山さんからバトンをいただきました、1年の國枝です。
初めてのリレー日記ということで、僕の入部動機について書かせていただこうと思います。
中学・高校は部活動と学校行事に明け暮れる日々。
ただ、目の前にあることをこなすだけで、将来のことなどろくに考えたこともなかった。
目の前に、茫漠と横たわる社会に対して、無関心で、視野の狭い自分。
最高学府である東京大学に進学したら、教育系や国際系などのサークルに入り、いわゆる“意識の高い人間”になろうと思っていた。
合格発表後のテント列や、サークルオリエンテーション。
様々な“意識高い系サークル”を周ったが、常に窮屈さを感じている自分がいた。
体裁の良い言葉で飾り立て、調子良くこしらえた夢を、背伸びをして語る自分に強い違和感を感じた。
東京大学運動会ラグビー部。
週5回のグラウンド練習。加えて週3回のウエイトトレーニング。
入部することになれば、4年間の全てをラグビーに捧げることになる。
だから僕は躊躇していた。
将来、社会に出た時に、身を助けるような、実用的なスキルや経験をこの4年間で得なければいけないのではないか。
部活に打ち込む4年間。今までの自分と何も変わらないのではないかと。
でも、気づけば新歓練習に足を運んでいる自分がいた。
ボールを持って、走る。
ただそれだけの単純な行為に、どうしてか、僕は夢中にならずにはいられなかった。
余計なことは考えず、こんな風に、毎日、真剣に体を動かすことができたらどんなに幸せだろうか。と考える自分がいた。
練習が終わり、グラウンドに寝そべると、心地良い疲れが押し寄せ、充足感に満たされた。
そして、かりそめの自分が剥がれ落ちていくのを感じた。
最終的に、僕は自分に正直であることに決めた。
東京大学運動会ラグビー部に入部することを決めた。
入部して、4ヶ月が経過した現在、
僕は自分の選択が間違っていなかったと考えている。
1つ1つの練習に、プレーに真剣に取り組む自分は、他のどんな時の自分よりも輝いていると思う。
現在はDLとして満足にプレーできない状態が続いているが、『リアル』から目を背けずに、
1つ1つのことを全力でやりきりたいと思っている。
そして、いつの日か、スイカジャージを着て対抗戦で活躍したいと思う。
拙い文章となってしまいましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。
次は、誰よりもストイックな姿勢で、チームを引っ張ってくださっているスタッフの太田さんにバトンを回したいと思います。
初めてのリレー日記ということで、僕の入部動機について書かせていただこうと思います。
中学・高校は部活動と学校行事に明け暮れる日々。
ただ、目の前にあることをこなすだけで、将来のことなどろくに考えたこともなかった。
目の前に、茫漠と横たわる社会に対して、無関心で、視野の狭い自分。
最高学府である東京大学に進学したら、教育系や国際系などのサークルに入り、いわゆる“意識の高い人間”になろうと思っていた。
合格発表後のテント列や、サークルオリエンテーション。
様々な“意識高い系サークル”を周ったが、常に窮屈さを感じている自分がいた。
体裁の良い言葉で飾り立て、調子良くこしらえた夢を、背伸びをして語る自分に強い違和感を感じた。
東京大学運動会ラグビー部。
週5回のグラウンド練習。加えて週3回のウエイトトレーニング。
入部することになれば、4年間の全てをラグビーに捧げることになる。
だから僕は躊躇していた。
将来、社会に出た時に、身を助けるような、実用的なスキルや経験をこの4年間で得なければいけないのではないか。
部活に打ち込む4年間。今までの自分と何も変わらないのではないかと。
でも、気づけば新歓練習に足を運んでいる自分がいた。
ボールを持って、走る。
ただそれだけの単純な行為に、どうしてか、僕は夢中にならずにはいられなかった。
余計なことは考えず、こんな風に、毎日、真剣に体を動かすことができたらどんなに幸せだろうか。と考える自分がいた。
練習が終わり、グラウンドに寝そべると、心地良い疲れが押し寄せ、充足感に満たされた。
そして、かりそめの自分が剥がれ落ちていくのを感じた。
最終的に、僕は自分に正直であることに決めた。
東京大学運動会ラグビー部に入部することを決めた。
入部して、4ヶ月が経過した現在、
僕は自分の選択が間違っていなかったと考えている。
1つ1つの練習に、プレーに真剣に取り組む自分は、他のどんな時の自分よりも輝いていると思う。
現在はDLとして満足にプレーできない状態が続いているが、『リアル』から目を背けずに、
1つ1つのことを全力でやりきりたいと思っている。
そして、いつの日か、スイカジャージを着て対抗戦で活躍したいと思う。
拙い文章となってしまいましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。
次は、誰よりもストイックな姿勢で、チームを引っ張ってくださっているスタッフの太田さんにバトンを回したいと思います。
| <<前へ |
2025年11月
| <<前月 | 翌月>> |
| |
| |
| |
| |
| |
アーカイブ
- 2025年11月(5)
- 2025年10月(13)
- 2025年9月(11)
- 2025年8月(11)
- 2025年7月(11)
- 2025年6月(10)
- 2025年5月(8)
- 2025年4月(9)
- 2025年3月(9)
- 2025年2月(15)
- 2025年1月(2)
- 2024年12月(18)
- 2024年11月(12)
- 2024年10月(12)
- 2024年9月(13)
- 2024年8月(11)
- 2024年7月(12)
- 2024年6月(8)
- 2024年5月(9)
- 2024年4月(8)
- 2024年3月(8)
- 2024年2月(19)
- 2024年1月(7)
- 2023年12月(9)
- 2023年11月(12)
- 2023年10月(11)
- 2023年9月(12)
- 2023年8月(11)
- 2023年7月(11)
- 2023年6月(8)
- 2023年5月(7)
- 2023年4月(8)
- 2023年3月(7)
- 2023年2月(15)
- 2023年1月(7)
- 2022年12月(23)
- 2022年11月(14)
- 2022年10月(13)
- 2022年9月(14)
- 2022年8月(14)
- 2022年7月(16)
- 2022年6月(10)
- 2022年5月(11)
- 2022年4月(12)
- 2022年3月(10)
- 2022年2月(15)
- 2022年1月(4)
- 2021年12月(12)
- 2021年11月(12)
- 2021年10月(14)
- 2021年9月(12)
- 2021年8月(12)
- 2021年7月(12)
- 2021年6月(11)
- 2021年5月(12)
- 2021年4月(11)
- 2021年3月(13)
- 2021年2月(10)
- 2021年1月(21)
- 2020年12月(11)
- 2020年11月(12)
- 2020年10月(13)
- 2020年9月(12)
- 2020年8月(14)
- 2020年7月(12)
- 2020年6月(12)
- 2020年5月(13)
- 2020年4月(12)
- 2020年3月(13)
- 2020年2月(12)
- 2020年1月(4)
- 2019年12月(10)
- 2019年11月(15)
- 2019年10月(11)
- 2019年9月(13)
- 2019年8月(13)
- 2019年7月(10)
- 2019年6月(8)
- 2019年5月(13)
- 2019年4月(7)
- 2019年3月(7)
- 2019年2月(5)
- 2019年1月(7)
- 2018年12月(15)
- 2018年11月(12)
- 2018年10月(15)
- 2018年9月(10)
- 2018年8月(7)
- 2018年7月(6)
- 2018年6月(10)
- 2018年5月(12)
- 2018年4月(11)
- 2018年3月(5)
- 2017年12月(11)
- 2017年11月(13)
- 2017年10月(12)
- 2017年9月(11)
- 2017年8月(12)
- 2017年7月(10)
- 2017年6月(10)
- 2017年5月(17)
- 2017年4月(10)
- 2017年3月(13)
- 2017年2月(4)
- 2016年12月(15)
- 2016年11月(12)
- 2016年10月(14)
- 2016年9月(12)
- 2016年8月(12)
- 2016年7月(15)
- 2016年6月(9)
- 2016年5月(9)
- 2016年4月(11)
- 2016年3月(10)
- 2016年2月(7)
- 2015年12月(8)
- 2015年11月(11)
- 2015年10月(10)
- 2015年9月(10)
- 2015年8月(5)
- 2015年7月(7)
- 2015年6月(11)
- 2015年5月(13)
- 2015年4月(8)
- 2015年3月(9)
- 2015年2月(12)
- 2015年1月(11)
- 2014年12月(12)
- 2014年11月(10)
- 2014年10月(12)
- 2014年9月(12)
- 2014年8月(12)
- 2014年7月(6)
- 2014年6月(5)
- 2014年5月(13)
- 2014年4月(11)
- 2014年3月(14)
- 2014年2月(7)
- 2013年12月(23)
- 2013年11月(29)
- 2013年10月(32)
- 2013年9月(30)
- 2013年8月(14)
- 2013年7月(15)
- 2013年6月(23)
- 2013年5月(33)
- 2013年4月(27)
- 2013年3月(20)
- 2013年2月(10)
- 2013年1月(1)
- 2012年12月(13)
- 2012年11月(11)
- 2012年10月(24)
- 2012年9月(13)
- 2012年8月(9)
- 2012年7月(5)
- 2012年6月(8)
- 2012年5月(11)
- 2012年4月(9)
- 2012年3月(10)
- 2012年2月(8)
- 2011年12月(6)
- 2011年11月(6)
- 2011年10月(7)
- 2011年9月(9)
- 2011年8月(10)
- 2011年7月(5)
- 2011年6月(5)
- 2011年5月(9)
- 2011年4月(7)
- 2011年3月(8)
- 2011年2月(4)
ブログ最新記事
- 埼玉旅行記 (11/16 18:05)
- 渋谷のサグラダ・ファミリア (11/15 20:40)
- 逆ナンなん? (11/13 16:34)
- バイト (11/12 10:31)
- モチーフで見る部員の部屋 (11/07 00:32)
- 自己開示 (10/31 13:42)
- ポスト考古学実習 (10/28 21:23)
- 白球に魅せられて (10/25 18:37)
- LoveType16 (10/25 11:46)
- 休みたい (10/25 07:09)
- No pain, no gain. (10/24 12:29)
- 銀杏 (10/18 07:50)
- ラグビーマン決戦・徳島頂上バトル (10/17 19:33)
- 名古屋に行きました。 (10/17 00:13)
- 勇気のいらない親切 (10/13 16:15)
- 懐かしのDAYS (10/10 16:14)
- アレルギー (10/04 23:56)
- 炎 (10/02 23:50)
- タックル怖くね? (09/29 22:08)
- surprise! mf (09/26 22:52)





.jpg)